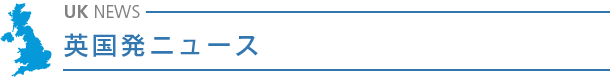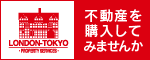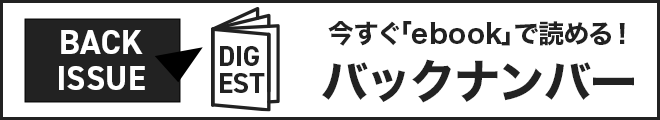日本語を母語としない英国及びアイルランドの大学生が、日本語でスピーチやプレゼンテーションを行い、その内容を競い合う本大会。スピーチ、個人プレゼンテーション、グループ・プレゼンテーションの3部門からなり、日本に関連するものから、母国や英国にまつわるものまで多様なテーマでの発表が行われた。
スピーチ部門では、「『当たり前』が生み出す逆差別~日本における社会通念の弊害」という題名でスピーチを行ったニューカッスル大学のラウラ・オンチュさんが栄えある優勝を手にした。オンチュさんは、日本では男女間における仕事と育児の負担のバランスが取れていないと指摘し、男性が会社に優遇されているという事実は、女性差別であるとともに男性への逆差別にも繋がるのでは、と持論を展開した。
2位に輝いたリーズ大学のジョセフ・マクルヒルさんは、「言語学習における非言語的伝達方法の重要性」と題し、自身が日本へ留学した際の経験談を交えつつ、真の相互理解のためには、非言語能力におけるコミュニケーションが必要不可欠であると主張した。3位に入賞したユニバーシティー・カレッジ・ロンドンのバンメイ・テイさんは、「日本のアニメが成功した理由と今後の発展に伴う問題」と題したスピーチの中で、日本のアニメ業界が抱える低賃金労働問題を取り上げ、今後の更なる発展のためにはクリエーターの労働環境改善は欠かせないと訴えた。
初級修了レベルの日本語能力保持者を対象とした個人プレゼンテーション部門では、中国の厳しいネット規制の現状に触れ、規制を緩和することが中国の民主化に貢献する、と提議したSOASのデニス・ソンさんが優勝。アイルランドの国民的な飲み物であるギネスの特徴を多角的な視点から紹介したブリストル大学のダニー・レーさんが2位に入賞した。
グループ・プレゼンテーション部門では、全4グループが各々のテーマに沿って、話し口調やロール・プレイなどの工夫を凝らした発表を行い、観客を沸かせた。(加藤久美子)


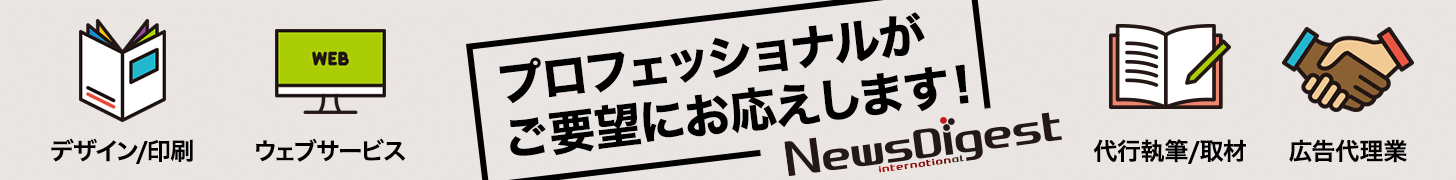

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?