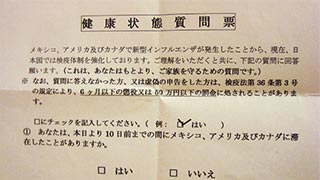ドイツ戦後史に新しい光を投げかける文書が発見された。1967年6月2日に西ベルリンで行われたデモの際に、当時26歳の学生だったベンノ・オーネゾルクが警官に射殺されるという事件があった。この際に発砲した警察官K・H・クーラスが、実は東独の秘密警察シュタージの密偵で、共産主義者だったことが、シュタージ文書管理局の研究員の調べで明らかになったのだ。クーラスもこの事実を認めている。
ドイツ戦後史に新しい光を投げかける文書が発見された。1967年6月2日に西ベルリンで行われたデモの際に、当時26歳の学生だったベンノ・オーネゾルクが警官に射殺されるという事件があった。この際に発砲した警察官K・H・クーラスが、実は東独の秘密警察シュタージの密偵で、共産主義者だったことが、シュタージ文書管理局の研究員の調べで明らかになったのだ。クーラスもこの事実を認めている。
なぜ、ドイツでこの発見が大きな波紋を呼んでいるのか。オーネゾルク射殺は、いわゆる「68年世代」にとって忘れることができない事件である。その理由は、この事件が西独で吹き荒れた街頭デモ、大学紛争、若者の政府に対する異議申し立ての引き金の1つとなったからである。
多くの若者はこの事件をきっかけに、西独政府に対して疑問や反感を抱くようになった。オーネゾルクを射殺した警官クーラスは、若者たち、特に左派勢力にとって「強権的な西独の抑圧体制」の象徴だった。彼は業務上過失致死の罪で裁判にかけられたが、「数人の若者に取り囲まれて身の危険を感じたので撃ってしまった」と述べ、無罪になっている。
このことはリベラル勢力を激怒させた。「我々も武装しなければならない」と主張する一部の若者はテロ活動に走り、RAF(赤軍派)を結成して政治家の暗殺や旅客機のハイジャック事件などを引き起こした。つまりオーネゾルク事件は、左派勢力が急速に過激化する引き金ともなったわけである。
歴史について「If(もしも)」を語ることは空しい。しかし仮に、当時の捜査でクーラスがシュタージに積極的に情報を提供していたスパイであり、東独の独裁党SED(社会主義ドイツ統一党)の党員だったことが判明していたら、若者たちはクーラスを単に「西独の暴力装置の象徴」とみなしただけでなく、東独政府に対しても強い反感を抱いたはずである。つまりこの警官がシュタージの密偵と暴露されていたら、西独社会のオーネゾルク事件に対する見方が大きく変わっていた可能性が高いのである。多くの若者が共産主義にも失望し、過激な活動に走ることを思いとどまっていたかもしれない。
シュタージ文書は、クーラスがオーネゾルクを撃った理由について記していない。重要な部分は廃棄されているからだ。「シュタージが西独社会を混乱させるために、クーラスに学生を撃つように指示した」という見方はうがちすぎだろう。シュタージにとっては、クーラスが当時西ベルリン警察で東からのスパイに関する捜査も担当し、東側に内部情報を提供していたことの方がはるかに重要だったはずだ。シュタージがクーラスに約1万5000マルクもの金を払っていたことは、彼が貴重な情報源だったことを示している。
シュタージはクーラスに関する実名索引カード(F16)を廃棄していたため、この重要な事実はドイツ統一後も埋もれたままになっていた。問題の文書は、別の調査をしていた研究員が偶然見つけたものだ。秘密警察の文書庫からは、これからも現代史を塗り替えるような事実が発見されるかもしれない。
5 Juni 2009 Nr. 768



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック ローマ教皇ベネディクト16世は、5月中旬にイスラエルを訪れた。彼はその際に、ユダヤ人たちと和解するための重要なチャンスを逃してしまった。
ローマ教皇ベネディクト16世は、5月中旬にイスラエルを訪れた。彼はその際に、ユダヤ人たちと和解するための重要なチャンスを逃してしまった。