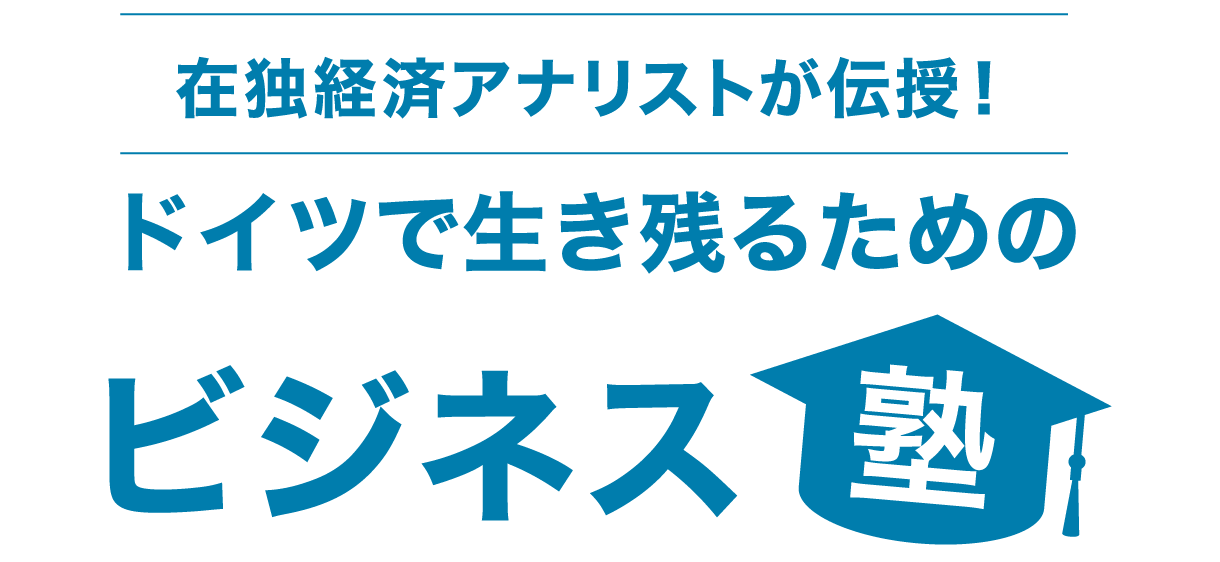第35回2026年のドイツ賃金交渉仕事と生活への影響は?
今年のドイツ賃金交渉は、一時金でお茶を濁すのではなく、基本給そのものをどれだけ底上げできるかが問われる年になりそうだ。人手不足と生活苦を背景に、労働組合側は引き続き強気であり、景気低迷にあえぐ企業側との衝突は避けられない。今回は、今年の賃金交渉の行方を予想し、私たちの仕事と生活への影響を読み解いてみたい。
- 今年のドイツ賃金交渉は難航必至。争点は「一時金」から「基本給アップ」へシフト
- 金属・電機と公共部門に注目。大幅賃上げを巡り、ストライキによる生活への影響も
- 目線は「+3〜4%」。従業員はこれを基準に交渉し、企業は投資と生産性強化を
基本給の大幅引き上げに労組がこだわる理由
まず、ドイツの労働組合側の主張を確認しておこう。ここ数年、彼らは「インフレ調整一時金」(2024年末まで免税)などの各種一時金を活用し、目先の手取り額の最大化に努めてきた。コロナ禍後のインフレで実質的に賃金が目減りした分を一刻も早く「取り戻す」ためだ。しかし、一時金はその名の通りあくまで「一時しのぎ」に過ぎない。そのため、今年以降の交渉における労組の基本戦略は、一時金依存を脱却し、基本給の恒久的な底上げを勝ち取ることにある。
具体的には、今年予想される2%程度のインフレ率に加え、過去の実質賃金目減り分を取り戻すための「キャッチアップ要素」を積み上げた数値を要求の根拠としている。「ドイツ経済の低迷が続くなか、そんなに高い賃上げに応じる原資がない」と主張する経営側に対し、労組側は「購買力の低下こそが内需停滞、経済低迷の主因である」として、高い賃上げの正当性を強く主張している。労組側の試算によると、2025年の実質賃金水準は、コロナ禍前の2019年に比べてまだ2.4%低い。今年の交渉は難航必至と予想せざるを得ない。
今年の焦点は金属・電機と州公共部門
今年の賃金交渉においては、10月末に期限を迎える金属・電機産業(労組:IGメタル、対象:373万人)と、昨年末から交渉が難航している州レベルの公共部門(労組:ヴェルディ、対象:教員、警察、病院など約110万人)の動向が特に重要だ。金属・電機産業の妥結結果は全産業のベンチマークとなりやすく、公共部門の交渉過程では「警告ストライキ」(Warnstreik)が仕事や生活にダメージを与えやすいためだ。
企業や政府側は、労組が要求する高いベースアップをそう簡単には受け入れようとしないため、労組は積極的に実力行使に打って出るだろう。特に公共部門のストライキは、学校の休校や役所手続きの遅延などを招くため、春先にかけてニュースのチェックが欠かせない。
昨年末に公表されたドイツ連銀の中期経済予測によると、就業者1人当たりの賃金は、昨年の+4.7%からは減速するものの、今年も+4.0%と非常に高い上昇が続く見込みである。ここ数年の妥結傾向から予測すると、労組が1年+8%程度の非常に強気な賃上げを要求するのに対し、実際の妥結額は2年累計で+6~8%(年平均+3~4%)という形に落ち着く公算が高い。これは+2%程度と予想される今後のインフレ率を上回る水準であり、労組が望む「キャッチアップ」がまた一歩前進することを意味する。一方の企業や州政府にとっては、かなり重い追加コスト負担となる。
予想される「賃上げ目線」と私たちが取るべきアクション
昨年までに妥結済みの賃金契約における2026年の昇給率は+2.5〜3.5%程度となっている。「+3〜 4%」という今年の賃上げ目線は、労働組合の協約賃金だけでなく、非組合員管理職や、枠外給与者(AT社員)の給与改定においてもベンチマークとなる。もしあなたが上司からこれより低い昇給を提示されたら、少なくとも納得できる説明を求める権利があるはずだ。
一方、企業経営者にとっては、基本給上昇による固定費増加を吸収するための業務効率化やデジタル化への投資が待ったなしとなる。少子高齢化に伴うシニア世代の大量退職が加速するドイツでは、来年辺りから失業率が急低下し、人手不足が一層深刻化するだろう。
サステナブルな人材確保と生産性向上のためには「魅力的な報酬」「働きやすさ」「やりがい」が欠かせない。賃金交渉を単なる分配の議論に終わらせず、持続可能な組織を作るための「未来への投資」と位置づけ、戦略的な一手を打っていただきたい。
ドイツ連銀中期経済予測
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP (前年比) |
+0.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | 大規模財政出動の割に弱い |
| インフレ (前年比) |
+2.3% | +2.2% | +2.1% | +1.9% | 中銀目標に沿って沈静化 |
| 1人当たり賃金 (前年比) |
+4.7% | +4.0% | +3.1% | +3.0% | インフレを上回る賃上げ継続 |
| 失業率 | 6.3% | 6.2% | 5.7% | 5.4% | 人手不足が深刻で失業率急低下 |



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック