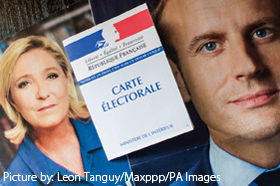コール元首相を悼み、記帳するメルケル首相
東西ドイツ統一を実現し、ユーロ導入など欧州統合の強化に貢献したヘルムート・コール元首相が、6月16日に87歳で死去した。ドイツと欧州の歴史の流れを大きく変えた政治家が、また一人この世を去った。
歴史の好機を逃さず統一を実現
メルケル首相は、同日行った演説の中で「コール氏の存在は、ドイツにとって幸運だった。彼が、歴史が与えたチャンスを逃さずにドイツ統一を実現したことは最高の偉業だ。我々ドイツ人はコール氏に感謝する」と述べ、統一宰相の功績を称えた。「コール氏は、私の人生をも大きく変えた」と語ったメルケル首相の胸には、複雑な思いが去来していたはずだ。社会主義国東ドイツで育ち、東ベルリンの研究所で物理学者として働いていたメルケル氏は、壁崩壊後に政治の世界へ飛び込んだ。彼女を1991年に婦人・青少年大臣に抜擢したのは、コール氏だった。メルケル氏は「コールのお嬢さん」と揶揄されながらも、キリスト教民主同盟(CDU)の中で急速に出世していった。
だが1999年に、CDUが多額の不正献金を受け取っていた問題が発覚し、コール氏が深く関与していたことが判明した。しかし彼は献金者の名前の公表を拒んだ。当時CDU幹事長だったメルケル氏は、不正献金事件を糾弾する公開書簡を新聞に公表し、「恩師」コール氏を糾弾して袂を分かった。この事件以降、コール氏はCDU内部で影響力を失い、逆にメルケル氏が党首として権力を手中にする。2005年には首相の座に就任した。コール氏は「飼い犬に手をかまれた」と感じ、メルケル氏との接触を断った。コール氏の未亡人が、ベルリンでの国葬ではなく、EUもしくは欧州議会が中心となる「追悼式典」を望んだ背景にも、コール家のメルケル首相への反感があると言われる。
戦争体験がコール氏を欧州統合へ駆り立てた
コール氏は1930年に南西ドイツのルートヴィヒスハーフェンで生まれた。第二次世界大戦の惨禍を経験した最後の首相である。兄の戦死や空襲などの体験は、彼を欧州統合に邁進させる最大の原動力となった。彼にとっては、欧州統合は欧州での戦争再発を防ぐための手段だった。コール氏は1946年にCDUに入党する。同党で彼は急速に頭角を現し、1959年にはラインラント=プファルツ州議会議員に初当選した。1973年にCDU党首に選ばれた彼は、1982年に52歳で西ドイツ最年少の連邦政府首相に就任する。
ボンの中央政界で、コール氏はしばしば「プファルツの田舎者」と軽蔑され、「国際感覚に欠ける地方政治家」と嫌われた。だが彼は1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊すると、東西ドイツ統一を実現する好機と判断し、党内・野党の反対を無視し、統一へ向けて突き進んだ。その政治的嗅覚は、評価に値する。
最大の難関は、第二次世界大戦中の旧連合国の承認を得ることだった。東西分断時代のドイツはまだ国家主権を持っていなかった。フランスのミッテラン大統領、英国のサッチャー首相、ソ連のゴルバチョフ書記長は、欧州の中心に約8200万人の人口を持つ大国が誕生することに強い懸念を抱いていた。しかしコール氏は、米国のブッシュ(父)大統領の強力な支援を取り付けることによって、ドイツ統一に関する国際条約「2プラス4」を短期間でまとめ上げた。
ソ連は最後まで統一に難色を示したが、コール氏はゴルバチョフ氏と直談判を重ね、強力な経済支援と引き換えに、旧東ドイツに駐留していた約34万人のソ連軍部隊を撤退させることに成功した。
1990年10月3日に東西ドイツは統一され、コール氏は第二次世界大戦後初めてドイツの国家主権を完全に回復させた。2カ月後の連邦議会選挙でCDUは勝利し、コール氏は統一後初めての首相に就任した。統一が実現した要因の一つは、ゴルバチョフ氏という革新的な政治家がソ連の最高指導者だったことだ。千載一遇のチャンスを逃さずに、猛スピードで統一を実現したことは、コール氏の大きな功績である。
欧州統合の理想に強い逆風
彼は欧州諸国の統一ドイツへの不安を取り除くためには、欧州統合を強化する必要があることを理解していた。このためドイツ人が深い愛着を持っていたマルクを廃止し、共通通貨ユーロの導入に踏み切った。コール氏は、「ドイツ政府の権限をEUに譲渡すればするほど良い」と確信していた。ナチス・ドイツが欧州全体に未曽有の被害を与えたことを踏まえて、ドイツにとっては、欧州の価値共同体の中に身を埋没させることが、最良の選択だと信じた。だがコール氏は統一後のドイツ経済の回復に失敗した。旧東独を中心に失業者数が急増し、国民の不満は強まった。1998年の連邦議会選挙ではゲアハルト・シュレーダー氏率いる社会民主党(SPD)の前に敗退し、首相の座を去った。ハンネローレ夫人の自殺、家庭の内紛、自宅での転倒事故など、晩年は数々の不幸に見舞われた。
コール氏が掲げた理想は今、強い逆風に遭遇している。右派ポピュリズムの台頭、BREXITやギリシャの債務問題など、EUの前には難題が山積。盟友米国も、一国主義・保護主義に傾斜し、欧州から離反する兆候を見せ始めている。コール氏が主張した「EUは戦争防止のためのプロジェクト」というスローガンだけでは、グローバル化とデジタル化に翻弄される庶民のEUへの不信感を弱めることはできない。
欧州統合を後戻りできない状態まで深化させるというコール氏の構想は、未完に終わるのだろうか。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック