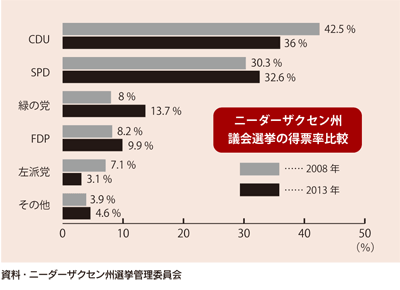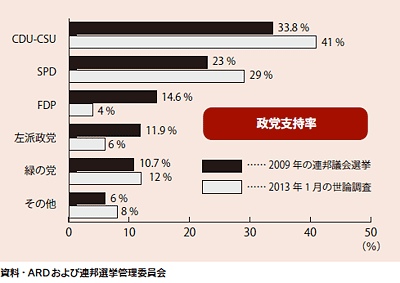今ドイツの地方自治体が、強く神経を尖らせている問題がある。それが、「Armutseinwanderer(貧困移民)」だ。読者の皆さんは「我々日本人には関係ない話」と思われるかもしれない。ところが、この問題は日本人を含むすべての外国人に飛び火しかねない危険な要素を含んでいる。私の21年前の経験を踏まえて、解説しよう。
急増する貧困移民
2007年には、ブルガリア、ルーマニア、セルビアなどの東欧諸国からドイツに移住した市民の数は6万4000人だった。しかしこの数は、2011年に14万7000人と、2倍以上に増加している。昨年上半期には、移民数が前年同期比で24%も増えている。今年1月には、7332人がドイツへの移住を申請。前年の同時期に比べて50%の増加だ。
貧困移民の大半は定住地を持たない「ロマ」(俗にジプシーと呼ばれることもあるが、正確な名称ではない)だが、政治的な迫害を逃れた亡命ではなく、経済的な理由でドイツへやって来たものと推定されている。ルーマニアやブルガリアでは、犯罪組織がロマたちから金を集めて、バスなどで西欧に移動させる例も報告されている。
問題は、欧州連合(EU)の指令により来年1月から、ブルガリアやルーマニアからドイツなど西欧諸国への労働者の移動の自由(Arbeitnehmerfreizügigkeit)が認められること。労働人口が域内で自由に移動することを奨励するEUの政策により、ロマたちもまるで国内を移動するかのように、欧州の中を移住することが可能になる。このためドイツ内務省は、この国を目指す移民の数が来年以降さらに増えると予測している。
社会保障支出も増加
現在、貧困移民が増えているのがベルリン、フランクフルト、マンハイム、ドルトムントなどの大都市。ノルトライン=ヴェストファーレン州では、デュイスブルクでロマの増加が目立ち、その数は約6000人に達している。同市では、炭坑や鉄鋼業の衰退によって空き家になったアパートが多く残っている。地方自治体が貧困移民をそうしたアパートに住まわせるので、この町で貧困移民の数が急増しているのだ。このためデュイスブルク市では昨年、社会保障関連の歳出が1800万ユーロ(21億6000万円・1ユーロ=120円換算)も増えた。
ベルリンのノイケルン地区では、ルーマニアとブルガリアからのロマ2400人が自営業者として登録し、子ども養育手当などを市役所から支給されている。地方自治体は、「EUの政策のツケを我々が払わされるのは不当だ」として、連邦政府に対応を求めている。これを受けてハンス=ペーター・フリードリヒ内務相は、「貧困移民をなくすには、ルーマニアやブルガリアの貧困を根絶することが最良の道」として、両国に働きかけることを約束した。
21年前にも同じ経験
ドイツは、1990年代に東欧からのシンティ・ロマの移民数が増えたことによって、すでに苦い経験を持っている。1992年夏に旧東ドイツ・ロストック市の団地街で、シンティ・ロマの数が急増。施設に入りきらなくなった移民たちは、団地の前の芝生で寝起きしていた。衛生状態が悪化し、住民たちは苦情の声を上げた。その後、ネオナチが亡命申請者の登録施設があった建物に放火し、付近の住民も拍手喝采を浴びせたのだ。
ベルリンの壁の崩壊以降、出入国規制が緩和されたために、東欧と西欧の間の人の行き来は比較的容易になった。この隙をついて、犯罪組織が東欧のシンティ・ロマたちを西欧に送り込む例が急増したのだ。しかし各国政府やEUが迅速に対応しなかったため、財政難に苦しむ地方自治体が責任を負わされる形となった。
1992年には、極右勢力による暴力が全国で増加。この年にネオナチに殺された外国人・ドイツ人の数は前年に比べて5倍以上も増えて、17人に上った。旧西ドイツのメルンやゾーリンゲンでは、ネオナチがトルコ人の住宅に放火して、多数の死傷者が出た。この年の極右による暴力事件の総数は、約2290件に達した。
極右勢力に追い風
シンティ・ロマの急増が引き金となって、社会全体で外国人に対する反感が高まったのだ。ビデオカメラの前で団地に火炎瓶を投げ込むネオナチの映像は世界中を駆け巡り、ドイツの対外的なイメージに深い傷が付けられた。ドイツはそれまで寛容だった政治亡命者の受け入れに関する規定を、厳しくせざるを得なかった。
現在、「貧困移民」の急増に地方自治体が手を焼く姿は、21年前にこの国が経験した悪夢を彷彿(ほうふつ)させる。この状況は、外国人の排斥を求めるネオナチ勢力にとって追い風となる。「貧困移民は税金や社会保険料も払っていないのに、高福祉社会ドイツを食い物にしている」という極右の主張にうなずく市民が増えるからだ。極右政党NPDは、すべての外国人を社会保険制度から締め出すことを綱領の中で提案している。
「この道はいつか来た道」とならないように、ドイツ政府とEUは早急に対策を取るべきだ。また、ネオナチの外国人排斥論への同調者が増えないように、ドイツのマスメディアも報道の仕方には細心の注意を払ってほしい。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック