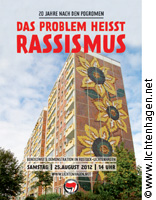ドイツ政府の税収はここ数年、飛躍的に改善している。2011年の税収は5730億ユーロ(57兆3000億円・1ユーロ=100円換算)。これは前年比で7.9%の増加。2012年度の税収も4.2%、来年の税収も3.5%それぞれ増える見通しだ。
連邦財務省によると、毎年の借金(いわゆる財政赤字)も減っていく予定だ。2012年には321億ユーロの財政赤字が、来年には41%減って188億ユーロになる見通し。2016年には、財政赤字ゼロを目指している。つまり4年後には歳出と歳入が均衡し、ドイツ政府は無借金経営を達成するのだ。ギリシャやイタリアが、税収不足に悩んでいるのとは対照的である。
財政状況が改善している背景には、いくつかの理由がある。まず、ドイツ経済がリーマンショックの悪影響から着実に回復し、特に中国やインド、南米向けの輸出が好調であることだ。企業収益が改善すれば、国庫には巨額の税金が転がり込む。
そして、この税収の伸びのもう1つの背景には、リヒテンシュタインやスイスなどに所得を隠していたドイツの富裕層が、次々に脱税の事実を自ら暴露し、滞納していた税金を払っているという事実がある。
そのきっかけとなったのは、2006年にリヒテンシュタインのLGT銀行の元行員が、銀行から盗み出した外国人の顧客データを、ドイツの諜報機関・連邦情報局(BND)に460万ユーロ(4億6000万円)で売った事件だ。
このデータを基に、2008年に税務当局はドイチェ・ポストのクラウス・ツムヴィンケル元社長の巨額脱税を摘発。同氏は1億ユーロの罰金を支払った。LGT銀行のデータによって500人を超える脱税犯が摘発され、税務署は滞納されていた税金6億2600万ユーロ(626億円)の回収に成功した。つまりドイツ政府は、LGT銀行の元行員に払った4億6000万円の報酬の136倍の税収を受け取ったのである。ドイツ政府にとっては、数億円の「投資」によって、その100倍を超える税収が国庫に転がり込むのだから、「安い買い物」ということになる。
だがリヒテンシュタインの法律に照らせば、この行員は銀行のデータを盗んだ犯罪者である。外国政府が、窃盗犯に多額の報酬を払ってそのデータを買うことは、犯罪を奨励することにつながる。本来ならば、盗品と知りながら購入することは、犯罪である。だがドイツ政府にとって、626億円もの税金を追徴できることの旨みは、あまりに大きいのであろう。法治国家であるドイツとしては珍しい、「超法規的措置」である。
実際、LGT銀行の事件を模倣して一攫千金を狙う者が増えている。今年8月にも、ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州政府が、900万ユーロ(9億円)を支払って、スイスの銀行から盗み出された顧客データを買ったことが明らかになった。NRW州政府が購入した4枚のCDには、スイスに所得を隠しているドイツの脱税犯の氏名や連絡先が含まれているものと見られる。これも、スイスの銀行からデータを盗み出した犯人に外国政府が巨額の報酬を与えているわけであり、銀行側は激怒している。
ドイツ側から見ても、脱税をしている市民全員が摘発されるわけではなく、CDにたまたま名前と住所が載っていた脱税犯だけが摘発されるのは不公平だという指摘もある。このためドイツのザビーネ・ロイトホイサー=シュナーレンベルガー法相は、「外国からの脱税に関する顧客データなどの購入を禁止する法律を施行するべきだ」と主張した。しかし、この提案はメルケル政権の中でもほとんど注目されていない。ドイツ政府にとっては、どのような手段であれ、脱税犯が摘発されて税収が改善されることは好ましいというのが本音なのだろう。
さらにLGT事件以来、スイスやリヒテンシュタインに所得を隠していた市民が、自ら脱税の事実を税務署に名乗り出て、滞納額を支払うケースが急増している。バーデン=ヴュルテンベルク州財務省によると、2010年の半ば以来、脱税の事実を当局に届け出た市民の数は9361人に達している。NRW州でもその数は約6300人に上る。
盗難CDとは別に、金融機関も以前に比べると捜査当局に情報を開示せざるを得なくなっている。かつてスイスやリヒテンシュタインの銀行については、「顧客の秘密を守る」という評判が高かった。ドイツの富裕層がこれらの国々の口座に所得を隠したのは、そのためだ。しかし今日では、テロ組織や麻薬組織の資金洗浄を防ぐ意味でも、捜査当局の依頼があれば、銀行は情報を提供せざるを得ない。
「天網恢恢(てんもうかいかい)疎にして漏らさず」という言葉がある。神様が悪人に対して張り巡らしている網は、目が粗いようでいて実は悪人をきちんと取り締まるという意味だ。この諺が示すように、税務署と司直は、我々をしっかりと見張っている。
5 Oktober 2012 Nr. 939



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック