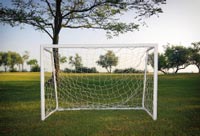©www.bilder.cdu.de
私は常々、「金融危機と不況のために政府が膨大な財政赤字を抱えているのに、本当にこれだけの規模の減税を行えるのだろうか」と不思議に思っていた。新政権で財務大臣に就任したヴォルフガング・ショイブレ氏(CDU)も同じ意見のようで、「国の金庫は空なのだから、2013年まで大規模な減税はあり得ない」と断言した。
ショイブレ大臣が大型減税を否定したことは、発足からわずか1カ月足らずの間に、閣内で深刻な意見の対立が生じたことを示している。特にFDPのギド・ヴェスターヴェレ党首は、面目をつぶされたようなものだ。彼は大幅な減税を約束したために連邦議会選挙の勝者となり、政権に参加することができたからである。FDPの支持者には、企業経営者や自営業者が多いが、彼らは「大型減税は選挙に勝つための口約束にすぎなかったのか」と大いに失望するだろう。
ショイブレ氏に援護射撃をするかのように、政府の諮問機関である経済専門家評議会は、11月に発表した経済情勢についての報告書の中で、「財政赤字と公共債務を減らす努力を始めるべきだ」と提言している。
この報告書の中で経済学者たちは、「メルケル政権が今後4年間に取り組むべき最大の課題は財政赤字の削減である。そのためには歳出を少なくとも370億ユーロ(4兆9950億円)減らす必要がある」と主張している。
ユーロ圏に加盟している国は、財政赤字の国内総生産(GDP)に対する比率を、3%未満に抑えることを義務付けられている。2009年にはドイツの財政赤字比率は3%ぴったりだったが、2010年には5.1%と大幅に増えると予想されている。
また報告書では、「来年の失業者数が今年よりも50万人増え、400万人に近づく」と予想されている。失業率の上昇は税収を減らし、地方自治体の負担を増加させる。
ドイツは今年、金融危機と不況の影響で、マイナス5%という史上最悪の経済成長率を記録した。来年は1.6%とプラスに転じると予想されているが、回復基調はまだ弱々しい。米国の不動産バブル崩壊によって、銀行のバランスシートに刻み込まれた深い傷はまだ癒えていない。こう考えると、メルケル政権に減税の余裕がないことは火を見るよりも明らかだ。公約通り減税を実現するただ1つの道は、国債を増発して借金でまかなうことだ。メルケル首相は、「経済状況はまだ不安定だ」として、公共債務を増やす方針を示唆しているが、経済学者の間では借金をしながら減税をすることについて強い批判が出ている。
特に、政府が財政赤字と公共債務の削減について具体的なスケジュールを公表しないことは、大きな問題である。ほかのユーロ圏加盟国も同じように借金経営を続けていることは、ユーロの安定性に大きな影を落としかねない。メルケル政権は、国民を納得させるような政策を打ち出すことができるだろうか。
4 Dezember 2009 Nr. 794



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック