 ドイツにお住まいの読者は、この国の人々が環境保護に熱心であることに、すでに気が付かれていることだろう。地球温暖化に歯止めをかけるための二酸化炭素(CO2)排出量削減は、いまや政治家、マスコミ、企業、市民が最も強く関心を持っているテーマの一つだ。
ドイツにお住まいの読者は、この国の人々が環境保護に熱心であることに、すでに気が付かれていることだろう。地球温暖化に歯止めをかけるための二酸化炭素(CO2)排出量削減は、いまや政治家、マスコミ、企業、市民が最も強く関心を持っているテーマの一つだ。
フランクフルトで1年おきに開かれるIAAは世界最大級のモーターショーの一つだが、今年は初めて環境保護がメーンテーマとなった。どのメーカーも燃費が良く、CO2の排出量が少ない車を前面に押し出したのである。だが国内自動車メーカーは、CO2削減をめぐって大きな悩みを抱えている。その理由は欧州連合(EU)が準備している新しい指針である。EUはヨーロッパで車を売るすべてのメーカーに対し、2012年までに新車が1キロ走る際に出すCO2の量を120グラム以下に抑えることを、法律によって強制しようとしているのだ。
現在、欧州自動車工業連合会に属するメーカーの車は、1キロ走るのに平均160グラムのCO2を出す。つまり、まだまだ大幅な改善が必要なのだ。大型で車体が重い車ほど、CO2排出量が多い。ということはベンツやポルシェ、BMWのように大型車の比率が多いドイツは、小型車が多いイタリアやフランスに比べて不利なのである。
国内自動車メーカーは「ディーゼルエンジンこそが、最も環境にやさしい技術」と考え、長い間ハイブリッド技術を軽視してきた。ところが、数年前になってようやく考え方を改め、他社と共同でハイブリッドエンジンの開発に乗り出した。だが、すでにハイブリッドカーを販売しているトヨタなどの日本のメーカーに、大きく水を開けられている。国内のメーカーが重い腰を上げたことは、CO2の大幅な削減を求める世論の圧力が、これまで以上に高まってきたことを示している。
メルケル首相は2020年までに、ドイツのCO2の排出量を1990年に比べて40%減らすことを目指している。政府が大きな期待をかけているのが、風力発電、太陽光発電、水力発電などCO2をまったく出さない再生可能エネルギーだ。現在、国内で消費される電力量のうち、再生可能エネルギーで作られているのは5%前後にすぎないが、政府のCO2削減目標を達成するには、2020年までにこの比率を約21%まで引き上げる必要がある。また、住宅の密閉性を良くし、暖房効率を大幅に高めることによって、エネルギーの消費量を減らそうともしている。
政府はこれらの気候保護プロジェクトの資金をひねり出すために、消費者が電力、ガス、暖房のための灯油を消費する際、「気候保護税(クリマ・セント)」を徴収することを検討している。経営者団体の試算によると、この税金が導入された場合、電力コストはいまと比べて5億4000万ユーロも高くなる見通しだ。企業からはこの計画に対し批判が出ているが、市民は「環境保護に費用がかかるのは仕方がない」と思っているのか、強い反対の声は聞かれない。
それにしても、再生可能エネルギーの比率を21%に拡大するというのは、野心的な計画だ。本当に実現するのだろうか。
28 September 2007 Nr. 682



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック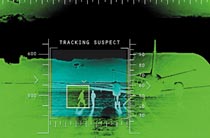 危ないところだった。ドイツの捜査当局は、ロンドンやマドリードのような同時爆弾テロがもう少しで発生するのを、未然に防ぐことに成功したのである。しかしこの事件は、ドイツ国内でも英国やフランスと同じように、過激思想を持ったイスラム教徒のテロリストが生まれつつあることをはっきり示すものであり、多くの政治家、捜査幹部を震撼させた。
危ないところだった。ドイツの捜査当局は、ロンドンやマドリードのような同時爆弾テロがもう少しで発生するのを、未然に防ぐことに成功したのである。しかしこの事件は、ドイツ国内でも英国やフランスと同じように、過激思想を持ったイスラム教徒のテロリストが生まれつつあることをはっきり示すものであり、多くの政治家、捜査幹部を震撼させた。 この夏、ドイツの多くの金融関係者は、バカンス気分になれなかったかもしれません。8月にデュッセルドルフの公的銀行であるIKB産業銀行が、米国での不動産投資のせいで巨額の損失を被ったというニュースは、金融界に強い衝撃を与えました。
この夏、ドイツの多くの金融関係者は、バカンス気分になれなかったかもしれません。8月にデュッセルドルフの公的銀行であるIKB産業銀行が、米国での不動産投資のせいで巨額の損失を被ったというニュースは、金融界に強い衝撃を与えました。 アフガニスタンでドイツ人が攻撃される例が、今年になって大幅に増えています。5月には、クンドゥスの市場で3人のドイツ連邦軍兵士が、自爆テロによって殺害されました。8月にも、ドイツ大使館員の警護任務のためにアフガニスタンに派遣されていた3人の警察官が、道路にしかけられた爆弾のために死亡しています。さらに、人道支援プロジェクトに参加しているドイツ人らが、誘拐される事件も増えています。
アフガニスタンでドイツ人が攻撃される例が、今年になって大幅に増えています。5月には、クンドゥスの市場で3人のドイツ連邦軍兵士が、自爆テロによって殺害されました。8月にも、ドイツ大使館員の警護任務のためにアフガニスタンに派遣されていた3人の警察官が、道路にしかけられた爆弾のために死亡しています。さらに、人道支援プロジェクトに参加しているドイツ人らが、誘拐される事件も増えています。 旧東独で、またもや呆れるような事件が起きました。8月20日、ザクセン州のミューゲルンという小さな町で、ドイツ人の若者50人が、8人のインド人を追いかけ、けがを負わせたのです。
旧東独で、またもや呆れるような事件が起きました。8月20日、ザクセン州のミューゲルンという小さな町で、ドイツ人の若者50人が、8人のインド人を追いかけ、けがを負わせたのです。





