ドイツではロックダウンにもかかわらず、新型コロナウイルスの新規感染者や死亡者の数が高止まりの状態にあるが、昨年12月27日(一部の地域では26日)にワクチンの予防接種が始まった。
 昨年12月26日、ドイツで初めて新型コロナワクチンを接種した101歳の女性
昨年12月26日、ドイツで初めて新型コロナワクチンを接種した101歳の女性
他国に比べて低い接種数
接種は介護施設に住む80歳を超える市民やコロナ病棟で働く医療従事者らから始まり、1月13日までに約69万人が第1回の投与を受けた(このワクチンは、約3週間の間隔を置いて2回注射する必要がある)。各州政府は全国に合計で約400カ所の予防接種センターを開設しており、今後接種の対象を70歳を超える市民、60歳を超える市民へと広げていく。
予防接種の滑り出しは、他国に比べてスムーズではなかった。このため一部の州首相から「欧州連合(EU)とドイツは、ワクチンの購入量が少なすぎたのではないか」という批判が出た。確かに13日時点では、EUでの投与数は米国やイスラエルに比べて少ない。
イスラエルではすでに国民の22.2%、英国では4.2%が1回目の投与を受けているが、ドイツでは0.82%にすぎない。ドイツではマインツのビオンテック社が米国ファイザー社と共に、早期にワクチンを開発したことを考えると、滑り出しの悪さは意外だ。
EUは約23億本を注文
連邦保健省のイェンツ・シュパーン大臣は、「EUやドイツの購入本数が少なすぎたわけではない。現在各国でワクチンの需要が急増しているのに対し、メーカーの製造が追いつかないのが最大の理由だ」と説明している。このためビオンテック社はマールブルクでもワクチンの製造を始めて、供給量を増やす方針だ。
ちなみにEUは、1月13日までに6社に対し合計22億6500万本のワクチンを注文している。調達先を1社に集中しなかったのは、事前に注文してもメーカーが開発に失敗する可能性もあるため、リスクを分散することが狙い。このうち欧州医薬品局が審査を終えて、欧州委員会に承認を勧告したのは、ビオンテック・ファイザーの製品と、米国モデルナの製品の2種類。ワクチンが1年に満たない短期間に開発されたことを考えると、欧州医薬品局が副作用の有無などについて時間をかけて審査を行うのは止むを得ないだろう。EUは「調達不足」という批判を受けて、1月8日にビオンテック・ファイザーの製品を3億本買い足して、合計6億本を注文し終えた。
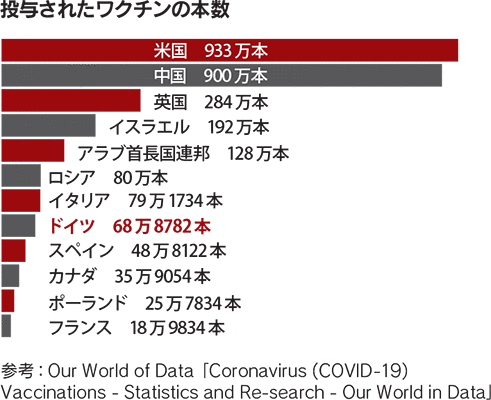
ゼーダ―首相「介護職に予防接種の義務化を」
さて、新型コロナウイルスによって重症化したり死亡したりする危険が最も高いのは、高齢者である。お年寄りの中には、糖尿病や心臓病などの基礎疾患を持っている人が少なくない。ロベルト・コッホ研究所によると、昨年12月23日までの累積死者数のうち、感染場所が判明している死者9692人の感染場所を調べてみると、82.9%が介護施設だった。
このためドイツ政府は介護施設で働く職員たちもワクチン投与キャンペーンの「第1グループ」に指定し、優先的に予防接種を行おうとしたが、ふたを開けてみると「副作用が心配なので予防接種を受けたくない」という職員の比率が予想以上に高かった。メディアは、「一部の介護施設では、職員の約70%が接種を拒否した」と報じている。ドイツ集中治療学会のアンケートによると、同国で介護業務を行っている人のうち、「予防接種を受ける」と答えた人の割合は約50%だった。
1月13日の時点では、ドイツではこのワクチンによる重篤な副作用は報告されていない。しかしソーシャルメディアの世界では、メルケル政権のコロナ対策に反対する勢力などが、予防接種についても否定的な情報を流している。このため一部の介護職員は、不安を感じているのだろう。
バイエルン州政府のマルクス・ゼーダ―首相は1月上旬に「介護施設の職員など一部の職業について、新型コロナウイルスの予防接種を義務化するべきだ」と発言して物議をかもした。しかし介護業界は、義務化に批判的だ。ドイツ介護従事者連盟(DBfK)のクリステル・ビーンシュタイン理事長は、「介護従事者の何%が予防接種を拒否しているかについての、信頼できる統計はない。3年間の研修を終えた介護従事者は、予防接種の重要性を十分に理解しているはずだ」と主張し、義務化に反対の意思を示した。
今のところ連邦政府は、全ての国民に対する予防接種の義務化については反対している。しかしドイツでは、ほかの病気についてはすでに予防接種で義務化されているものもある。昨年3月1日以降、学校や幼稚園に入るには、はしか(麻しん)の予防接種を受けたことを示す証明書を見せることが義務付けられている。こう考えると、一部の職種で予防接種義務が導入される可能性は否定できない。この国では当分の間、予防接種をめぐって激しい議論が行われるだろう。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック 毎年恒例の新年演説を行ったメルケル首相(12月30日撮影)
毎年恒例の新年演説を行ったメルケル首相(12月30日撮影)
 11月21日、緑の党のオンライン党大会で話すハベック氏(左)とベアボック氏(右)
11月21日、緑の党のオンライン党大会で話すハベック氏(左)とベアボック氏(右)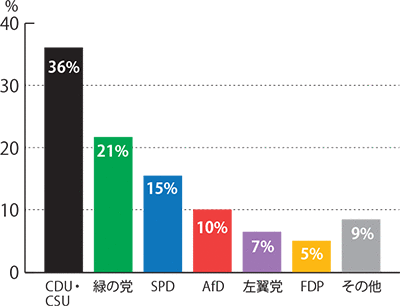
 11月9日、バイデン氏への祝辞を述べるメルケル首相
11月9日、バイデン氏への祝辞を述べるメルケル首相 10日に開かれたオンライン会議で話すメルケル首相
10日に開かれたオンライン会議で話すメルケル首相





