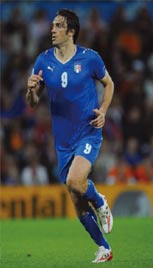フェスティバル当日は海の男たちが
ここぞとばかりに大活躍
スコットランド北東部のバンフシャーにある、小さな海辺の街での話。かつて漁業が盛んだったこの地域では毎年、6月末頃になると、「トラディショナル・ボート・フェスティバル」と題した昔ながらの伝統的な漁船の記念運行を始めとするイベントを開催している。昨年度は、初日となる土曜日こそ晴天に恵まれるも、翌日は大嵐となったために1年がかりの準備が台無し。さらに、土曜日の夜中に誰かが口笛を吹いているのを関係者が耳にしたのが問題となった。
なんで口笛ごときが騒ぎになるのかというと、どうやら同地では「海沿いで口笛を吹くと、側にいる悪魔が小馬鹿にされたと感じて、仕返しに強風を送る」という言い伝えがあるらしい。悪魔らしからぬ繊細さというか器の小ささが露見するような興味深い伝説ではあるが、ともかく今年度は二度と同じ轍は踏むまい、ということで街全体に口笛禁止令が発 令されたというわけだ。
さて、禁止令というからには気になるのが、その罰則措置。実際問題、口笛を吹いただけで、逮捕された日には地元市民はともかく、旅行者はたまったもんじゃないだろう。この辺りを主催者のロジャー・グッドイアーさんに直接問い質してみると、「口笛を吹いているのが見つかったら即座に、現地関係者から警告が与えられます。それでも言うことを聞かないようなら、そんな奴は海に放り投げてやります」と何だかやる気満々。そう、彼らはこの禁止令を出すことで、イベントを大いに盛り上げようとしているのだ。もはや悪ノリの領域まで達しているといってもいいだろう。
今年度における本イベントの開催日は、6月20日からの3日間。さて、その期間に悪魔の出番は来るのか。でも、英国で雨が降るたびに自分のせいにされるんじゃあ、悪魔も敵わないけどね。
BBC Online News
"Superstitious town bans whistling"



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック