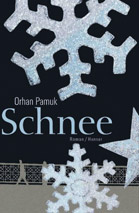一夜にしてあなたも外国人に!?
ある日、政府から「国籍を剥奪します」と 言われたら、あなたならどうしますか?南部カンヌに住むアブデルクリムさんは、1955年チュニジア生まれ。父親はアルジェリア人、母親はチュニジア人だ。生後3カ月で渡仏して以来これまで、フランス国籍を持ち、フランス人として暮らしてきた。しかしこのほど、移民局が各種書類の調査を行ったところ、過去の手続きミスが発覚したため、フランス国籍を剥奪されてしまった。50数年「フランス人」だった彼が、突如外国人となってしまったのである。
事の発端は2003年に遡る。当時、移民局から国籍に関する質問を受け取った彼は、1976年に発行された正規書類を提出した。それを受け2004年1月、カンヌ裁判所は、この書類を元に彼の家族全員に対しフランス国籍の正当性を認めたが、アブデルクリムさんのみが却下された。それは、「アルジェリア国独立後に行われた、フランス国籍維持のための手続きがなされていなかったため」という。
この出来事にさらに追い打ちをかけたのが、国籍紛失に伴い2004年に行ったフランス国籍の再申請手続きの結果だった。カンヌ移民局は、彼が1986年に暴力事件で書類送検されている事実を理由に、国籍の申請を却下したのだ。
とは言え、国立統計研究所(INSEE)のデータ上では、選挙時の際に必要となる有権者リストに依然として登録されており、先月行われた大統領選挙の時も、投票用紙が郵送されてきたという。カンヌのあるグラス市(アルプ・マリティム県)のクロード・セラ県知事も今回の事態に関して「(裁判所の)決定は、現状に矛盾している。早急に現状改善すべきである」とコメントしているが、有効な解決策は皆無というのが現状だ。
移民局は現在、彼に妥協案として「滞在許可証の申請」を勧めている。しかし彼は「なぜ、祖国で外国人にならなければならないのか」と、同提案を拒否している。先頃には、移民2世のサルコジ新大統領が就任したばかり。しかし現実には、その彼が「移民選別法案」を掲げている。果たして、フランスの移民に安息の日は訪れるのだろうか?
「Libération」紙 “Français depuis cinquante ans, désormais sans nationalité”



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック