
今では伝説となったタイタニック号
1912年4月14日の深夜に氷山に接触し、沈没した巨大豪華客船タイタニック号。処女航海にして、海の藻屑となったこの船にまつわる伝説は数多いが、今月とあるオークションに出品された「鍵」から、新たな英国の英雄の姿が浮かびあがることになった。
その「鍵」とは、タイタニック号に設置された郵便倉庫の扉を開くためのもの。今でこそ、度重なる紛失・遅配などが目立つロイヤル・メールだが、当時の英国の郵便は、そのサービスの良さを売り物にしていた。もちろん、ニューヨークに向けてイングランド南西部サザンプトンを発ったタイタニック号にも米国行きの多くの郵便物が積荷されていたわけだが、その管理を託されたのが、鉄道郵便員として15年の経験を持つオスカー・ウッディーさんを始めとする5人の優秀な郵便局員だったのだ。
皮肉なことに、船が氷山に接触した14日はウッディーさんの44歳の誕生日だった。氷山接触の事故が起きたのは、船上での彼の誕生日を祝うパーティーの真っ只中。それにも関わらず、事故の知らせを受けたウッディーさんら5人は、すぐに祝宴を止め、郵便物が保管されている場所へ向かったという。
しかし、保管庫となっていたGデッキには既に膝上辺りまで海水が入り込んでいた。「郵便物を確実に届ける」という自らの任務を果たすために、5人は凍えるような海水をもろともせず、水浸しになった手紙をかき集め安全と思われる場所へと移動させる作業を始めた。そして、その作業は船が沈没する瞬間まで続けられたという。
この惨事から生還した男性は当時を振り返ってこう言った。「逃げるように勧めても、彼らは首を横に振り作業を続けていました。当時タイタニック号で勤務できる者は、その業界の中でも上位1%に当たる優秀な人たちですから、仕事に対する人一倍のプライドがあったのでしょう」
鍵がオークションにかけられたことで改めて明らかになった、船上におけるさらなる悲話と、当時の郵便局員たちが持っていた仕事に対する責任感。このプライドが現代のロイヤル・メールに残っていれば、我々も安心して郵便を託せるのだが……。
「The Times」紙 Titanic key to a postman’s bravery



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック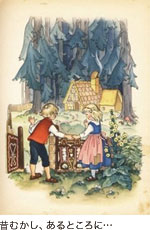 グリム童話の名作「ヘンゼルとグレーテル」のあらすじを覚えているだろうか。貧しいきこりの亭主とその後妻が、明日食べる物もなくなってしまったある日、口を減らそうと2人の子ども、ヘンゼルとグレーテルを森に捨ててしまうという話だ。そんなメルヘンの世界の出来事が何と現実に起きてしまった。
グリム童話の名作「ヘンゼルとグレーテル」のあらすじを覚えているだろうか。貧しいきこりの亭主とその後妻が、明日食べる物もなくなってしまったある日、口を減らそうと2人の子ども、ヘンゼルとグレーテルを森に捨ててしまうという話だ。そんなメルヘンの世界の出来事が何と現実に起きてしまった。 この広い宇宙のどこかに、地球と同じような知的生命体が存在するのではないのだろうか?そんな想いが「スターウォーズ」「猿の惑星」「宇宙大戦争」など数々のSF作品を生み出した。そして、世界各地からは数多くの未確認飛行物体の目撃証言が報告されているが、それらの情報はどれもタブロイド紙を賑わすゴシップ記事の範囲で真偽は定かではなかった。
この広い宇宙のどこかに、地球と同じような知的生命体が存在するのではないのだろうか?そんな想いが「スターウォーズ」「猿の惑星」「宇宙大戦争」など数々のSF作品を生み出した。そして、世界各地からは数多くの未確認飛行物体の目撃証言が報告されているが、それらの情報はどれもタブロイド紙を賑わすゴシップ記事の範囲で真偽は定かではなかった。 皆様は「ラップ・ダンス」なるものをご存知か。主に「紳士クラブ」と称するお店で提供されるサービスで、チップを渡すと踊り子さんが服を脱ぎながらお客の膝の上でクネクネと腰を振る、あのいかがわしい踊りのことである。ロンドンでは先日、このラップ・ダンスのチップをめぐる裁判があった。
皆様は「ラップ・ダンス」なるものをご存知か。主に「紳士クラブ」と称するお店で提供されるサービスで、チップを渡すと踊り子さんが服を脱ぎながらお客の膝の上でクネクネと腰を振る、あのいかがわしい踊りのことである。ロンドンでは先日、このラップ・ダンスのチップをめぐる裁判があった。 ゲーテやシラーの古典からグリム童話まで、原文で手軽に読めたら…、なんて考えている世界中のドイツ文学愛好者および研究者に朗報。ネット検索エンジン最大手グーグルの蔵書デジタル化プロジェクト「Google book search」にこのほど、ミュンヘンのバイエルン州立図書館が名乗りを上げたのだ。
ゲーテやシラーの古典からグリム童話まで、原文で手軽に読めたら…、なんて考えている世界中のドイツ文学愛好者および研究者に朗報。ネット検索エンジン最大手グーグルの蔵書デジタル化プロジェクト「Google book search」にこのほど、ミュンヘンのバイエルン州立図書館が名乗りを上げたのだ。





