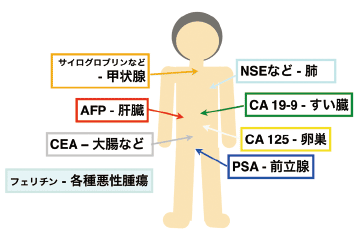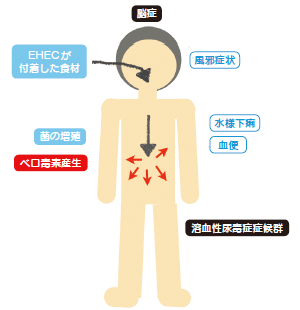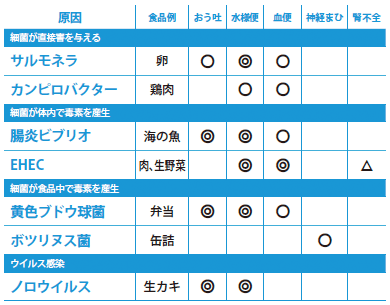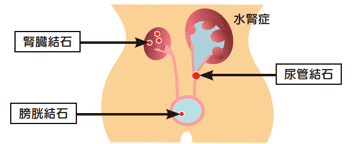胆石って?
胆のう(Gallenblase)はお腹の右上、肋骨の下辺りに位置する洋なし形の袋の臓器です。肝臓で作られた胆汁(Galle)を貯めておく貯蔵場所で、食べ物が胃から十二指腸に入ると中の胆汁を十二指腸内に放出し、脂肪の消化・吸収を助けます。この胆汁成分が石のように硬く固まったのが胆石(胆のう結石、Gallenstein)です。胆石の大きさは4〜5mm から2cm を超えるものまで様々。数も色々で、胆のう内に多数の胆石が詰まって見付かることがあります。また、砂のよう細かいものは「胆砂」、泥状のものは「胆泥」と呼ばれています。
胆石の成分は?
胆石の主成分はコレステロール、胆汁酸、ビリルビンです。胆石のほとんどは、高脂肪食や高カロリー食と関連するコレステロール結石です。その他、胆道系の感染によって生じるビリルビン結石(ビリルビンカルシウム結石)もあります。
増えている胆石保有者
日本人の20人に1人(500万人以上)が胆石を保有していると推測されます。胆石はやや女性に多い、中高年の疾患とされていましたが、最近では若い世代にも見付かっています。
胆石症の症状は?
健康診断などで見付かる胆石の多くは無症状(無症候胆石、サイレント・ストーン)です。見付かってから5年の間に何らかの腹部症状を経験する人は10人に1人、10年間では4人に1人です。「胆石症」は、胆石が胆のう出口や胆のう管に詰まった時に起こります。右上腹部の激しい痛みが主症状で、黄だんや発熱を伴うことも。腹痛は食後、特に脂っこい食事をした後に出現することが多く、右の背中や右肩の痛みを訴えることもあります。食後に上腹部の不定愁訴を感じるだけということもあります。
胆石の治療法は?
痛みのない胆石なら何の治療もせず、原則的に経過のみを観察します。ただし、3cm以上の大きな胆石や、胆のう壁が石灰化した陶器様胆のうは「胆のう癌」のリスクが高いため手術が考慮されます。石灰化のない小さな胆石に対しては、経口の胆石溶解剤(胆汁酸製剤)が用いられることもあります。
一方、症状のある胆石症は手術の適応となります。以前は開腹による胆のう摘出手術が一般的でしたが、最近は入院期間が短く、傷口も小さくて済む腹空鏡手術が増えています。胆のう癌の合併が否定できない場合には開腹による手術が選択されます。
また、結石が総胆管内にある場合は、症状の有無にかかわらず十二指腸内視鏡を用いて総胆管の出口である十二指腸乳頭部を介して結石の回収が試みられます。体外から胆のう内の胆石に衝撃波を当てて壊そうとする「体外衝撃波胆石破砕法(ESWL)」は、石灰化の有無、大きさ、個数により用いられますが、治療の限界もあり、日本ではあまり行われなくなってきています。
図1 胆のうの病気
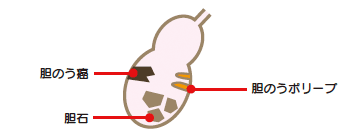
胆のう炎が合併した場合
胆石で流れが淀んだ胆汁に細菌(主に腸内の大腸菌)が感染すると胆のう炎になります。右上腹部からみぞおち部の痛み、悪寒・発熱、白血球数の増加が特徴です。治療の基本は手術です。
胆のう癌と胆石の関連
胆のう癌の多くに胆石の合併がみられます。しかし、胆石が胆のう癌を引き起こすという証拠はありません。胆石の経過観察では、胆のう癌を疑わせる変化の有無にも注意が払われます。
胆石の予防のために
胆石は体重過多で、血中トリグリセリド(中性脂肪)値の高い人に多くみられます。ドイツの美食やワイン、ビールに魅せられて高脂肪食、高カロリー食を続けている方や、運動不足で体重が増えている方は、食生活などライフスタイルの改善を心掛けましょう。
胆のうポリープ(Gallenpolyp)とは?
胆のうの壁の粘膜の一部が突起状に盛り上がった良性病変がポリープです。腹部超音波検査で指摘される機会が増え、成人の5〜10% に見付かっています。胆のうポリープの多くは、胆汁中のコレステロールが胆のう壁にくっついてできる大きさ5mm以内のコレステロールポリープです。複数個見付かることもあります。その他、胆のう壁の一部の過形成によるポリープ、胆のうの炎症によるものなどがあります。症状は全くありませんが、見付かった後は、経過観察が大切です。大きさ10mm を超える単発のポリープや、数カ月の間に急激に成長するポリープ、胆のう壁に変化が診られる場合は要注意で、CT検査などによる精査が勧められます。
| 胆石 | • 症状がなければ経過観察 • 腹痛、胆のう炎を起こせば手術 |
|---|---|
| ポリープ | • 大きさ5mm以下のコレステロール・ポリープが多い • 2個以上であることも少なくない • 桑の実形や球形 • 経過観察で良い |
| がん | • 10mm以上の大きさ • 1個(1カ所)だけのことが多い • 形が不整である • 手術が必要 |
胆のうポリープと癌
問題となるのは早期の胆のう癌と、悪性に変化する可能性のあるポリープです。今までの調査から、ポリープの大きさ(高さ)が16mm を超えると癌の可能性が60%、20mm以上では80% と言われています。仮に癌化が強く疑われた場合には胆のう全体の摘出手術が行われます。最近は腹空鏡による胆のう摘出術が行われるようになってきています。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック