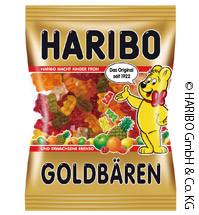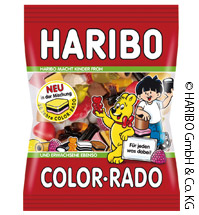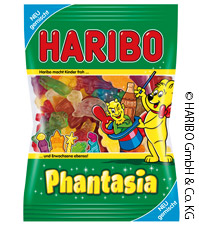ドイツで考える
資産運用術
お金や資産に関する意識を高めることは、より豊かな暮らしを実現させる第一歩。毎月何にいくら使っているのか、健康保険や国民年金にいくら支払っているのかなど身近なお金の運用について考えることからはじめてみましょう。これから紹介する心得や豆知識で資産運用の基本を知り、今日から実践してみてください。
(取材協力:山片重嘉、取材・執筆:栗原ちひろ)
資産運用、6つの心得
Point
1
少額でも長くが基本!
貯蓄の意識改革を
将来に備えた貯蓄の基本は「少ない額でも定期的に長く続ける」ことです。20代の頃は自分への投資、30~40代なら子供や新居への投資など、貯蓄が難しい理由はさまざま考えられますが、金銭的に余裕が出てきた50代からスタートするのでは遅すぎます。貯蓄は「複利」がポイントとなりますので、20代から少額でも定期的に少しずつ貯蓄をすることで今後の生活をより豊かに過ごすことが可能になります。
この「複利」とは、元々手元にあるお金、「元本」と貯蓄をすることで付随する利息に対し、さらに利息が付くというシステム。例えば25歳~65歳までの40年間、毎月100ユーロずつ4%の複利で運用する場合、4万8000ユーロの元本に6万8500ユーロの利息が付いて、最終的には11万6500ユーロとなります。このカラクリは下記のグラフのように双曲線状に利息が延びるため、時間をかけてゆっくりと貯蓄をするほど、利息を多く受け取ることができるのです。
貯蓄期間による複利効果の伸び
(複利4%で毎月100ユーロを40年間貯蓄する場合)
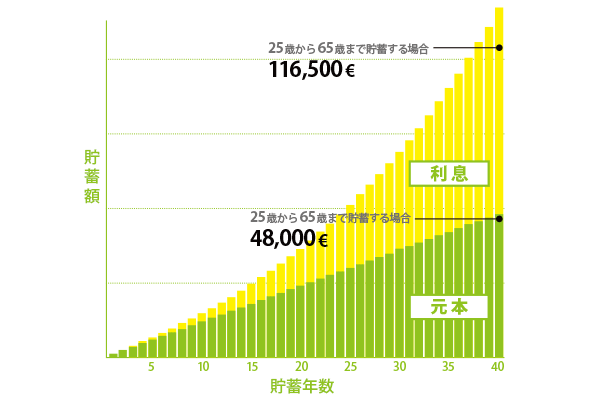
Point
2
投資は分散型が基本!
外貨両替の際にも活用が可能
積極的に投資を行なってみたいと考えている方は、まずは知識を増やすことが大切。銀行から購入する投資信託よりも手数料が低いETF(上場投資信託)もありますので、自分の納得のいく方法を見付けましょう。
このような投資をする際には分散投資、ドルコスト平均法を理解する必要があります。まず、分散投資とは投資対象を多様化させることと、一括で大きな金額を投資するのではなく毎月分散して投資することで価格変動のリスクを軽減させる方法です。また、ドルコスト平均法とは、一定期間ごとに一定の金額を投資をする方法のこと。例えば、毎月100ユーロを12カ月にわたって投資すると仮定します。下記の図のように景気の上昇に伴い株価も上昇するため、景気が良い時は100ユーロで購入できる株数は平均よりも少なくなりますが、景気が下降しているタイミングでは株価も下がるため、平均よりも多く購入することが可能です。景気は統計的にも波のように変動していくので、これもまた一括で投資するよりもリスクが軽減されます。
これらは株式投資をする場合にのみ当てはまるだけでなく、例えばユーロを日本円(またはその逆)に替えたい場合にも活用できます。ある程度の大きな金額を両替したい場合は、数カ月にわたって行なうことで、為替などの変動によるリスクが軽減できるのです。
ドルコスト平均法のイメージ
(毎月100 ユーロを12カ月にわたって投資する場合)
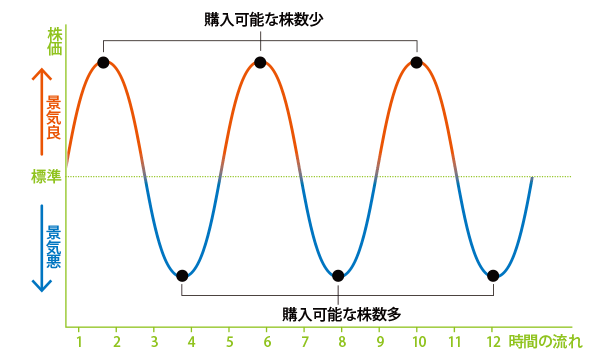
Point
3
もしもに備えた準備を
保険加入の重要性
お金の運用は増やしたり貯めたりするだけではなく、リスクに備えた保険への加入がとても重要です。万が一の事態が起こった際に余計な出費を減らすため、これらの保険はセイフティーネットとなります。掛け捨てにはなりますが、自分では支払いきれない大きな金額を請求された場合や、被害を起こしてしまった場合にカバーしてくれます。ここでは最低限入っておくべき、2つの保険について紹介しましょう。
個人賠償責任保険
Privathaftpflichtversicherung
過失により自分が加害者となった場合に適用される保険。他人を傷付けた場合(人的損害)、他人の物を壊した場合(物的損害)に損害を補償してくれます。下記でご紹介するようなトラブルをカバーしてくれるプランを保険会社と相談し、ベストなものを見付けましょう。金額は未婚、既婚、子供がいる場合など世帯によっても変動あり。ワーキングホリデーや語学学校など短期滞在者向けの月単位で加入できる保険もあります。
ドイツで想定し得るトラブル
| 状況 |
トラブルによる責任の内容(例) |
| 人の物を壊してしまった |
壊した物を弁償をする必要が出てくる |
| 鍵を失くしてしまった |
アパート全体の鍵を変えなくてはいけなくなった場合の鍵や鍵穴の工事費用などを支払わなければならない |
| 部屋で水漏れが発生 |
下の階のアパートに被害を与えた場合、修理・工事費用、またはインテリアなどを弁償する必要が出てくる |
| 人にケガをさせてしまった |
街中でぶつかった相手にケガを負わせた場合の治療費などを支払わなければならない |
歯の保険(追加健康保険)
zusätzliche Krankenversicherung
法定健康保険に加入している場合、歯の治療費を幅広くカバーしたい際には、追加健康保険に加入する必要があります。詰めものやインプラントなど、特に金額が大きくなることが予想されるマテリアルに関しては、これらがカバーされている保険に加入していないと自己負担しなければなりません。まずは自分が加入している健康保険会社にどのようなプランがあるのか確認してみましょう。プライベート保険の場合は、追加健康保険で加入するのではなく、プランを自由に選択することになります。
Point
4
ドイツで暮らす日本人も対象
お得な制度はフル活用を
ドイツにはある一定条件を満たしていれば日本人でも助成金や補助金、控除を受けられる制度がいくつかあります。それらの基本的な情報を知ることで、支出を減らすことができます。ドイツで暮らす日本人が知っておくべき基本的な制度は下記の4つです。※それぞれの制度は申請や手続きが必要になります。
1. 児童手当
Kindergeld
子供1人(~2人目)につき毎月194ユーロが受給できる制度。3人目からは200ユーロ、4人目以降は225ユーロとなります。基本的には子供が18歳になるまでの間支給され、その後も学生や職業訓練生である場合などは、最長25歳まで延長することが可能です。※この手当は、就労ビザの取得者が対象となります。駐在員の方は、受給できない場合もあります。
2. 両親手当
Elterngeld
子供を持つ前に働いていなかった専業主婦(主夫)も含め、すべての両親が対象の制度。子供の誕生月から基本的には12カ月間、毎月最低300ユーロを受給することができます。受給金額は前年度の収入に対して減った分の割合で決まります。また、子供の数に応じてそれぞれ12カ月間の受給が可能です。
3. リースター補助金
Riesterzulage
母親に直接受給権がある制度。子供が生まれた年を含めた4年間、年間60ユーロを自己負担することで助成金の積み立てることが可能です。年間の補助金額は大人1人175ユーロ、子供1人300ユーロ(2007年以前に生まれた場合は185ユーロ)。専業主婦(主夫)の場合は、配偶者が被雇用者であれば夫婦共に加入することで、間接的な受給権を得ることができます。
4. リュールップ年金の税金控除
Rüruprente / Basisrente
従業員が給与からの天引きで納めている法定年金とは別に、リュールップ年金に加入することで所得税控除のメリットがあります。例えば未婚者で月収が2500ユーロ、年間3万ユーロの給与額の場合は、約30%が控除されます。そのため、実質毎月の積立額の7割で10割分の貯蓄ができるということになるのです。
Point
5
老後の備えは
個人年金がおすすめ
被雇用者の場合、毎月給与からの天引きで法定年金を納めています。年金保険は名義人にとっては終生年金ですが、法定年金はでは配偶者に対する遺族年金は約半分になります(日本の国民年金には遺族年金はありません)。
また法定年金だけでは十分な年金を得られないので、国も個人年金への加入を推奨しています。
リュールップ年金であれば積立額は所得税を控除(例:15~40%)でき、配偶者も遺族年金として残額を100%受給可能です。その代わり受給は毎月年金のみとなります。プライベート年金は積立額の税控除はありませんが、一括受給も可能でその際のキャピタルゲイン税は半額になります。細く長く続ければ複利効果があり、毎月積み立てのため積立内容を一部株式ETFなどにすれば、ドルコスト平均法の効果(ポイント2を参照)も期待できます。
Point
6
資産価値はお金だけではない
自分への投資についても考えよう
そもそも「資産」とはお金に限ったことではありません。現在ではドイツに住んでいながらも自分のスキルを生かし、インターネットを介して日本からの仕事を受注をしたり、自ら情報を発信することが可能な時代です。
子育てがひと段落したタイミングでの社会復帰を考えた際や定年退職後に再び新しいことにチャレンジしようと考えた時に、自分自身の特技や技術、知識は財産になります。そのために、例えば旅行をして見聞きした知見や本を読んで得た知識、スキルを学んで得た技術に対しての「自己投資」は、ゆくゆく自分の資産を形成する大切な要素となります。
また、いつまでも健康でいるために運動をしたり食事に気を付けるための投資をすれば、老後も医者要らずの元気な身体が資産となります。これは余計な医療費の出費を抑えることにもつながるのです。このようにお金を直接生み出すための投資以外にも自分への投資の資金や時間を確保することも今後の社会を生きていく上で大切な要素となります。
お金を賢く運用するための
おすすめサービス3選
インターネットバンキング
N26
https://next.n26.com
無料で発行できるクレジットカード(デビットカード)を使って支払いをした場合に、連動したアプリで自動的に毎月何にいくら使用したのかを知らせてくれます。また、残高はリアルタイムで反映されるので、より正確な情報がすぐに手に入るのもポイント。家計簿をつけるのが苦手な人や、時間的に難しい人におすすめです。
Revolut.com
www.revolut.com
プリペイドのクレジットカードを作り(バーチャルカードは無料発行、実物のクレジットカードは6ユーロ)、プリペイドにチャージした金額をいつでもほかの通貨に為替手数料なしで両替できるシステムです。例えばイギリスに旅行に行きユーロをポンドに変えたい場合、瞬時に両替され、ポンドでのクレジットカード使用が可能に。旅行好きにおすすめ。
海外送金
TransferWise
https://transferwise.com
銀行よりもはるかに安い手数料で海外送金が行なえるサービス。日本円、ユーロ、ポンド、アメリカドルなどが可能です。仲介手数料は日本円であれば現在は0.8%(手数料率は変更の可能性もあり)、為替手数料はなし。日本語対応およびサポートがあるため、ドイツ語や英語が苦手な人でも気軽に安心して利用できます。
資産運用の豆知識
一生のうちで大きな買い物となる不動産と、最近話題の仮想通貨。この2つのトピックスについて、資産運用を考える際の知識として知っておきたい情報を解説します。
知っておこう、不動産投資の話 Q&A
 話を聞いた人
話を聞いた人
ウィンドゲート 代表取締役 尾嵜豪さん
ベルリンと日本に拠点を持つ不動産会社。「渋谷とベルリンの文化の架け橋のために、より良い不動産を」をモットーに、ドイツではベルリンを中心に不動産売買仲介や賃貸、管理などを、日本では渋谷区を中心に東京の不動産売買仲介や賃貸、管理などを行なっている。
http://windgate.co.jp
Q不動産投資とは?
A不動産に投資することは、労働の対価として得る収入ではなく、保有している資産によって収入を得るということです。
Q不動産投資のメリットとデメリットを教えてください。
Aメリットは、本業を続けながらも、賃料によって収入を得ることができる点、投資した部屋をほかの人に貸すことでその街との関わりができ、都市形成への社会貢献ができる点などが挙げられます。デメリットは賃料収入が入ってこなくなるリスク、建物の老朽化に伴う修繕費用がかかるリスク、物件の価値の低下によるリスク、日本に在住している方がドイツで不動産を買った場合は、為替変動のリスクなどが考えられます。
Q不動産投資が可能なのは、どのような人ですか?
A投資自体は誰もが可能です。ただし、融資を受けて投資をする際は、ある程度の手持ち資金を持っていると借りやすくなります。ドイツの場合は、州や地域によって土地の価格が異なりますので一概にはいえませんが、都市部でも日本円で1000万円程度のワンルームを購入することは可能です。
Q一般的に馴染みのある不動産投資といえばマイホームの購入だと思いますが、購入を考える際に抑えておくべきポイントを教えてください。
Aドイツで購入する際のポイントはいくつかあります。
①不動産は立地が最も重要になります。ドイツでは日本ほど駅からの距離は重視されないので、近隣の治安、レストランやショッピングセンター、公園、主要道路などへのアクセスの良い場所ほど価値が高くなります。そういった場所を選ぶことでリスクヘッジにもなります。
②定期的にきちんと修繕されたり管理されているかどうかを、エージェントに確認しながら見極めることが大切です。
③ドイツでは、「アルトバウ」と呼ばれる、築100年ほどの建造物が人気が高い傾向にあります。天井が高く、壁が分厚いので騒音を気にする必要がありません。また良い建材をふんだんに使用していることから、建物自体がしっかりしているのが人気の秘密です。
④ドイツには日本と違い地震がないため、築年数で価値が下がるという心配はそれほどありません。
Qマイホーム購入後、日本に帰国しなくてはいけない場合、購入した家はどうするのが良いでしょうか?
Aドイツでは長く住むことで税務上有利になります。ドイツが居住の拠点となる個人の場合は、10年以上住むことで原則として売却益に税金がかからなくなりますので、その期間住んでいるのであれば売却するのも良いでしょう。また、その他の選択肢としては賃貸として貸し出すことや、家具付きのマンスリー賃貸としての可能性も検討できます。
Q最近ではAirbnbのような形態で短期の貸し出しをする人もいますが、この方法は収益を得る上で有利でしょうか?
A通常の賃貸よりも収益率が良いのは事実ですが、多くのリスクがあるためおすすめはしません。まず、民泊は禁止されていたり制限されていることがあるため、場所によって違法になる可能性があります。また、多くの人が出入りするため、部屋をきれいに保つことができるか、かなり不透明です。
知っておこう、仮想通貨の話Q&A
 話を聞いた人
話を聞いた人
ファイナンシャルアドバイザー 山片重嘉さん
弊誌で「ドイツでお金と上手に付き合う方法」を連載中。ファイナンシャルアドバイザーとして、個人・法人へのアドバイスを行っている。また、自身が運営するサイト「DJ-Finanz」で、お金にまつわるさまざまな情報を発信している。年金保険の無料相談受付中!
https://dj-finanz.de
Q仮想通貨とは?
A仮想通貨は英語では「暗号通貨」という意味の「クリプトカレンシー」と呼ばれています。誰もが通信機器を持っていればインターネット上で第三機関を通さずともさまざまな情報を検索したり、直接誰かにメールや資料を送ることができるように、ビットコイン・仮想通貨も第三機関を通さなくても個人間で直接送ることが可能になります。インターネットを所有している人や会社がないように、仮想通貨もまた、国や会社、個人に属しているものではありません。そのためどこかの会社が潰れてもインターネットがなくならないように、仮想通貨もなくなることはありません。また、発行量の上限が定められているので、法定通貨のようなインフレのリスクがないのも特徴です。
Q仮想通貨を支えるブロックチェーンとは?
Aインターネットが生まれたことにより、情報が瞬時に世界中に届けられるようになった分、その弊害として写真や音楽、映画など著作権のあるものも簡単にコピーできるようになってしまいました。しかしお金で同様のことができてしまっては困ります。そこで仮想通貨の場合はこのようなことが起こらないよう考え出されたブロックチェーンを使って個人間でのお金のやり取りを可能にしています。
Q仮想通貨によってどのようなことが起こり得るのでしょうか?
A私たちが暮らしているドイツや日本は幸いなことに自国の通貨が強く、経済も比較的安定しているため、想像しがたいですが、世界には銀行口座を作れない人たちがたくさんいます。そういった人々も仮想通貨を使って自由にお金を送金することが可能になるのです。また、現状、自国の通貨が弱い国や経済が安定していない国では、自国の通貨をアメリカドルに換金したり、ゴールドに変えるのと同じように仮想通貨を購入する人が多いため、ビットコインなどの価値が高騰する場合があります。
Q仮想通貨を購入した場合に気を付けることを教えてください。
Aドイツでは仮想通貨を法定通貨との間で売買した場合や、また仮想通貨同士で売買をした場合には課税の対象となるので、確定申告が必要となります。ただし、1年以上そのまま保有した場合には、ゴールド(金地金)と同じように売却益に対する税金が免除されます。現状では仮想通貨は変動幅が大きく、全損の可能性もある非常にリスクの高いものなので、あくまでも失っても良いくらいの少額で試すのが良いでしょう。




 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック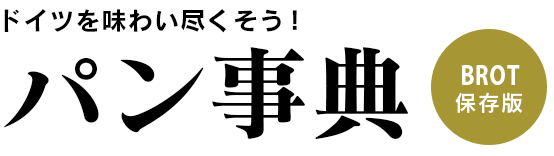
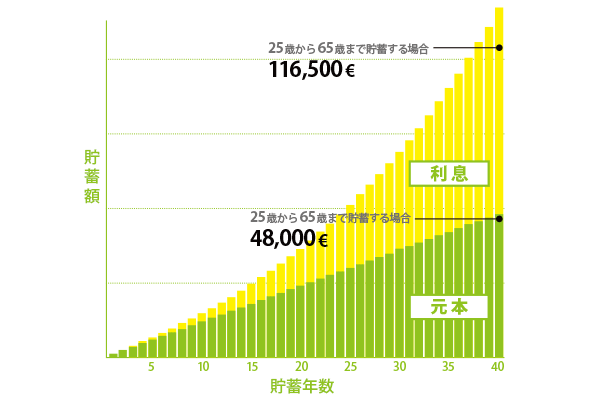
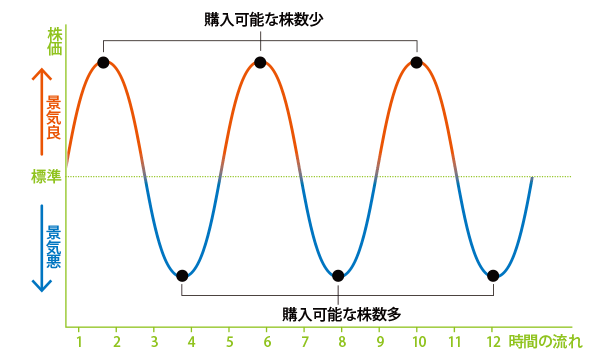


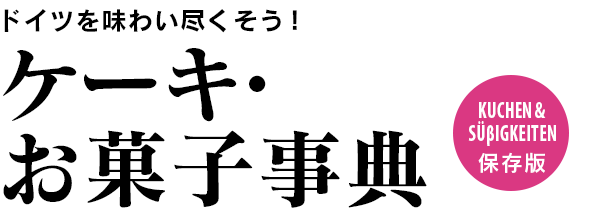



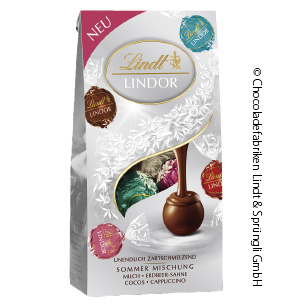

 スイスやベルギーなどのチョコレート名産地に隣接しているドイツだが、自国が生んだブランドも数多く存在している。価格も1ユーロ前後から高級品まで幅広く、また、スーパーやデパートでは選ぶのに迷うほど、多種多様なメーカーのチョコレートが販売されている。自分用はもちろんお土産にも最適で、幅広いシーンで活躍してくれる。
スイスやベルギーなどのチョコレート名産地に隣接しているドイツだが、自国が生んだブランドも数多く存在している。価格も1ユーロ前後から高級品まで幅広く、また、スーパーやデパートでは選ぶのに迷うほど、多種多様なメーカーのチョコレートが販売されている。自分用はもちろんお土産にも最適で、幅広いシーンで活躍してくれる。