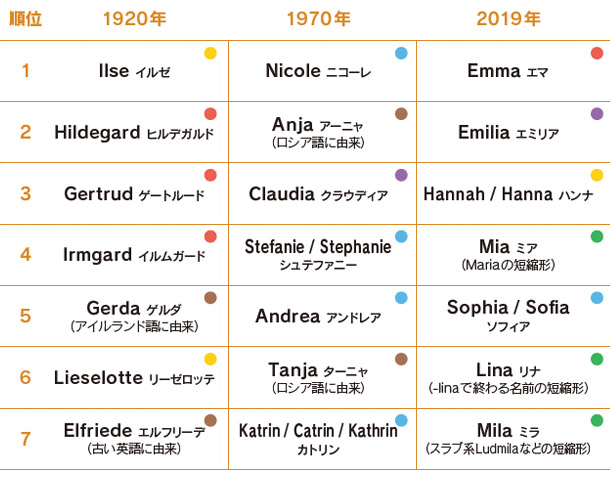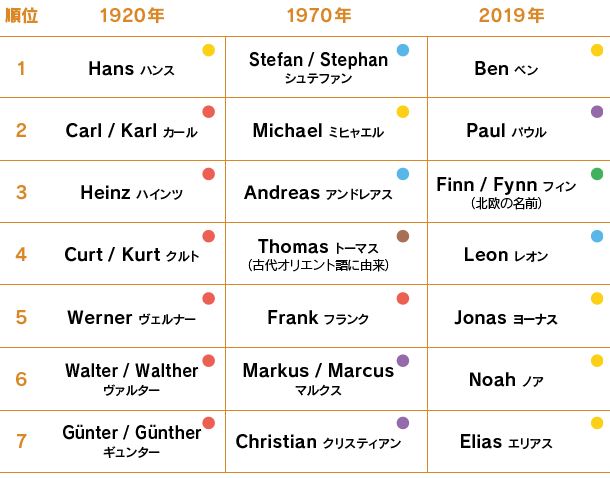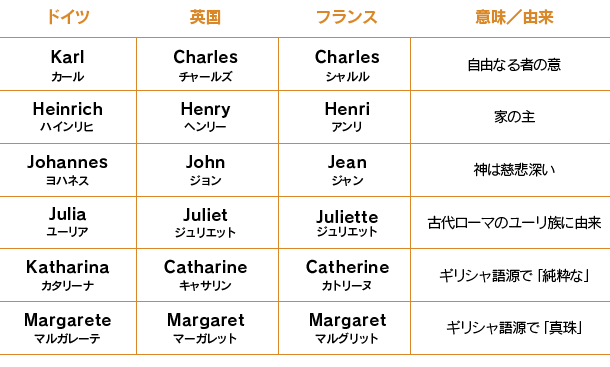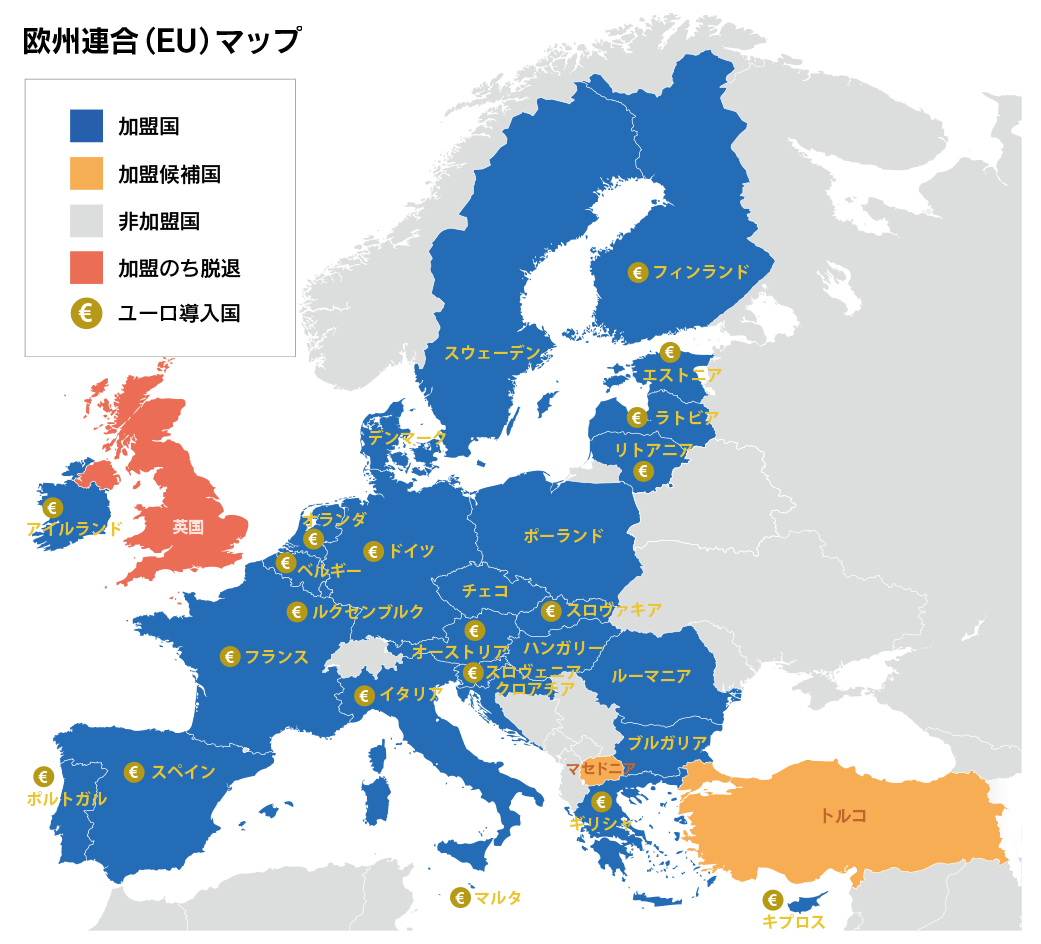あなたも森に行きたくなる! ドイツ人が森を愛する理由
ドイツ人に趣味を尋ねると、「森を歩くこと」と答える人が少なくない。休日にはたくさんの人が森を散策するだけでなく、サイクリングや乗馬を楽しむ人などで森がにぎわう。今回は、そんなドイツ人が愛してやまない「Wandern(ヴァンデルン) = ハイキング」の文化を紹介するとともに、これからハイキングデビューしたい方へお役立ち情報をお届け。森を歩けば、ドイツがもっと分かるかも?(Text:編集部)
ハイキングガイドに聞く!ドイツの森の楽しい歩き方
ドイツでハイキングデビューしたいけど、自分たちだけではちょっと不安……。そんな方のために、日本人初のドイツ・ハイキング連盟認定ガイド(Wanderführerin)の小野和美さんに、出発前の準備や注意点、ハイキングデビューにおすすめの森などを紹介してもらった。準備ができたら、さぁハイキングに出かけよう!
 小野和美さん Kazumi Ono
ハイデルベルク在住。日本人初のドイツ・ハイキング連盟認定ガイド。また、森林セラピーガイドの資格を持つ。オーデン・ヴァルトクラブ(Odenwaldklub e.V.)に所属。ハイキングに行きたい人の希望に合わせて、オリジナリティー溢れるハイキングプランを提案、ガイドを行っている。
小野和美さん Kazumi Ono
ハイデルベルク在住。日本人初のドイツ・ハイキング連盟認定ガイド。また、森林セラピーガイドの資格を持つ。オーデン・ヴァルトクラブ(Odenwaldklub e.V.)に所属。ハイキングに行きたい人の希望に合わせて、オリジナリティー溢れるハイキングプランを提案、ガイドを行っている。
ドイツ・ハイキング連盟(Deutscher Wanderverband)とは?
ドイツの人々が安全に楽しく森歩きをできるよう、ハイキングコースやハイカー用の宿泊施設・レストランの整備や情報提供などを行っている組織。ヘッセン州カッセルに本部がある。ドイツ各地の58のハイキング団体を取りまとめており、会員数はドイツ全土でおよそ6万人。130年以上の歴史があり、現在に至るまで歴代の連邦大統領が後援を引き継ぐ由緒ある団体だ。小野さんが所属するオーデン・ヴァルトクラブも登録団体の一つ。www.wanderverband.de
出発前に、ここをチェック!
1. 天気予報の確認
まずは自分がハイキングへ行く場所の天気予報をチェックすることで、着ていくべき服や持ち物が決まります。標高が高い場所は天気が変わりやすいので、レインウェアは必須です。ドイツの場合、森と森の間に木の生えていない田園地帯や麦畑を通り抜けることがあるのですが、そこでは強い風が吹くことが多いので、風よけできる服も便利です。
2. 体調管理
森の中に入ると、途中で体調が悪くなってもすぐに帰ることができない場合も。そのため睡眠不足や疲れがたまっている場合は、ハイキングルートや距離を調整しましょう。ドイツではむしろ体調改善やリフレッシュのために森へ行く人も多く、大切なのはその日の自分に合ったコースを選ぶこと。ハイキングガイドがいる場合は、必ず事前に体調を伝えてください。
3. 服装
ハイキングでは長時間歩くので、体温調節をしやすいように重ね着しましょう。寒い時期に重宝される保温性の高いインナーウェアは、温かくなり過ぎたり、汗が乾きにくく逆に体を冷やしてしまうことがあるため、ハイキングには不向き。ズボンは、動きやすくストレッチ性のある素材や、ゆとりのあるものを選んでください。
4. 持ち物
どんなに短いルートでも、飲み物、そして高カロリーな行動食(チョコレート、ナッツなど)を持参。また、特に夏のドイツの森はダニが多いので、ダニ除けスプレーや、ダニに噛まれた時のためにダニ除去カード(Zeckenkarte)があるといいです。登山用ストックは、歩くときに体のバランスが取れ、膝や腰への負担が軽減されるのでおすすめです。
ガイドの小話
超難関!ガイドへの道のりガイドからの注意点

もともと趣味で始めた森歩きですが、気づけば10年以上ハイデルベルクの森歩きグループに参加し、森に関する知識や地図の読み方を学びました。ドイツの森の魅力を日本にも紹介したいとの思いから、また私の所属団体の方々からの応援もあって、ハイキングガイドの資格試験に挑戦することに。
受験に向けて、ガイド養成のための9日間の合宿にも参加しました。合宿では、地図学や気象学、コンパスの習得はもちろん、生物学や地質学などの森の生態に関すること、旅行規約や保険、ツアーのプランニング方法など、毎日みっちり講義と実技があります。語学力的にも付いていくのが大変で、毎晩必死に復習しました。また、ドイツ赤十字の応急手当コースを受講するほか、グループ内でけんかが起きた際の解決法という驚きの実技も(笑)。
そうして試験を迎え、無事に合格。森歩きのプロとして、独自のハイキング企画を提供できるのはうれしいですね。今後は小さなグループを中心に、ドイツや日本をはじめさまざまな方に向けて、森の素晴らしさを丁寧に伝えていきたいです。
ガイドからの注意点
自然をあなどらない
自分で地図を読んで歩けないうちは、大きくて深い森には1人で入らない、ということを守っていただきたいです。私たちガイドも、お客様を森に案内する前に必ず2回は下見をしますが、そのたびに新しい発見があります。森の状況は、刻一刻と変わっていくもの。慣れていない人だと、例えば狩猟の時期に出ている狩猟場所のサインを見落としたり、木の伐採の時期に重なると、行けるはずだった道が全く通行できなくなっていることも。ドイツは基本的に「自己責任の国」ということもあって、日本だったら当然出ているはずの注意書きや柵が無い場所も多いのです。また、夏場は日が長いからといって、夜に自分たちだけで森に行くのもおすすめしません。森にいるうちに暗くなって足場が見えなくなったり、イノシシなどの動物の行動時間と重なったりすると危険です。安全あっての森歩きですので、あまり冒険し過ぎないようにしましょう。
小野さんおすすめのドイツの森
独特の文化や暮らしを味わえる 黒い森地方 Schwarzwald

ドイツ南西部1万1100平方キロメートルに広がる国内最大の低山地帯。針葉樹で形成されているため、1年中黒く見え、森の中も暗いことから「黒い森」と呼ばれています。黒い森には独自の文化があり、南ドイツの民芸品として知られるカッコウ時計の故郷でも。また、黒い森のさくらんぼケーキ(Schwarzwälder Kirschtorte)や黒い森のハム(Schwarzwalder Schinken)など、この土地ならではの食文化も充実しています。マスの養殖も行っていて、特に日本の方だと「南ドイツで魚が食べられるんだ!」と驚かれることが多いです。黒い森の魅力は、地元ならではの食文化や暮らしを森の中で見て体験できること。独特な雰囲気を楽しみたい方はぜひ訪れてみてください。
 黒い森のさくらんぼケーキ
黒い森のさくらんぼケーキ
 黒い森のハム
黒い森のハム
Schwarzwald Tourismus GmbH
黒い森観光案内所
Heinrich-von-Stephan-Str. 8b, 79100 Freiburg
www.schwarzwald-tourismus.info
歴史の足跡をたどれる オーデンの森 Odenwald

ヘッセン州のダルムシュタット、ハイデルベルク、バイエルン州のアシャッフェンブルク、バーデン=ヴュルテンベルク州のハイルブロンにまたがる森。ここにはローマ人やケルト人の遺跡がたくさん残っているため、歴史や遺跡がお好きな方におすすめです。ゲルマン人からローマ帝国を守った辺境防壁沿いでは、ローマ浴場や望楼などの遺跡を見ることができます。また、オーデンの森内にあるメッセル採掘場は大量の化石が発掘されており、ユネスコ自然遺産としても知られる場所です。何百万年も前に噴火した珍しい地層が見られ、自然観察に興味がある方にも満足いただけると思います。
Odenwald Tourismus GmbH
オーデンの森観光案内所
Marktplatz 1, 64720 Michelstadt
www.tourismus-odenwald.de
ワイン好きがこぞって訪れる プファルツ地方の森 Pfälzerwald

周辺の大都市圏の人々がリラックスできる場所として、1950年代から保護されてきた自然公園。1992年にユネスコによって生物圏保護区に登録され、1998年以降はフランスの北ヴォージュと国境を越えて共同プロジェクトなどに取り組んでいます。プファルツワインで有名なプファルツ地方の森とあって、ハイキングの途中でブドウ畑を眺めたり、ランチタイムにそこで造られたワインを楽しめるのが魅力の一つです。温暖な気候と年間1800時間以上の日照時間から「ドイツのトスカーナ」と呼ばれ、レモンやイチジク、ヤシなど、温帯を好む植物が自然に生育。ドイツで一番早く春が訪れる場所ともいわれます。
Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen
生物圏保護区プファルツの森・ヴォージュ山脈北部
Franz-Hartmann-Str. 9, 67466 Lambrecht
www.pfaelzerwald.de
ハイキングの楽しみ
個性豊かなガイドたちによる「ドイツ流おもてなし」
森の中で大合唱
ドイツ人グループのハイキングでよく見る光景ですが、誰かが歌集を持ってきて、みんなで歌うことがあります。私の周りにも歌好きのガイドが多く、休憩中に参加者に歌詞カードを配ったり。彼らのおすすめの曲は「Der Mond ist aufgegangen(月が昇った)」、「Der Jäger aus Kurpfalz(プファルツ地方の猟師)」など。もちろん歌詞にはドイツの木や森が登場します。
シュナップスで乾杯!

こちらもハイキングガイドの気の利いたサービスの一つで、ドイツの蒸留酒である「シュナップス」を振る舞う人も。冬場の森歩きはやはり寒いので、歩いている間は大丈夫でも、休憩などで立ち止まるとどんどん冷えてしまう。そんな時に、体を温めるという目的でみんなで乾杯。もちろん、しっかり歩けるように飲みすぎは厳禁ですが、ちょっといい気分になって歩くことができますよ。
参考:www.waldkulturerbe.de、Bundesministerium für Ernährung und Landwirschaft「Der Wald in Deutschland」、石田仁志ほか著「トポスとしての〈森〉の系譜 (近世近現代編-漢字文化受容から西洋文化受容へ-)」、池田憲昭「ドイツにおける森と地域と教育」講演記録より、北村昌美「森林と林業の「これから」を考えるために」



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック