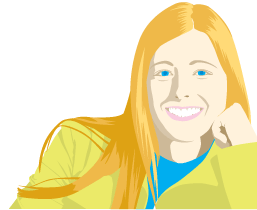Nr. 15 公私の境界線
 一見、個人主義が徹底していて、一人ひとりが好きなことを主張しながら自由に暮らしているように見えるドイツ社会ですが、実際に住んでみると、個人の「暮らし方」に関しては意外と社会的プレッシャーが強い、と思うことがしばしばあります。日本では、休日をテレビの前で過ごそうと、家族と一緒に出かけようと、日常の過ごし方を他人から干渉されることはあまりありませんが、ドイツ人同士では案外他人の日常生活に注目していたり、プレッシャーを感じたりする人が多いようです。
一見、個人主義が徹底していて、一人ひとりが好きなことを主張しながら自由に暮らしているように見えるドイツ社会ですが、実際に住んでみると、個人の「暮らし方」に関しては意外と社会的プレッシャーが強い、と思うことがしばしばあります。日本では、休日をテレビの前で過ごそうと、家族と一緒に出かけようと、日常の過ごし方を他人から干渉されることはあまりありませんが、ドイツ人同士では案外他人の日常生活に注目していたり、プレッシャーを感じたりする人が多いようです。
“ドイツ人は家庭を大切にする”と言われますが、よく見てみると、ドイツ社会では個人の家庭生活が完全な「私」ではなく、多分に「公」的な要素を含んでいる、ということがわかります。日本では「私事」であると思われていることが、「公」の社会生活の一部であることが多いのです。そこで今回は、ドイツ人の家庭生活の中で、対外的に重要なシグナル効果を持つ部分をいくつか取り上げてみましょう。
所有物のメンテナンス
物づくりを生業にしていた庶民の多いドイツですが、昔は店であろうが、砥石だろうが、かな床だろうが、マイスターになったら生産資本はギルド(組合)から借りて、死んだらまたギルドに返すものでした。ギルドのメンバー同士、代々の共有財産である生産資本を預けるのはモノの価値が守れる人間に限る、と監視し合っていた時代が何百年も続いていたのです。当然、日ごろからそういった能力を対外的に誇示しておかなければ、ギルドでの登用や出世に大きな影響が出ていました。
土曜日をまるまる家や車のメンテナンスで過ごす人も珍しくありませんが、会社での休日出勤を頑なに断って自分の所有物の手入れに精を出すドイツ人を見て、これは個人的な物欲の表れだろうか、などと困惑する前に、そのような行動が社会的に重視された歴史的な背景にある、ということを知っておくことが大切でしょう。
規則的な出勤、帰宅、休暇
決まった時間に家を出て、定時に帰宅することは、生活を計画的に把握して、効率よく暮らしている証拠と見なされます。時間を目いっぱいに使って暮らそうと思ったら、計画を立てなくてはならないと考えられているからです。しなくてはならないことをしっかりと合理的に把握し、事前にしっかりと時間配分をしていることが最も生産性の高い暮らし方だ、という社会通念があるのです。アーティストやワンマン起業家などは別として、地道に会社員として暮らしている人に「臨機応変」は必ずしも「カオス」ではなく、時間を目いっぱいに活用する生産性の高い別の方法なのだ、と納得させることは至難の技でしょう。臨機応変の対応や柔軟性を求める外資系企業の要請を理解させようと思ったら、環境を整え、しっかりとした論拠を提供したうえで説明しないと、議論は平行線で終わってしまうはずです。
これは休暇のとり方についても言えます。計画通りに一定期間休暇に出かけることは、単に娯楽を追及しているだけではありません。暮らしが計画通りにうまく運営されており、支出と収入のバランスも計画通りに取れていることを対外的に誇示する行為です。不景気になると、休暇に出かけたと偽って、食料を2週間分買いこんで家の中に閉じこもる人も多いと言います。それほどまでしても計画通り休暇をとるということは、計画通り暮らせている、ということを示す社会的なバロメーターにも なっているのです。
計画的な家事
計画性と規則性が重視されるもう一つの大きな分野が、家事です。洗濯をする間隔、掃除機をかける頻度、窓を拭くタイミング、買い物に出る日程、しっかりタイムプランを決めている人が多く見られます。
これも、歴史的に考えれば当然のこと。以前テレビで、ベルリン出身の一家がテレビ局のサポートを受けながら、6週間ほど19世紀前半の「黒い森」地方の農家の暮らしを実践してみる、という番組が話題を呼んでいました。それを見てつくづく思ったことは、冷蔵庫のない時代に、牧畜と酪農、肉食をベースに海の遠い内陸地方で冬を生き延びるためには、暮らしの「計画性」はサバイバルの大前提だった、ということです。
9月の初めに収穫が終わり、11月に豚を1匹屠殺したら、5月ごろに最初のジャガイモを収穫するまでは、牛乳やチーズを除いて、食べ物も家畜のえさも半年間はストックしかありません。保存食の確保も献立も、エネルギーの使い方も、計画的に行わなければ餓死するしかない。そんな生活では、むやみに他人の都合に合わせて便宜をはかり、計画を変更していては命にかかわります。人間関係を犠牲にしてでも計画を守れる人の方が偉いかもしれない、というような心理が生まれても当然の成り行 きだったと思うのです。
そんな何百年にもわたる歴史的体験を乗り越えて、近代的なサービス精神を理解してもらおうと思ったときに、口で説明しただけではなかなか難しいのも少しも不思議ではありません。
家の中を他人に見せる
計画的なメンテナンスと掃除が行き届いている家は、当然対外的に見せるためのものです。特別に豊かでなくても、自分の生活の中身をくまなく人に見せますが、これは趣味の良さや金儲けの能力など、個人的な才気を誇示しているというよりも、自分はしっかりと計画的に生活を営む能力があるのだ、そして、それがこの程度の財につながっているのだ、という「情報開示」のような役割があるように思います。前近代の時代にギルドの世界で出世させてもらおうと思ったら、当然そのような能力の情報開示を求められたわけですから。
少なくともある程度気心の知れた相手には、家に上げた後で全室見せることが礼儀、ということになっています。社会的に信頼できる人物であるかどうかは、家の中でもデモンストレーションされるもの、というわけです。
こうして見ると、“家庭生活を大切にするドイツ人”は、必ずしもエゴイスティックに私生活のみを大切にしているわけではないと言えるでしょう。きちんとした社会生活を営もうとしているまじめな人物であるからこそ、社外での生活を大切にしている、という面もありうるのです。
人事評価などでも、こういった公私の境界線の引き方が違うことを考慮しておかないと、社員の社会性や能力を見誤る危険性があります。外資系企業の要請とドイツ人社員の常識が衝突するような場面では、一歩引いてそういった境界線の所在を確認し、その人がどこまで社会的に「公」の生活をきっちりやろうとしているのかを確認してみることも大切でしょう。
|
|||||



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック
 ドイツ人と一緒に仕事をしている人なら、経験済みの方も多いと思います。うっかり終業間際に職場のドイツ人に何か頼みごとをしたら、あっさり断られ、帰られてしまった。あるいは、雰囲気がいきなり険悪になり、冷や汗をかいたこと。
ドイツ人と一緒に仕事をしている人なら、経験済みの方も多いと思います。うっかり終業間際に職場のドイツ人に何か頼みごとをしたら、あっさり断られ、帰られてしまった。あるいは、雰囲気がいきなり険悪になり、冷や汗をかいたこと。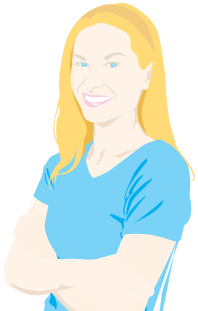 家をいつもきれいにしている人の多いドイツ。小さな子どもがいて、しかも主婦がパートで午前中働いているような家庭でも、リビングルームに限らず、すべ ての部屋がきれいに、まるで家具店のショールームのように片付いていたりします。
家をいつもきれいにしている人の多いドイツ。小さな子どもがいて、しかも主婦がパートで午前中働いているような家庭でも、リビングルームに限らず、すべ ての部屋がきれいに、まるで家具店のショールームのように片付いていたりします。 経験のある方は多いと思います。明らかにミスをしたドイツ人が全然謝ってくれないので、気分を害したこと。あるいは、ドイツ人にミスを指摘して注意を促しても、一向に謝らないどころか、少しも改めようという姿勢が見えずに困惑したこと。
経験のある方は多いと思います。明らかにミスをしたドイツ人が全然謝ってくれないので、気分を害したこと。あるいは、ドイツ人にミスを指摘して注意を促しても、一向に謝らないどころか、少しも改めようという姿勢が見えずに困惑したこと。