Nr. 5 他人の子を叱る
 ドイツの現地校に子どもを通わせている人がよく直面する悩みのひとつに、「他人の子どもの叱り方」というものがあります。日本にいて、日本人同士であっても難しいこの問題、せっかく子どもに現地の友人ができた、と喜んだのも束の間、その友人の行動に大きな問題を感じた時、親としてはどう対応すべきか迷うものです。そこで今回は、ドイツで子どもを叱る場合のコツを説明しましょう。
ドイツの現地校に子どもを通わせている人がよく直面する悩みのひとつに、「他人の子どもの叱り方」というものがあります。日本にいて、日本人同士であっても難しいこの問題、せっかく子どもに現地の友人ができた、と喜んだのも束の間、その友人の行動に大きな問題を感じた時、親としてはどう対応すべきか迷うものです。そこで今回は、ドイツで子どもを叱る場合のコツを説明しましょう。
日本的な感覚からすると、まず戸惑うのは、「これはいけないことだからやめなさい」という叱り方が通用するような、社会全体に適用される行動基準がほとんど存在しないという事実ではないでしょうか。比較的規律正しく、ルールを重視する人が多いとはいえ、ドイツ社会の行動規範というものは、日本に比べて均一性がなく、地方によって、また家庭によっても千差万別です。従って、厳しく家で礼儀を叩き込まれている子どももいれば、全く子どもに構わない家もあり、また可愛いがるだけでほとんど叱らず、しつけなど全く考えていない家、しつけの重点が「整理、整頓、清潔」であって「人に対する礼儀正しさ」にはない家など、とにかくいろいろなパターンに出合うものです。
多種多様な基準を身につけているクラスメートと付き合いながら成長する子どもたちは、当然、家庭によって異なるルールが存在する、ということを心得てい ますから、よその家に出かけても、ひとまずは自分のやりたいことをやって、叱られるかどうか試してみるという姿勢を身につけている場合も多いと思います。信頼できるしっかりした家の子どもでも、よその家ではとんでもないことをしでかして、ケロリとしていたりということもあります。
さて、ドイツ人の基本的な考え方ですが、家の中のルールは社会常識によって決まるのではなく、家の主(Hausherr)の判断によって決まるもの、ということになっています。日本と最も勝手が違うのは、遊びに来た子どもが羽目を外してとんでもないことをし始めても「これは一般的にいけないといわれていることだから、やめよう」と、大人が子どもにあいまいな一般常識を盾に注意しても通用しない点でしょう。
そんな場面で有効なのは、その場のルールを決定する権利のある責任者としての大人の断固とした態度です。例えば、リビングルームでボールを蹴ったり、ソファやタンスによじ上って飛び降りたりするような遊びが始まったら、「ここでは許されていない行為だからやめなさい」(Aufhören, das ist hier nicht erlaubt)と注意することになります。「なんで?」と聞き返されたら、「私がやって欲しくないから(Weil ich das nicht will.)」「ここのルールを決めるのは私だから(Ich bin der Bestimmer hier)」と権限の所在をはっきりとさせます。そして、毅然として、決めたルールを徹底的に守らせるのです。
子ども同士の付き合いに支障をきたすかもしれないと思ったり、注意した子どもの親との関係が険悪になるかも、と案じて大人が子どもに遠慮することはありません。「家の中のルール」は「漠然としたドイツ流」といったような社会常識によって決まるものではないので、周りの家とルールが違っても全くかまわないからです。他人の家では、あくまでも「その家の人の常識」 が基準になる、ということが子どもも親も納得する当たり前の社会常識なのです。
ですから、ルールを説明しても、よその子どもがいうことを聞いてくれなかったら「あなたのお家で許されていることなら、あなたのお家でやってちょうだい(Mach das bitte bei dir zuhause, wenn deine Mutter es dir erlaubt)」と釘を刺すお母さんも珍しくありません。
では、自分の家や敷地外の公共の場で、子どもに注意する場合はどうすればよいでしょうか?これは地方差があるもので、一般的には、南ドイツでは赤の他人同士でも子どもには「こら、そこに紙くずを散らすな」「年寄りに席を譲れ」などと注意しますが、北ドイツでは我関せずと無視する人が多いような印象を受けま す。ですが、直接的に自分、あるいは自分の子どもの身に降りかかってくるような行為であれば、即座にその場で抗議し、やめさせるべきでしょう。
その場合も、「これは一般的によくないとされる行為」であると指摘してみても効果が薄いという点に気を付けましょう。法律や契約に違反するものでない限りは「私が迷惑だから(Es stört mich)やめて欲しい」という姿勢で交渉すること。それでは押しが弱いかもしれませんが、あいまいな社会行動規範を反映して、その分子どもが騒いではならない時間帯、芝刈り機を使用してはならない時間帯、他人に対して口にしてはいけない言葉、他人の庭に飼い猫が入り込んでも許容される範囲など、ありとあらゆることまで細かく法律で決められている社会ですから、誰かに何かをやめさせたい場合には、それが法律で規制されている行為であるか否か、事前に調べてみる価値はあるかも知れません。大人であろうが子どもであろうが、やめてくれるようお願いしてみても相手からの歩み寄りが見られない場合の最終手段として、「これは法律でも許されていない行為ですよ。(Das ist verboten)」と言うこともできるからです。
|
|||||



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック (Bitte) Aufhören, das ist hier nicht erlaubt.
(Bitte) Aufhören, das ist hier nicht erlaubt. 異文化コミュニケーションについて書かれた本を読むと、西洋人には好意を受けたお礼として贈り物をしても喜ばれないからしないほうがよい、というアドバイスを目にすることがあります。お中元やお歳暮を始め、感謝の気持ちを物に託すことに慣れている日本人にとって違和感があるのは否めません。「口頭でのお礼だけではそれこそ失礼にあたるのではないか」「他にどんなお礼の方法があるの」など気を揉むことになれば、近所付き合いはますます億劫なものになってしまいます。そこで、今回はドイツで一般的なお礼の仕方を取り上げることにしましょう。
異文化コミュニケーションについて書かれた本を読むと、西洋人には好意を受けたお礼として贈り物をしても喜ばれないからしないほうがよい、というアドバイスを目にすることがあります。お中元やお歳暮を始め、感謝の気持ちを物に託すことに慣れている日本人にとって違和感があるのは否めません。「口頭でのお礼だけではそれこそ失礼にあたるのではないか」「他にどんなお礼の方法があるの」など気を揉むことになれば、近所付き合いはますます億劫なものになってしまいます。そこで、今回はドイツで一般的なお礼の仕方を取り上げることにしましょう。 ドイツ人は、自分でも「ドイツはサービス地獄」といって嘆くことがありますが、日本的な感覚では絶対に信じられない光景に遭遇するのが、例えば百貨店などのクレームに対する顧客窓口でしょう。最近ではドイツ企業も必死に窓口担当者に「サービス精神」を叩き込もうと、社員セミナーに巨額のコストを注ぎ込んでいるようですが、長年培われてきた「ドイツ人の常識感覚」は、そう簡単には変わらないようで、小売店などでいやな思いをすることはよくあるものです。
ドイツ人は、自分でも「ドイツはサービス地獄」といって嘆くことがありますが、日本的な感覚では絶対に信じられない光景に遭遇するのが、例えば百貨店などのクレームに対する顧客窓口でしょう。最近ではドイツ企業も必死に窓口担当者に「サービス精神」を叩き込もうと、社員セミナーに巨額のコストを注ぎ込んでいるようですが、長年培われてきた「ドイツ人の常識感覚」は、そう簡単には変わらないようで、小売店などでいやな思いをすることはよくあるものです。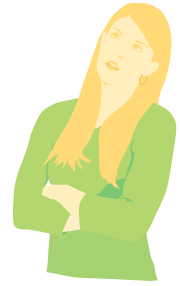 西洋人はデジタル思考をする、といわれることがありますが、確かにドイツ人と付き合っていると、日本的な感覚では簡単にイエスかノーか決められないと思うことでも、白黒はっきりした決断を迫られることがよくあります。「お茶かコーヒーか」といったレベルなら悩みませんが、一番戸惑うのは「はっきり言ってしまったら誰かが傷つくのでは」と心配されるような場合。ずいぶん昔の話ですが、ドイツ人の夫と婚約して間もない頃の失敗談をお話しましょう。
西洋人はデジタル思考をする、といわれることがありますが、確かにドイツ人と付き合っていると、日本的な感覚では簡単にイエスかノーか決められないと思うことでも、白黒はっきりした決断を迫られることがよくあります。「お茶かコーヒーか」といったレベルなら悩みませんが、一番戸惑うのは「はっきり言ってしまったら誰かが傷つくのでは」と心配されるような場合。ずいぶん昔の話ですが、ドイツ人の夫と婚約して間もない頃の失敗談をお話しましょう。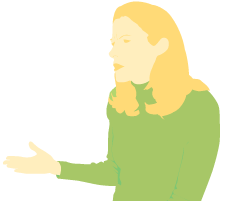 困っているドイツ人に親切のつもりで融通を利かせてあげたのに、逆に文句をいわれてしまったとき、あなたならどうしますか?感情でも、意見でも、フィルターなしのストレートな表現を「正直」「誠意」とする風潮があるドイツですが、ものすごい剣幕で文句をいわれたら、日本人ならやっぱり傷つきますよね。特に感情面から責め込まれると、理不尽な駄々だろうがなんだろうが、とにかく動揺してしまうもの。ドイツ人同士はお互い、どうやって折り合いをつけているので しょう?あるとき、バスに乗っていて目撃したドイツ人同士のやりとりをご紹介しましょう。
困っているドイツ人に親切のつもりで融通を利かせてあげたのに、逆に文句をいわれてしまったとき、あなたならどうしますか?感情でも、意見でも、フィルターなしのストレートな表現を「正直」「誠意」とする風潮があるドイツですが、ものすごい剣幕で文句をいわれたら、日本人ならやっぱり傷つきますよね。特に感情面から責め込まれると、理不尽な駄々だろうがなんだろうが、とにかく動揺してしまうもの。ドイツ人同士はお互い、どうやって折り合いをつけているので しょう?あるとき、バスに乗っていて目撃したドイツ人同士のやりとりをご紹介しましょう。





