ドイツでは業者限定の国際見本市から一般消費者向けのサロンまで、ワインフェアが多数開催されています。今回はお勧めを選んでみました。
〈 業者向けフェア 〉
「ProWein」デュッセルドルフ毎年開催
(次回は2015年3月15~17日)
メッセ・デュッセルドルフ社が開催するワイン&スピリッツ専門見本市。1994年にスタート。20年を迎え、出展者数ではボルドーの「Vinexpo」、ヴェローナの「Vinitaly」を上回る世界最大規模の見本市に成長。2014年の出展者数は4830社。うち845社がドイツ本国、3985社(82%)が外国の出展者。イタリア、フランスの出展者が圧倒的に多い。訪問者数は約4万9000人で、うち45%が国外から。出展者、訪問者ともに年々着実に増加している。2013年からは中国・上海でも「ProWein China」を開催、英国のワイン教育機関WSETを招へいし、セミナーに力を入れている。
www.prowein.de
「Intervitis Interfructa」シュトゥットガルト
3年に1回開催(次回は2016年4月27~30日予定)
ドイツ・ワイン生産者協会が中心となって組織し、シュトゥットガルト・メッセで開催する技術見本市。ワイン、フルーツ、ジュース、スピリッツの生産に関するあらゆる技術が対象。農業機械からタンク、樽、ボトリングライン、パッケージに至るまでの最新技術をキャッチできる。2013年は24カ国から567社が出展。
www.messe-stuttgart.de/de/intervitis-interfructa
〈 一般向けのフェア 〉
「Forum Vini」ミュンヘン
毎年開催(次回は2014年11月14~16日)
今年で30回目を迎えるワイン&スピリッツ・フェア。主催者の交代があり、今年からはワイン関連の出版社マイニンガー社が主催。2013年は国内外から270社が出展、9000人が訪れた。ドイツ、イタリア、オーストリアから合計150醸造所が出展。食材業者も出展している。
www.forum-vini.de
「Wein Düsseldorf」デュッセルドルフ
毎年開催(次回は2014年11月8~9日、場所:インターコンチネンタルホテル)
ヴェーバー・メッセ社が主催ドイツを中心に約100の醸造所が出展。 ハンブルク、ハノーファー、ケルン、ミュンヘン、 シュトゥットガルトなどでも開催されている。
www.weinduesseldorf.de
「eat & style」毎年開催
(次回はベルリン2014年11月14~16日、シュトゥットガルト11月21~23日)
フレート・イベント社が主催する、今年で9年目となるフード・フェア。出展者400社、今年はすでにハンブルク、ケルン、ミュンヘンで開催。 合計訪問者数は11万人。メインスポンサーでもあるドイツ・ワインインスティトゥートの「wine & style」のブースでは13生産地域のワインが試飲でき、ワイン関連のセミナーも充実している。
www.eat-and-style.de
このほか、ワイン商が主催するフェアがあります。秋冬はワイン関連の催し物が多いので、お近くの店舗で尋ねてみてください。
リザ・ブン醸造所
 ラインヘッセン、ニアシュタインの家族経営の醸造所。現在、ワイン造りに取り組んでいるリザは4代目。少女時代は、天候に左右されながら週末も仕事をする両親の姿を常に見ていたため、醸造所の仕事には魅力を感じなかったと言う。醸造家の仕事の面白さを再発見したのは、税理士事務所、幼稚園、ホテル、旅行代理店などで実習体験を積んだ後のこと。アビトゥア(大学入学資格)取得後はラインヘッセン地方の醸造所などで実習を積み、大学では国際ワイン経済学を専攻。学生時代にオーストラリアと南アフリカの醸造所で研修した。「ワイン造りは1年サイクルでしか学べない。困難なヴィンテージに何度も遭遇している父母や祖父母から学ぶことはとても多い」と言う。所有畑は10ヘクタール。ニアシュタインのヒッピング、エールベルク、オルベルでは主にリースリングを育て、その他の畑ではブルグンダー種に力を入れている。リザのリースリングに対する評価は高く、目下、注目の若手醸造家の1人でもある。
ラインヘッセン、ニアシュタインの家族経営の醸造所。現在、ワイン造りに取り組んでいるリザは4代目。少女時代は、天候に左右されながら週末も仕事をする両親の姿を常に見ていたため、醸造所の仕事には魅力を感じなかったと言う。醸造家の仕事の面白さを再発見したのは、税理士事務所、幼稚園、ホテル、旅行代理店などで実習体験を積んだ後のこと。アビトゥア(大学入学資格)取得後はラインヘッセン地方の醸造所などで実習を積み、大学では国際ワイン経済学を専攻。学生時代にオーストラリアと南アフリカの醸造所で研修した。「ワイン造りは1年サイクルでしか学べない。困難なヴィンテージに何度も遭遇している父母や祖父母から学ぶことはとても多い」と言う。所有畑は10ヘクタール。ニアシュタインのヒッピング、エールベルク、オルベルでは主にリースリングを育て、その他の畑ではブルグンダー種に力を入れている。リザのリースリングに対する評価は高く、目下、注目の若手醸造家の1人でもある。
Weingut Lisa Bunn
Mainzerstr. 86, 55283 Nierstein
Tel. 06133-59290
www.weingut-bunn.de
2013 Chardonnay vom
Kalkstein trocken 7.50€
2013年 シャルドネ・フォン・カルクシュタイン 辛口
 リザは醸造所の運営に関わるようになってから、ジーガーレーベ、ファーバーレーベ、フクセルレーベ、ケルナーをリースリングとブルグンダー種に植え替え始めた。また、生産しているワインのコレクションを、フルーティーで生き生きとしたグーツワイン、テロワールを前面に感じさせる遅摘みのオルツワイン(いわゆる村名ワイン)、自然醗酵後、長期にわたって酵母と接触させ、最後にボトリングするラーゲンワイン(単一畑のぶどうから造るワイン)の3段階に整理し、商品構成を明確にしたという。ご紹介するシャルドネはディーンハイムの単一畑、石灰岩土壌のターフェルシュタインのものだが、エチケットには畑名を表示していない。2013年は開花期の天候が思わしくなく、花震いのため結実が悪かった。そのため、80%は種がなく、ごく小粒にとどまったが、その後は順調に成熟し、甘く凝縮したぶどうが収穫できたと言う。ぶどうのアロマの多くは果皮に含まれているが、小粒だったため果皮の割合が果汁に対して高く、味わい豊かなワインになったそうだ。醸造時には彼女自身が足で踏んでぶどうを破砕し、一夜にわたってスキンコンタクト。10%をバリックで自然醗酵、残りはステンレスタンクで醗酵させたもの。滑らかで肌理の細かな舌触り、ほのかなナッツと洋梨の風味、ソルティーな後味、そしてあくまで軽快。タパスを肴にグラスを傾けるときにぴったりのワイン。
リザは醸造所の運営に関わるようになってから、ジーガーレーベ、ファーバーレーベ、フクセルレーベ、ケルナーをリースリングとブルグンダー種に植え替え始めた。また、生産しているワインのコレクションを、フルーティーで生き生きとしたグーツワイン、テロワールを前面に感じさせる遅摘みのオルツワイン(いわゆる村名ワイン)、自然醗酵後、長期にわたって酵母と接触させ、最後にボトリングするラーゲンワイン(単一畑のぶどうから造るワイン)の3段階に整理し、商品構成を明確にしたという。ご紹介するシャルドネはディーンハイムの単一畑、石灰岩土壌のターフェルシュタインのものだが、エチケットには畑名を表示していない。2013年は開花期の天候が思わしくなく、花震いのため結実が悪かった。そのため、80%は種がなく、ごく小粒にとどまったが、その後は順調に成熟し、甘く凝縮したぶどうが収穫できたと言う。ぶどうのアロマの多くは果皮に含まれているが、小粒だったため果皮の割合が果汁に対して高く、味わい豊かなワインになったそうだ。醸造時には彼女自身が足で踏んでぶどうを破砕し、一夜にわたってスキンコンタクト。10%をバリックで自然醗酵、残りはステンレスタンクで醗酵させたもの。滑らかで肌理の細かな舌触り、ほのかなナッツと洋梨の風味、ソルティーな後味、そしてあくまで軽快。タパスを肴にグラスを傾けるときにぴったりのワイン。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック
 モーゼル中部ピースポートの家族経営の醸造所。もともと料理人志望だったユリアン・ハート(28)が24歳の時に立ち上げた。ユリアンの父母は共に学校教師。10歳の頃から台所で母を手伝うようになった彼は、15歳の誕生日に両親が提案したミニバイクを断って、ミシュラン・ガイドが高く評価しているレストラン『ソノラ』(ドライス)でのディナーをプレゼントしてもらう。その後、ミシュランの3つ星シェフ、クラウス・エアフォルトらの下で料理修業をし、一流シェフになることを目指した。しかし、著名なリースリングの産地ピースポート生まれのユリアンは、料理を極めるほどにワインへの興味が湧いてくるのを抑えられず、ベルンカステル=クースの醸造学校で勉強しながら、エゴン・ミュラー醸造所、ケラー醸造所などで修業、2010年ヴィンテージで醸造家としてデビューする。現在の所有畑は4.5ヘクタール。ラインホルト・ハート醸造所、ヨハン・ハート醸造所とも親戚関係にあり、2013年からは叔父が経営していたヨハン・ハート醸造所を継ぎ、ヴィントリッヒの畑のほかにピースポートの著名畑を入手。同年に結婚し、畑もセラーもマーケティングも、すべて妻のナディーヌと二人三脚で取り組んでいる。
モーゼル中部ピースポートの家族経営の醸造所。もともと料理人志望だったユリアン・ハート(28)が24歳の時に立ち上げた。ユリアンの父母は共に学校教師。10歳の頃から台所で母を手伝うようになった彼は、15歳の誕生日に両親が提案したミニバイクを断って、ミシュラン・ガイドが高く評価しているレストラン『ソノラ』(ドライス)でのディナーをプレゼントしてもらう。その後、ミシュランの3つ星シェフ、クラウス・エアフォルトらの下で料理修業をし、一流シェフになることを目指した。しかし、著名なリースリングの産地ピースポート生まれのユリアンは、料理を極めるほどにワインへの興味が湧いてくるのを抑えられず、ベルンカステル=クースの醸造学校で勉強しながら、エゴン・ミュラー醸造所、ケラー醸造所などで修業、2010年ヴィンテージで醸造家としてデビューする。現在の所有畑は4.5ヘクタール。ラインホルト・ハート醸造所、ヨハン・ハート醸造所とも親戚関係にあり、2013年からは叔父が経営していたヨハン・ハート醸造所を継ぎ、ヴィントリッヒの畑のほかにピースポートの著名畑を入手。同年に結婚し、畑もセラーもマーケティングも、すべて妻のナディーヌと二人三脚で取り組んでいる。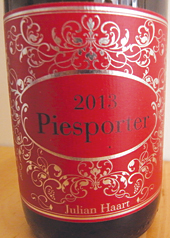 叔父の畑を継いだことで、ユリアンはヴィントリッヒの畑のほかに、ピースポートのゴルトトロップフヒェン、シューベルツライ、ドームヘアの3つの畑を手に入れることになった。栽培されているリースリングの樹齢は平均45年。シューベルツライでは1905年に植えられたリースリングも実を付けている。急斜面の畑での手仕事は家族の協力に支えられている。畑仕事も収穫も、ユリアンの父母やナディーヌの父母ら、一家総出で行っている。畑面積は現状を維持し、すべてを家族で行う醸造所でありたいと語る。このピースポートのリースリングはゴルトトロップフヒェンとシューベルツライのぶどうを使用したもの。ステンレススティールタンクでの醸造。清らかでエレガント、しかも非常に精密な印象のワイン。残糖は15g/ℓで中辛口に相当。ユリアンは「モーゼル・トロッケン(モーゼルの辛口)」と表現する。2013年ヴィンテージは雨がちで、選別に手間が掛かったという。全般的にアルコール度数は低めだが、エキス量は前年、前々年を高く上回っているそうだ。ユリアンのリースリングは初ヴィンテージから評価が高く、2011年産は2種類のワインがパーカー・ポイント94点を取得している。
叔父の畑を継いだことで、ユリアンはヴィントリッヒの畑のほかに、ピースポートのゴルトトロップフヒェン、シューベルツライ、ドームヘアの3つの畑を手に入れることになった。栽培されているリースリングの樹齢は平均45年。シューベルツライでは1905年に植えられたリースリングも実を付けている。急斜面の畑での手仕事は家族の協力に支えられている。畑仕事も収穫も、ユリアンの父母やナディーヌの父母ら、一家総出で行っている。畑面積は現状を維持し、すべてを家族で行う醸造所でありたいと語る。このピースポートのリースリングはゴルトトロップフヒェンとシューベルツライのぶどうを使用したもの。ステンレススティールタンクでの醸造。清らかでエレガント、しかも非常に精密な印象のワイン。残糖は15g/ℓで中辛口に相当。ユリアンは「モーゼル・トロッケン(モーゼルの辛口)」と表現する。2013年ヴィンテージは雨がちで、選別に手間が掛かったという。全般的にアルコール度数は低めだが、エキス量は前年、前々年を高く上回っているそうだ。ユリアンのリースリングは初ヴィンテージから評価が高く、2011年産は2種類のワインがパーカー・ポイント94点を取得している。 ラインガウ地方エストリッヒ・ヴィンケルにある、800年の伝統を誇る醸造所。1211年にすでにワインを醸造販売していたとの記録がある。城主だったマトゥシュカ=グライフェンクラウ伯爵の死後、1997年からはナッサウ・シュパルカッセがオーナーに。1999年より醸造所ディレクターおよび醸造責任者を務めるロヴァルト・ヘップ(Rowald Hepp)氏は、亡き伯爵とも親交があり、醸造所経営の立て直しに尽力。2001年にゴーミヨ・ドイツワインガイドの最優秀醸造所ディレクターに選ばれた。「シュロス・フォルラーズを国内的にも国際的にも一目置かれる醸造所にしたいというビジョンを持って仕事に取り組んできた」と語る。彼はリースリング以外のぶどう畑をすべてリースリングに植え替え、収量を落として品質向上に努めた。現在の畑面積は80ヘクタール。土壌の個性を生かした高品質でオーセンティックなワイン造りで定評がある。ヘップ氏はジャパン・ワイン・チャレンジの審査員として、ほぼ毎年渡日している。VDP会員。
ラインガウ地方エストリッヒ・ヴィンケルにある、800年の伝統を誇る醸造所。1211年にすでにワインを醸造販売していたとの記録がある。城主だったマトゥシュカ=グライフェンクラウ伯爵の死後、1997年からはナッサウ・シュパルカッセがオーナーに。1999年より醸造所ディレクターおよび醸造責任者を務めるロヴァルト・ヘップ(Rowald Hepp)氏は、亡き伯爵とも親交があり、醸造所経営の立て直しに尽力。2001年にゴーミヨ・ドイツワインガイドの最優秀醸造所ディレクターに選ばれた。「シュロス・フォルラーズを国内的にも国際的にも一目置かれる醸造所にしたいというビジョンを持って仕事に取り組んできた」と語る。彼はリースリング以外のぶどう畑をすべてリースリングに植え替え、収量を落として品質向上に努めた。現在の畑面積は80ヘクタール。土壌の個性を生かした高品質でオーセンティックなワイン造りで定評がある。ヘップ氏はジャパン・ワイン・チャレンジの審査員として、ほぼ毎年渡日している。VDP会員。 シュロス・フォルラーズは、1716年にドイツで初めてカビネット(貴重なワインを保管する小部屋の意)という言葉をワインに使用したという。ワインの品質等級を表す最古の概念だ。ヘップ氏お勧めのこの「カビネット、ファインヘルプ」はタウヌス珪岩などのシュロス・フォルラーズの畑のぶどうから造られたもの。2013年産は柑橘系の風味と火打石のニュアンスがあり、後味に蜂蜜や甘いメロンの風味が感じられる。「エディション」は、毎年スタッフ全員でその年のコレクションをブラインドテイスティングし、辛口系で典型的なリースリングの個性を持ち、ヴィンテージの特徴がよく出ている、食中酒にふさわしいワインを選び、命名しているもの。2013年産は柑橘類とかりんの美しい風味。シュペートレーゼクラスのぶどうでスキンコンタクトを8時間行い、ふくよかさを出している。「醸造所が軌道に乗ったのは素晴らしいチームワークのおかげ。エディションは毎年スタッフに捧げるワインでもあるんだ」とヘップ氏。醸造所の人気商品となっている。
シュロス・フォルラーズは、1716年にドイツで初めてカビネット(貴重なワインを保管する小部屋の意)という言葉をワインに使用したという。ワインの品質等級を表す最古の概念だ。ヘップ氏お勧めのこの「カビネット、ファインヘルプ」はタウヌス珪岩などのシュロス・フォルラーズの畑のぶどうから造られたもの。2013年産は柑橘系の風味と火打石のニュアンスがあり、後味に蜂蜜や甘いメロンの風味が感じられる。「エディション」は、毎年スタッフ全員でその年のコレクションをブラインドテイスティングし、辛口系で典型的なリースリングの個性を持ち、ヴィンテージの特徴がよく出ている、食中酒にふさわしいワインを選び、命名しているもの。2013年産は柑橘類とかりんの美しい風味。シュペートレーゼクラスのぶどうでスキンコンタクトを8時間行い、ふくよかさを出している。「醸造所が軌道に乗ったのは素晴らしいチームワークのおかげ。エディションは毎年スタッフに捧げるワインでもあるんだ」とヘップ氏。醸造所の人気商品となっている。 エファ・フリッケはブレーメン出身。ガイゼンハイム大学でぶどう栽培・ワイン醸造を学び、イタリア、スペイン、オーストラリアなどで修業、ラインガウ地方のJ.B.ベッカー醸造所勤務を経てヨーゼフ・ライツ醸造所で醸造責任者として活躍した。ライツ醸造所に勤務していた2004年に独立を決意。06年に同醸造所での仕事と並行してキードリッヒに個人醸造所を立ち上げ、初ヴィンテージをリリース。所有畑0.24ヘクタール、生産量600リットルからのスタートだった。11年8月にライツ醸造所を退職し、9月からは完全に独立。現在の所有畑は6ヘクタール。栽培品種はリースリングと少量のジルヴァーナー。畑のほとんどがロルヒの急斜面にある。リューデスハイムの北側に位置するロルヒは近年注目を浴び始めている地区。中には樹齢60年のリースリングもあり、風化粘板岩や珪岩土壌の特性を生かしたワインが造られている。ロルヒのクローネとシュロスベルクは単独で醸造されるトップワイン。ロルヒハウゼンのゼーリッヒマッハーはセカンドワインという位置付けだ。このほか、ロルヒとキードリッヒそれぞれの村名ワインも生産している。約70%を輸出、残りはレストランと専門店に卸し、ワイン造りに専念している。
エファ・フリッケはブレーメン出身。ガイゼンハイム大学でぶどう栽培・ワイン醸造を学び、イタリア、スペイン、オーストラリアなどで修業、ラインガウ地方のJ.B.ベッカー醸造所勤務を経てヨーゼフ・ライツ醸造所で醸造責任者として活躍した。ライツ醸造所に勤務していた2004年に独立を決意。06年に同醸造所での仕事と並行してキードリッヒに個人醸造所を立ち上げ、初ヴィンテージをリリース。所有畑0.24ヘクタール、生産量600リットルからのスタートだった。11年8月にライツ醸造所を退職し、9月からは完全に独立。現在の所有畑は6ヘクタール。栽培品種はリースリングと少量のジルヴァーナー。畑のほとんどがロルヒの急斜面にある。リューデスハイムの北側に位置するロルヒは近年注目を浴び始めている地区。中には樹齢60年のリースリングもあり、風化粘板岩や珪岩土壌の特性を生かしたワインが造られている。ロルヒのクローネとシュロスベルクは単独で醸造されるトップワイン。ロルヒハウゼンのゼーリッヒマッハーはセカンドワインという位置付けだ。このほか、ロルヒとキードリッヒそれぞれの村名ワインも生産している。約70%を輸出、残りはレストランと専門店に卸し、ワイン造りに専念している。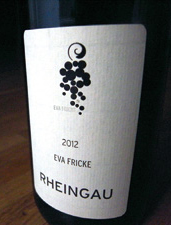 ロルヒ、リューデスハイム、そしてキードリッヒで栽培されたリースリングのブレンド。エファが生産するワインの中で、最もベーシックな「グーツワイン」(エステートワイン)。日々の食卓で楽しめる軽快なワインだ。2009年から生産しているもので、農家から購入したぶどうや果汁から造っている。購入先の農家がビオに移行しつつあり、13年産では30%がビオのぶどうだという。エステートワインは醸造所のメッセージが聞こえるワイン。エファのこのワインは、ラインガウ特有の砂状のレス土、粘土、陶土、スレート、珪岩などで育ったぶどうのハーモニーが楽しめる。熟れたリンゴやモモなどの果実のアロマに溢れ、爽快な酸味とのバランスも良い、すっきりとした辛口。優しい味わいの中に秘めた力強さを感じる。目下、エファは着々とビオディナミ実践の準備を進めている。醸造所設立当初から、除草剤、殺虫剤は一切投入せず、ラインガウ・ワイン醸造家連盟のエコロジーワイン規定に従って醸造している。
ロルヒ、リューデスハイム、そしてキードリッヒで栽培されたリースリングのブレンド。エファが生産するワインの中で、最もベーシックな「グーツワイン」(エステートワイン)。日々の食卓で楽しめる軽快なワインだ。2009年から生産しているもので、農家から購入したぶどうや果汁から造っている。購入先の農家がビオに移行しつつあり、13年産では30%がビオのぶどうだという。エステートワインは醸造所のメッセージが聞こえるワイン。エファのこのワインは、ラインガウ特有の砂状のレス土、粘土、陶土、スレート、珪岩などで育ったぶどうのハーモニーが楽しめる。熟れたリンゴやモモなどの果実のアロマに溢れ、爽快な酸味とのバランスも良い、すっきりとした辛口。優しい味わいの中に秘めた力強さを感じる。目下、エファは着々とビオディナミ実践の準備を進めている。醸造所設立当初から、除草剤、殺虫剤は一切投入せず、ラインガウ・ワイン醸造家連盟のエコロジーワイン規定に従って醸造している。
 カベルネ・ブランは1991年にスイス人のヴァレンティン・ブラットナーが、カベルネ・ソーヴィニヨンと耐性品種(Resistenzpartner)を交配して生み出したもの。その後、プファルツ地方の苗木業者(Rebveredler)フォルカー・フライタークが選別し、2004年に新品種として登録した。カベルネ・ブランは粒が小さく、凝縮度も高い。ボトリティスに対して強い耐性があるほか、ウドンコ病、ベト病にも耐性が見られ、リースリング並みに寒さに強い。ワインはソーヴィニヨン・ブランを思わせるエレガントで爽やかな風味と、リースリングを連想させる酸味が特徴。後味に残るほろ苦さも魅力的。従来のPiWi種と違ってネーミングが良いことも、注目される理由の1つ。ルンメル夫妻はカベルネ・ブランのゼクト(13.20€)も生産している。エチケットデザインは、ズザンネ夫人によるもの。1er(Einser=1番目の)は、本来の品種名VB91-26-1をそのように呼んでいたことから付けられている。
カベルネ・ブランは1991年にスイス人のヴァレンティン・ブラットナーが、カベルネ・ソーヴィニヨンと耐性品種(Resistenzpartner)を交配して生み出したもの。その後、プファルツ地方の苗木業者(Rebveredler)フォルカー・フライタークが選別し、2004年に新品種として登録した。カベルネ・ブランは粒が小さく、凝縮度も高い。ボトリティスに対して強い耐性があるほか、ウドンコ病、ベト病にも耐性が見られ、リースリング並みに寒さに強い。ワインはソーヴィニヨン・ブランを思わせるエレガントで爽やかな風味と、リースリングを連想させる酸味が特徴。後味に残るほろ苦さも魅力的。従来のPiWi種と違ってネーミングが良いことも、注目される理由の1つ。ルンメル夫妻はカベルネ・ブランのゼクト(13.20€)も生産している。エチケットデザインは、ズザンネ夫人によるもの。1er(Einser=1番目の)は、本来の品種名VB91-26-1をそのように呼んでいたことから付けられている。





