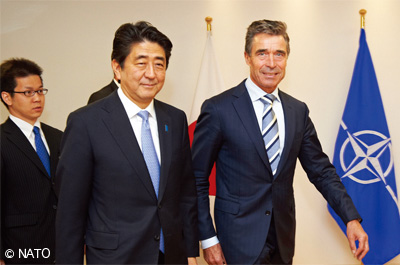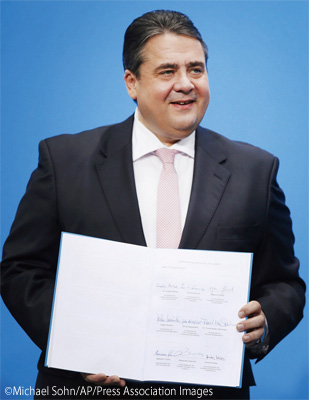5月22日から25日に掛けて、欧州連合(EU)加盟国で行われた欧州議会選挙の開票結果は、欧州委員会や各国の既成政党に強い衝撃を与えた。フランスや英国などで、EUに批判的な政党が大躍進したからだ。
FNの圧勝
EU全体を特に揺るがしたのは、フランスの極右政党フロン・ナショナール(FN)が、社会党などほかの政党をしのぐ最高得票率を記録して勝利したことだ。
前回の欧州議会選挙でのFNの得票率は6.3%だったが、今回は得票率を約4倍に増やして25%を記録。保守政党・国民運動連合(UMP)は20.8%、オランド大統領が率いる社会党はわずか14%にとどまった。
フランスの欧州議会選挙でFNがトップの座に立ったのは初めてのこと。満面に笑みをたたえた党首マリーヌ・ル・ペン女史は、勝利確定後の演説で、「FNの勝利はフランスの政界地図を塗り替える。オランド大統領は国民にとって裏切り者だ。有権者は今目覚め、偉大なフランスを復活させようとしている。(外国人ではなく)フランス人が自国で優先される時代が、ようやくやって来た」と獅ししく子吼した。
リベラルな思想を持つ人や、外国人に寛容なフランス人たちは、FNの圧勝に茫然自失の状態である。彼らは今回の事態を、「séisme(地震)」と形容した。

パリで行われたFNのデモ(撮影: 筆者)
経済危機が背景に
フランスはユーロ危機による不況に苦しんでいるが、オランド大統領が有効な対策を打ち出せないでいるため、市民の不満は高まっている。FNの勝利は、有権者の政府に対する抗議の表明である。ル・ペン党首は、移民の流入制限と治安の強化を訴えてきた。またFNは、フランスのユーロ圏からの脱退とフランの再導入を求めている。現在、シェンゲン協定に加盟している国の間では国境検査が廃止されているが、FNは国境検査と関税の復活を求めている。
フランスではドイツに比べてグローバル化に対する反感が強く、企業がフランス国内の工場を閉鎖して労働コストが安い地域での生産比率を高めることに、人々は不安を抱いている。多くのフランス人にとって、欧州統合はグローバル化の初期段階であった。ル・ペン氏は欧州統合に対する人々の不満を利用して、得票率を大幅に伸ばした。今回のFNの選挙スローガンは、「ブリュッセルにノン、フランスにウイ」だった。ル・ペン氏の訴えは、「EUが私たちの日常生活に不当に介入している」と感じるフランス人の心をつかんだ。
さらにFNは近年、穏健化路線を強めることによって、「極右政党」という悪いイメージの払拭に努めてきた。このため、FNに票を投じることに対する有権者の抵抗感は、年を追うごとに減ってきた。特に、2011年にル・ペン氏が党首になってからは、同党は極右的、人種差別的なスローガンを控えて、市民に受け入れられやすいソフト路線に切り替えている。
FNを創設した父親ジャン・マリー・ル・ペン氏は頑固な極右政治家で、ナチスへの共感や反ユダヤ思想を隠さなかった。彼は「アウシュヴィッツにガス室があったかどうかは、第2次世界大戦の歴史の細部に過ぎない」と発言し、罰金刑を言い渡された。また、「ヒトラーの台頭は通常の選挙によって達成されたのだから民主的だ」とも語っている。一方、娘のマリーヌはそのような態度を表に出さないよう細心の注意を払ってきた。
しかし、いくらオブラートで包んでも、FNの本質が外国人の権利制限を目指す極右政党であることに変わりはない。同党は欧州議会選挙のための政見放送の中で、「シンティー・ロマの流入はフランスが抱える最大の問題の1つだ」と訴えている。人々の外国人に対する反感を煽る、一種のヘイトスピーチだ。
英独でも反EU派が躍進
英国でも予想外の展開があった。反EU政党のイギリス独立党(UKIP)が、保守党や労働党を上回る27.5%の得票率を記録し、トップの座に立ったのだ。同党は、英国のEU脱退や移民の制限、外国企業の英国への直接投資の制限などを求める右派ポピュリスト政党である。ナイジェル・ファラージ党首は、「英国がEUから脱退すれば、1200億ポンド節約できる」と主張している。これまで英国のキャメロン首相はUKIPを「愚か者と人種差別主義者の集まり」と評していたが、今回の開票結果はUKIPが英国でもはや無視できない勢力となったことを示している。さらにこの選挙結果は、英国の有権者へのEUに対する不信感の高まりをも浮き彫りにした。英国が将来EUから脱退する可能性は、一段と高まったと言える。
反EU政党はドイツでも躍進した。ユーロの段階的廃止を求める新政党「ドイツのための選択肢(AfD)」は、7.1%の得票率を記録し、欧州議会入りを果たした。フランスや英国とは異なり、政権党であるキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)と社会民主党(SPD)が62.6%を確保したが、AfDは結党からわずか1年余りで保守系市民約200万人の間に一定の地盤を築き上げた。逆にかつて連立政権のパートナーだった自由民主党(FDP)は得票率を11%から3.3%に減らし、事実上「泡沫政党」となった。FDPはAfDに大量の票を奪われたのである。
欧州議会選挙の開票結果は、欧州のエリート層と庶民の間で、意識の格差が広がりつつあることを浮き彫りにしている。はたしてEUは、市民の信頼を回復できるのか。各国の既成政党の前途も多難である。
6 Juni 2014 Nr.979



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック