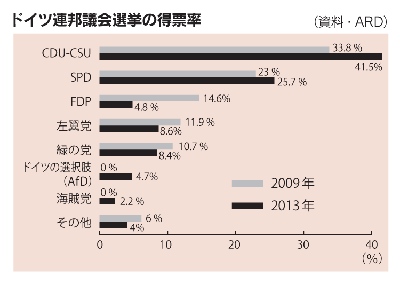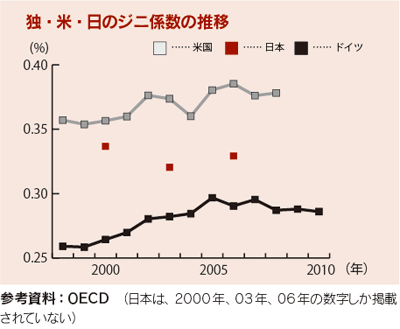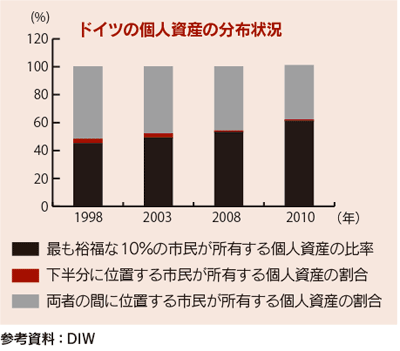10月6日、アフガニスタン北部のクンドゥスにあるドイツ連邦軍の基地を、ヴェスターヴェレ外相とデメジエール国防相が訪れた。
彼らは、アフガン軍と警察にこの基地を引き渡すための式典に出席したのである。主権の譲渡を象徴する木製の大きな鍵が、ドイツ人の閣僚たちからアフガン政府の内相らに手渡された。
一時は4500人が駐留
約11年にわたってアフガニスタンに駐留していたドイツ連邦軍は、今年10月末までに完全に撤退する。
2001年以降、米英仏など50カ国が、国連決議の下に国際治安支援部隊(ISAF)として延べ8万5000人の将兵をアフガニスタンに派遣してきた。テロ組織アルカイダは、2001年までタリバン政権の支援の下、アフガニスタンに訓練施設や基地を持ち、米国で同時多発テロを実行した。
各国は、アフガン政府が自力で軍と警察力を作り上げ、過激勢力に対抗できるよう訓練を施し、復興を助けることを任務としていた。
ドイツ連邦軍は当初、首都カブールに1200人の兵士を駐留させていただけだったが、2006年にはアフガニスタン北部の治安維持を任された。このためドイツは、一時4500人の将兵を同国に駐留させていた。
初めて戦闘を体験
アフガニスタン駐留は、ドイツ連邦軍を大きく変えた。1955年に創設された連邦軍は、この国で初めて地上での戦闘を経験したからである。
これまでアフガニスタンでは、米軍を中心に3000人以上の兵士が戦死し、ドイツ軍の兵士も54人が命を落としている。連邦軍の歴史で、戦死者が出たのは初めてのことである。クンドゥス基地の一角には、戦死した兵士たちに捧げられた慰霊の壁があり、兵士たちの名前入りプレートが貼り付けられている。冷戦の期間中には、「戦死」とか「戦闘で負傷」という言葉はドイツ人にとって抽象的な概念でしかなかったが、アフガンでの駐留によって、現実のものとなったのだ。
アフガン駐留は、ボスニアやソマリアで経験したような平和維持任務ではなく、いつ攻撃してくるか分からないゲリラたちとの、神経をすり減らすような戦いだった。当初ドイツの政治家たちは、「ドイツ連邦軍が戦争に参加している」という言葉を使うことを避けていた。しかし彼らも、タリバン・ゲリラの待ち伏せ攻撃や、自爆テロによってドイツ人の戦死者が増えるにつれ、連邦軍兵士たちが戦争に巻き込まれていることを、公に認めざるを得なかった。
激しい戦闘で負傷したり、目の前で戦友が殺されるのを目の当たりにして、帰国後も心的外傷後ストレス障害(PTSD)という精神的機能障害に苦しむドイツ人も少なくない。
クンドゥスの悲劇
2009年9月4日には、悲惨な事件が発生した。ドイツ連邦軍はアフガニスタン北東部で、「抵抗勢力タリバンのゲリラが、ガソリンを満載したタンクローリーを乗っ取った」という通報を受けた。ドイツ連邦軍のクライン大佐は、「タンクローリーが自爆テロに使われる危険がある」と考え、この車両を攻撃するよう米軍に要請した。それを受けた米軍の戦闘機が、川の砂地にはまって動けなくなっていた2台のタンクローリーを、爆弾で破壊した。
この攻撃でアフガン人は少なくとも約140人が死亡したが、当時の国防相だったユング氏は事件の3日後、「死亡者はタリバンのテロリストだけ。市民への被害はなかった」と発表。しかしアフガン政府の調べで、死亡したのはタリバン・ゲリラだけではなく、約40人の市民も空爆の巻き添えになっていたことが明らかになった。
タリバンはタンクローリーが立ち往生したため、近くの村の住民を呼び集め、ガソリンを配って重量を軽くし、車両が砂地から抜け出せるようにしていた。このため、多くの住民が車両の回りに集まっていたのだ。
同年11月末に、ビルト紙が暴露した事実は、ドイツ政府を窮地に追い込んだ。空爆の翌日にドイツ連邦軍の憲兵は現場を視察し、「ゲリラだけでなく市民も多数死傷している」という報告書を国防省に送っていた。つまり元ユング国防相は、市民の間に犠牲者が出ていることを知りながら、数日間にわたって「死亡者はゲリラだけ」と嘘をついていたのである。
同年11月に発足した新政権でユング氏は労働相に任命されていたが、メルケル首相はユング氏を更迭。「アフガン市民をタリバンから守る」というドイツ政府の大義名分は、多数の市民を死傷させた空爆で、大きく傷付けられたのだ。
アフガンの未来は?
今後、ISAFはアフガニスタンから徐々に撤収するが、その後、同国の治安がどうなるかについては不透明だ。各地に軍閥が割拠する状態は変わっておらず、政治家や官僚の腐敗が伝えられる。現在は守勢に追い込まれているタリバンが、ISAFの主力部隊が撤退した後に攻勢を開始し、欧米が支援する政権への攻撃を強める可能性もある。
同国に過激勢力が復活し、ISAFに協力したアフガン人や女性たちが弾圧される事態は、是が非でも防がなくてはならない。欧米諸国は今後も、アフガニスタンと長く関わらざるを得ないだろう。
18 Oktober 2013 Nr.964



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック