クリスティアン・ヴルフ連邦大統領が10月3日の統一記念式典で行った演説が、大きな議論を巻き起こしている。ヴルフ氏は「ドイツは世界各地からこの国にやってくる人々に対して開かれた国でなくてはならない。我々は移民を必要としている。外国人や帰化した外国人たちが、現在ドイツで行われている議論によって傷付いてはならない」と述べ、外国人を弁護する姿勢を示した。彼はティロ・ザラツィン氏の著作が引き金となってトルコ人などイスラム系市民に対する批判が強まっていることから、移民系市民の側に立とうとしたわけである。
そして彼は演説の中でこう言った。「キリスト教とユダヤ教は疑いなくドイツ文化の一部だ。しかし今ではイスラム教もまたドイツの一部だ」。この言葉に対して、連立政権の一翼を担うキリスト教社会同盟(CSU)から、激しい反発の声が上がったのである。
たとえばCSUのフリードリヒ議員は「ドイツの指導的文化は、キリスト教・ユダヤ教であり、イスラム教は指導的文化ではない。イスラム教がドイツ文化の一部であるという大統領の発言には同意できない」と述べた。CSUのほかの議員たちも、「イスラム教をキリスト教・ユダヤ教と同列に並べるのはおかしい」としてヴルフ氏の発言を批判している。
バイエルン州の首相であるゼーホーファーCSU党首は、さらに右寄りの発言をした。彼は「トルコやアラブからの移民が、ドイツ社会になかなか溶け込めないのは明らかだ。ほかの文化圏からの移民はもう必要ない」と述べ、ヨーロッパ以外からの移民の停止を求めたのだ。「ほかの文化圏(aus anderen Kulturkreisen)という言葉を文字通り解釈すると、トルコやイスラム諸国だけでなく、日本も含めたアジア諸国やインドなどからの移民も拒否するということになる。
天然資源に乏しいドイツの経済を支えているのは、外国との貿易である。この国の雇用の3分の1は、外国とのビジネスに直接・間接的に関わっている。私はヴルフ大統領が言うように、ドイツは外国に対して門戸を閉ざしてはならないと考えている。戦後の西ドイツは外国人の受け入れについて、比較的寛容な国だった。私はこのことが経済的、文化的にドイツを豊かにしてきたと思う。
移民の中には高い教育水準を持ち、ドイツの経済や文化に貢献している人もいる。トルコ人やイスラム系市民の中にも、高度な教育を受けた人はいるはずだ。たとえそうした人々が少数であっても、「異文化圏からの移民はいらない」として門を閉ざすことは、ドイツを精神的に貧しい国にするのではないだろうか。少なくともドイツの国際的なイメージを悪くすることは間違いない。CSU党員らの発言には、外国人に不満を持つ市民の票を確保しようとする意図がうかがえる。
ザラツィン氏の著作「Deutschland schafft sich ab」は110万部も売れた。マスコミも含めてこの本を批判するドイツ人は、少数派になりつつある。この本を読んだ多くの大学教授らが、次々に「正しい内容だ」とお墨付きを与えている。彼の本に集められているデータや見解は客観的には正しいかもしれない。しかしネオナチが支持する本がベストセラーリストの第1位になり、ほとんどのドイツ人がその主張に賛成するのは、外国人の1人として薄気味悪い。20年前のドイツでは考えられなかった現象だ。ドイツ政府の過去40年の移民政策に対するドイツ人の不満、この国で異文化が増殖することへの不安は、それほど大きいのである。統一後のドイツ人の意識は水面下で保守性を強めているのだろうか。その方向をしっかりと見極める必要がある。
22 Oktober 2010 Nr. 839



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック 1990年10月3日、当時のコール政権は東西ドイツの統一に成功した。ドイツはベルリンの壁崩壊から1年足らずで東西分断に終止符を打ち、国家主権を回復するという悲願を達成したのだ。コール氏の政治的センスは評価に値する。彼は壁崩壊をドイツ統一への千載一遇のチャンスと考え、わき目も振らずにこの目標へ向けて猪突猛進したのだ。私は1990年9月からミュンヘンに住んで、統一後ドイツがどう変化したかを定点観察してきたが、スピード統一の背景にはコール氏の手腕だけではなく、いくつかの「幸運」があったことを強く感じる。
1990年10月3日、当時のコール政権は東西ドイツの統一に成功した。ドイツはベルリンの壁崩壊から1年足らずで東西分断に終止符を打ち、国家主権を回復するという悲願を達成したのだ。コール氏の政治的センスは評価に値する。彼は壁崩壊をドイツ統一への千載一遇のチャンスと考え、わき目も振らずにこの目標へ向けて猪突猛進したのだ。私は1990年9月からミュンヘンに住んで、統一後ドイツがどう変化したかを定点観察してきたが、スピード統一の背景にはコール氏の手腕だけではなく、いくつかの「幸運」があったことを強く感じる。 今年9月9日、ポツダムのサンスーシ宮殿でメルケル首相は1人のデンマーク人を表彰した。彼の名はクルト・ヴェスタゴー。2005年にイスラム教の預言者ムハンマドのターバンが爆弾になっている風刺画を描いたために、世界中のイスラム教徒から抗議の的となった。一部のイスラム諸国では、この絵がきっかけとなって暴動まで起きた。
今年9月9日、ポツダムのサンスーシ宮殿でメルケル首相は1人のデンマーク人を表彰した。彼の名はクルト・ヴェスタゴー。2005年にイスラム教の預言者ムハンマドのターバンが爆弾になっている風刺画を描いたために、世界中のイスラム教徒から抗議の的となった。一部のイスラム諸国では、この絵がきっかけとなって暴動まで起きた。 9月10日夜、バイエルン州のトゥッツィングでグッテンベルク国防大臣の演説を聞いた。さすがに、ドイツで最も人気のある政治家だ。900人の聴衆で会場は満員。大臣は雄弁で、演説には若い力とユーモアが込められていた。ドイツには珍しい、カリスマ性を持つ政治家である。
9月10日夜、バイエルン州のトゥッツィングでグッテンベルク国防大臣の演説を聞いた。さすがに、ドイツで最も人気のある政治家だ。900人の聴衆で会場は満員。大臣は雄弁で、演説には若い力とユーモアが込められていた。ドイツには珍しい、カリスマ性を持つ政治家である。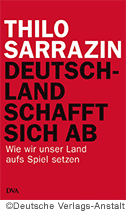 ドイツでは連邦銀行のティロ・ザラツィン元理事の著作がきっかけとなって、外国人をめぐる論争が激しく燃え上がっている。ザラツィン氏はドイツ政府と連銀の事実上の圧力によって理事を辞任したが、彼の著作「Deutschland schafft sich ab」は、シュピーゲル誌のベストセラー・リストの第1位に躍り出たほか、書店で品切れになるほどの人気だ。
ドイツでは連邦銀行のティロ・ザラツィン元理事の著作がきっかけとなって、外国人をめぐる論争が激しく燃え上がっている。ザラツィン氏はドイツ政府と連銀の事実上の圧力によって理事を辞任したが、彼の著作「Deutschland schafft sich ab」は、シュピーゲル誌のベストセラー・リストの第1位に躍り出たほか、書店で品切れになるほどの人気だ。





