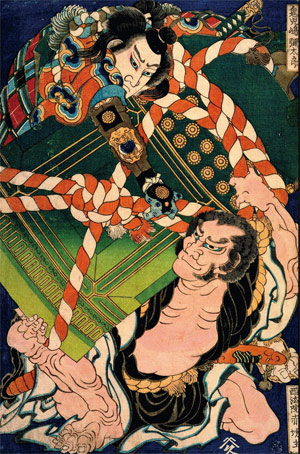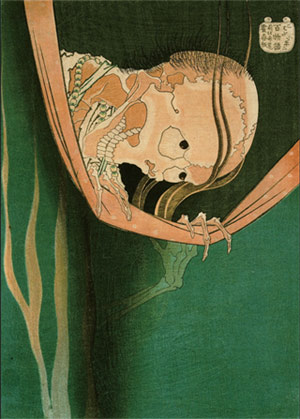ルドルフ・ヴァインスハイマー
ルドルフ・ヴァインスハイマーRudolf Weinsheimer
チェリスト
1931年ヴィースバーデン生まれ。8歳でチェロを始める。北西ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団のソロ・チェロ奏者を経て、1956年、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のチェロ奏者に就任。1978年から84年まで楽団員代表を務めた。1996年、定年により引退。1997年にドイツ連邦政府より功労十字小綬章を、2015年に日本政府より旭日小綬章をそれぞれ受章した。
「人生を変えた日」というものがある。ベルリン在住のチェリスト、ルドルフ・ヴァインスハイマー氏にとってその日とは、紛れもなく1956年6月1日だった。氏の言葉には、60年前に味わった驚きと感動が今もほとばしる。
1955年のある日のことです。当時私が所属していたヘルフォルトの北西ドイツ・フィルの同僚から、ベルリン・フィルがチェロ奏者を一人募集していることを聞きました。私は自分への一大挑戦と決意して、その日のうちに願書を送りました。すると半年後、ベルリンからオーディションの招待状が届いたのです! 私は興奮して、すぐに猛練習を開始しました。
ベルリン・フィルのオーディションでは、芸術監督のカラヤンを始め、楽団員全員が顔を揃えます。私は誰か聴いてくれる人が欲しくて、それから3週間、毎晩台所に行って下宿先のおかみさんの前で演奏しました。彼女は熱心に聴いてくれただけでなく、毎回香りの良いコーヒーを用意してくれました。
迎えた56年6月1日のベルリンでのオーディション。いよいよ私の番になって舞台に立つと、あのカラヤンが目の前にいます。鼓動が高まり、さあ弾こうと思ったとき、後方のドアが開きました。するとその奥の食堂から、コーヒーの香りが漂ってきたのです! 突然、私は台所のおかみさんの前にいる気分になり、完全にリラックスして弾くことができました。
夕方の最終選考の後、楽団の代表者が私のところに来て、「われわれのオーケストラはあなたを選びました」と告げました。今も忘れられません。私の人生を変えた一言です。
まさに黄金時代を迎えようとしていたヘルベルト・フォン・カラヤンとベルリン・フィルは、翌1957年、初の来日公演を行う。その直前、ベルリンの独日協会がベルリン・フィルのメンバーを招待して、日本について紹介する機会を作った。ヴァインスハイマー氏はそのとき同じテーブルに座っていた女性に一目惚れをする。
当時、独日協会の会長を務めていた日本学のヘルベルト・ツァッヘルト教授の令嬢フリーデルさんだった。戦前、ツァッヘルト教授が旧制松本高校で教鞭をとっていた時代に信州の松本で生まれたフリーデルさんは、日本人とのハーフの母親を持つ。その2年後、ヴァインスハイマー氏はフリーデルさんと結婚。日本との関係も自然と密になってゆく。
35歳の誕生日に、私はチェロの同僚3人を招いて、自宅でチェロ・カルテットの曲を演奏しました。その演奏に感銘を受けた義理の父は、「早稲田大学の大隈講堂というところで演奏してみないか?」と私に提案したのです。彼は当時ボン大学日本学科の教授を務めており、ボン大学と早稲田大学は姉妹校だったことで、学生や教員の交流が活発に行われていました(これは現在まで続きます)。1966年、ベルリン・フィルの2度目の来日公演の際、われわれ4人は大隈講堂で演奏し、約1500人の学生たちから熱狂的な喝采を受けました。これが今日まで交流が続く早稲田大学との最初の出会いです。
面白いことに、このチェロ・アンサンブルは4人では終わらなかった。
1972年3月、12人のチェロのために書かれた珍しい曲があるというので、ザルツブルクのモーツァルテウムでベルリン・フィルのチェリスト全員で公開録音を行いました。これが後に有名になるアンサンブルグループ「ベルリン・フィル12人のチェリストたち」の誕生の瞬間で、私はそのリーダー役を務めることになりました。1974年にわれわれは本格的なデビュー公演を行いますが、その「リハーサル」として、初めて一公演のプログラムを通して演奏したのも大隈講堂だったんですよ。
これまで数々の場所で演奏してきましたが、特に忘れられない経験の一つが天皇皇后両陛下の御前で演奏したことです。私は当時、近所のシュラハテンゼーという湖の周りをジョギングするのを日課にしていましたが、ある日、走りながら「ドイツのヴァイツゼッカー大統領から、即位された天皇陛下へのお祝いとして『12人のチェリストたち』のコンサートをプレゼントするのはどうだろう?」というアイデアがひらめいたのです。
大統領に連絡を取ると、私の提案にすぐに賛同してくれて、1992年7月、われわれは皇居にて両陛下の前で演奏する光栄に浴しました。両陛下は音楽に大変理解がおありで、その後も折に触れてわれわれのコンサートを聴きに来てくださいました。
この1992年、ヴァインスハイマー氏はもう一つ、「途方もない」コンサートを実現していた。ベルリンのツェーレンドルフ地区が750周年を迎え、区長から「アマチュアのチェリストと一緒に演奏する特別な機会を作ってもらえないか」という依頼を受けた。ベルリン・フィルの12人のチェリストのうち9人がこの地区に住んでいる縁もあった。早速、演奏会を企画したところ実に老若男女341人のチェリストが集まり、やはり記念年を迎える隣のポツダム市の新宮殿前でハーモニーを奏でたのだ。が、話にはまだ続きがある。
その数年後、私は日本ツアーの際に神戸の串揚げ屋「串乃家」のオーナー、松本巧さんと出会いました。「ポツダムでこれだけのチェリストが集まった。日本でやったらもっと大きなチェロの祭典にならないだろうか」と自身アマチュアのチェリストである松本さんに相談したところ、「神戸でやるならぜひ協力したい」とオーガナイズを了承してくれました。
1998年、アマチュアとプロを交えた1013人による前代未聞の「1000人のチェロ・コンサート」が、阪神大震災のチャリティー公演として神戸で実現します。このコンサートはその後も数年ごとに開催され、2015年には東日本大震災への復興支援として仙台で行われました。


1998年に始まった「1000人のチェロ・コンサート」
4人のチェリストから1000人のチェリストへ。いずれも日本との縁を経由して生まれた友情の輪だった。2015年秋、ヴァインスハイマー氏は「日本・ドイツ間の音楽を通した交流及び相互理解の促進に寄与」したことで日本政府より旭日小綬章を授与された。85歳を迎えた今も、名誉顧問を務める早稲田大学交響楽団の海外公演の実現のためにサポートを続けている。
このアマチュア音楽家の楽団は、2018年に通算15度目となるヨーロッパツアーを計画しています。年齢的に見て、私が直接関わるのは次が最後になるでしょう。音楽は平和に貢献します。これまで信じられないほど卓越した演奏を披露してきた彼らのために、素晴らしい演奏旅行の場を作りたいと思っています。
(取材・文:中村真人)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック

 ドイツ社会の中で、ドイツ人に紛れるように数十年間を暮らしていても、老年に差し掛かると徐々に日本人であることを思い出していく過程が皆さんにあるようです。
ドイツ社会の中で、ドイツ人に紛れるように数十年間を暮らしていても、老年に差し掛かると徐々に日本人であることを思い出していく過程が皆さんにあるようです。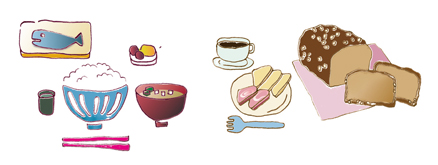


 東日本大震災
東日本大震災