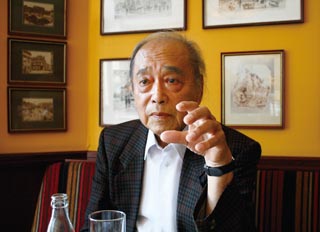ミヒャエル・ベッカー Michael Becker
ミヒャエル・ベッカー Michael Beckerトーンハレ・デュッセルドルフ インテンダント
1966年生まれ。少年合唱団やEUユース管弦楽団に所属し、子どもの頃から音楽に親しんだ。ケルン室内管弦楽団など多数のプロオーケストラに参加。大学では音楽とジャーナリズムで学位を取得。1993~2006年、ニーダーザクセン音楽祭のインテンダントを務め、その傍らでジャーナリストとして執筆活動やラジオ出演も。2007年、トーンハレ・デュッセルドルフのインテンダントに就任。
暖かい季節がやって来ると、デュッセルドルフ市民の週末の憩いの場はライン川沿いのプロムナードがメインとなる。ずらりと並ぶプラタナスの木漏れ日を受けながら、旧市街からさらに北上して行くと、エメラルドグリーンのドームが目に入る。この独特な美しさで存在感たっぷりの建築物が、デュッセルドルフの音楽の中枢。コンサートホール「トーンハレ」だ。
日本人が多く住む街デュッセルドルフにあって、ここ数年、日本と関連の深いプログラムが数多く企画され、在独日本人の耳を楽しませてくれている。「生活の中に音楽が溶け込む欧州での暮らしを、同地に住む日本人にも存分に楽しんでもらいたい」。そう語るのは、2007年からトーンハレのインテンダントを務めるミヒャエル・ベッカー氏。
日本に興味を持った最初のきっかけは、当時付き合っていた女性の存在です。
と、少年が秘密を打ち明けるように教えてくれた。日独ハーフの彼女の母親は岡山出身の生粋の日本人。ピアニストでもある彼女の存在が、ベッカー氏の日独音楽プロジェクトの推進を後押しした。
デュッセルドルフに来る前から、日本に関連のあるプロジェクトを多数手掛けてきました。そして、ここトーンハレのインテンダントに就任してからは、さらに多くの日本人アーティストと関わりを持つようになり、2年に1度、“Konnichiwa, Japan”という企画を開催するに至りました。これによって、飯森 範親, 佐渡 裕, 諏訪内 晶子, アリス=紗良・オット, 宮田 まゆみ, 札幌交響楽団など、たくさんの日本人音楽家をトーンハレに迎えることができました。
ちなみに、ぼくを日本と結びつけた彼女、ピアニストのサラ・コッホは、今では僕の妻です。
音楽一家に生まれた者の幸運な宿命か、ベッカーさん自身も音楽家だと言う。
私はヴィオラ奏者です。実は、ドイツにはヴィオラ奏者に関する、それはもう膨大な数のジョークがあって、笑いのネタにされやすいんですよ。でもね、私はこの美しい音色を奏でる楽器を学び、演奏することをとても誇りに思っています。1992年までは私自身、演奏家として各地のオーケストラで演奏してきました。でも、音楽ばかりやってきたわけではありません。私はジャーナリズムを学んだので、長年、新聞社やラジオ局でもジャーナリストとして働きました。
トーンハレの魅力について伺うと、彼がどれほどこのコンサートホールに魅力を感じているかが分かった。
まず、外観の美しさに関して言えば、トーンハレは確実にヨーロッパで最も美しいコンサートホールの1つに数えられるでしょう。かつて、世界最大のプラネタリウムとして作られた建造物は1978年、コンサートホールとして音楽界の宝物に生まれ変わったのです。

緑のドーム型の屋根が目印
© Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
デュッセルドルフ芸術アカデミーと美術館、ラ イン川に囲まれた立地は、芸術を親しむ環境として恵まれている。最寄の地下鉄駅(Tonhalle/Ehrenhof)からトーンハレに通じる壁面も、フォトコラージュの作品で埋め尽くされており、そこへ向う人の目を楽しませてくれる。一歩一歩会場へと近付くたびに、美しいものに触れる準備ができていく。そんな感じがする。
さらにコンサートホールの中に入ると、その空 間の美しさに息を呑む。紺碧の星空のようなドームの天井。コンサートでは、そこに音が吸い込まれ、拍手がまたたく無数の星のように降り注ぐのだ。
組織的にも、トーンハレはとても強固に団結しています。独自のオーケストラ、デュッセルドルフ・シンフォニカーを抱え、彼らのコンサートがトーンハレを活気付かせているのですから。トーンハレは、小さいながらも意欲に溢れたチームとして活動しています。「美しさ」「組織力」「意欲」の3つの要素が渾然一体となってトーンハレを支えているのです。
トーンハレは、ドイツで一番若いコンサートホールです。私たちは、子ども向けにも、大人向けにも、それぞれの年代の心に響くプログラムを吟味し、多種多様なコンサートをご提供しています。生まれる前の子どもから老夫婦まで、すべての世代の文化的な共感を得るため、そしてそれぞれの心と音楽を赤い糸で結ぶため、新しいことにも意欲的に取り組んでいます。

プラネタリウムだったトーンハレが誇るホールの内装
トーンハレを監督し、運営するのが「インテンダント」の役目。ベッカーさんの任務とは。
インテンダントである私は、トーンハレとデュッセルドルフ・シンフォニカーをより広く発展させる任務を負っています。私の仕事は、従業員の教育やコンサートの回数についての実務面からコンサートの形式やアーティストの選択などを監督する役目まで多岐にわたり、常時200人の従業員と一緒に働いています。

日本人の皆さんに、音楽の魅力を
知ってもらいたいと熱弁する
ベッカーさん
CDやDVDが販売され、今やインターネット経由で、コンサート中継を聴くこともできる。現代社会は、芸術に関わるコンテンツを家から一歩も外に出ずとも気軽に体験させてくれるが、コンサートホールで生の演奏を聴くという行為が特別な理由は何か、どんなところに魅力があるのだろうか。
一度でもトーンハレに足を運んでくださった観客の皆さんは、その後もまた再び訪れてくれます。CDなどの録音媒体との違いは、2度と味わえない、1度きりの体験だということ。コンサートでは、ホールを埋めるほかのたくさんの人々と共に時間を過ごし、音を聴いて、演奏を観る。演奏者たち(場合によってはソリスト1人)が、彼らの秘密を、ここではありったけの力をもって明らかにしてくれる。つまり、音楽の魅力を。
演奏者と観客とが一体となる空間でだけ得られる、この直感的な感覚に触れたなら、それはきっと忘れられない体験となるはず。もちろんCDは最高の演奏を聴かせてくれます。でも、個人的な経験という意味では、コンサートで得られるものは、CDなどの二次的な音から得られるものとは比べ物にならないんじゃないかと思います。

コンサートの合間の休憩は、コロッセウムのような広場で
2011年は、日独交流150周年の年。このために、ドイツでは多数のイベントが企画されている。もちろん、トーンハレも例外ではない。
2011年は、ドイツと日本にとって重要な年であることは確かです。私たちも日本との関係の中でどんなことができるかと考え、いろいろとプランを立てました。3月11日の東北太平洋沖地震が起きた今、「2011年」は、日本にとってまったく違った意味を持つ年となりました。このことは、私たちにとっても大きなショックであると共に、友人である日本のため何かしたいという思いに駆られました。3月26日にチャリティーコンサートを開催しましたが、このコンサートでは、デュッセルドルフ・シンフォニカー、ケルン放送交響楽団、デュッセルドルフ市楽友協会、ケルン放送合唱団とソリスト4人が、このコンサートのために日本から緊急来独した指揮者佐渡裕氏の指揮で演奏しました。曲は、ベートーベンの「第9」。この交響曲を選んだ理由は、これがドイツと日本を橋渡しする曲として一番有名で、勇気を与える曲だからです。日本の1日も早い復興を祈っています。
今年5月に開催を予定しているデュッセルドルフの日本週間は、日本とドイツの交流を祝う様々なイベントで彩られることでしょう。トーンハレでも、再び佐渡裕氏を迎え、デッセルドルフ・シンフォニカーの演奏に宮田まゆみの笙が冴えるコンサートが予定されているほか、尾高忠明が音楽監督を務める札幌交響楽団のヨーロッパツアーが、トーンハレにも上陸。ブレーメン・ドイツ室内フィルハーモニー管弦楽団は、狂言師と一緒に狂言風オペラ「魔笛」を披露するなど、たくさんの大小のプロジェクトを用意しており、ドイツと日本の文化の繋がりを余すことなく紹介します。私自身、この記念すべき年を一緒に祝い、プロジェクトに関われることをとても嬉しく思います。
ベッカーさんにとって、音楽とは?
Musik ist für mich ein Lebesmittel. Ohne Musik würde ich leiden.
(私にとって音楽は、日々の食事のようなもの。音楽のない人生は、辛く苦しいでしょうね。)
今後の夢は?
目標やゴールという意味で、私は夢を設定していません。実は、今までの人生の中でも自分のためにゴールを決めたことはないんです。
私は、コンサートの中で夢を見ます。そのコンサートが特別素晴らしいものであったときに。
インタビュー・構成:編集部・高橋 萌
5月13日(金)20:00、15日(日)11:00、16日(月) 20:00
デュッセルドルフ・シンフォニカー
指揮者:佐渡裕
笙:宮田まゆみ
プログラム:武満徹「セレモニアル -An Autumn Ode-」 /
細川俊夫「ランドスケープ V」 / 黛敏郎「饗宴」 /
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン「交響曲第7番」
チケット:13~34ユーロ(学生5ユーロ)
5月26日(木)20:00
狂言風オペラ「魔笛」
演奏:ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン管楽ゾリステン
狂言:大蔵流狂言師茂山一門
チケット:16~25ユーロ(学生5ユーロ)
5月27日(金)
札幌交響楽団
指揮者:尾高忠明
ソリスト:ヴァイオリニスト 諏訪内晶子
プログラム:武満徹「How Slow the Wind」 /
セルゲイ・プロコフィエフ「ヴァイオリン協奏曲第1番」 /
ピョートル・チャイコフスキー「交響曲第6番『悲愴』」
チケット:13~34ユーロ(学生5ユーロ)
Tonhalle Düsseldorf
Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf
チケット:0211-8996123
www.tonhalle.de



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック