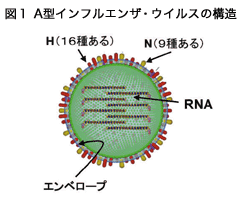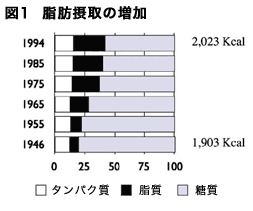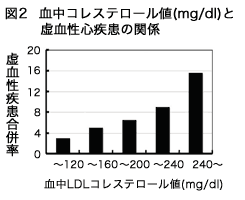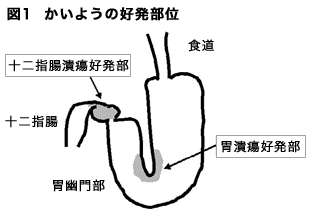肝臓の調子を測るバロメーターはありますか
昔から重要なことを「肝心」あるいは「肝腎」といいますが、実際、肝臓は私たちの生命維持にかかせない多彩な仕事をしている臓器です(表1)。しかし、残念ながらこれらが正常に機能しているかどうかを確かめる便利なマーカーはありません。酒豪の方は「お酒がおいしくなくなった時が肝障害」などと言われますが、これはバロメーターにはなりませんのでご注意を。
| 表1 主な肝臓の働き |
| * 栄養素の代謝とエネルギー源の貯蔵 * 胆汁の生成 * 解毒(薬物やアルコールの処理を含む) |
肝臓の状態を測るのに最も頻繁に使われているのは、ALT(GOT)とAST(GPT)という名の逸脱酵素です。肝臓の古い細胞は常に新しい細胞と置き換えられていますが、古い細胞が壊れる時に血液中に逸脱してでてくる酵素がこの逸脱酵素です。肝臓障害で多くの細胞が一時に壊されると、血液中の逸脱酵素値も上昇します。このため、逸脱酵素値が上昇している時には肝機能障害を疑い、肝臓病の精査をします。健康診断の項目にあるγ(ガンマ)GTP(GP)は、アルコールが肝臓の細胞を壊した時に上昇する逸脱酵素です。気になる方は、一度値を注意してみてください。
アルコールは健康によいとも言われますが
「酒は百薬の長」という諺がありますが、飲めば飲むほどよいという意味ではありません。飲酒量の度が過ぎるとアルコール性肝障害となり、中には肝硬変へと進み命を縮める場合もあります。上述のように、アルコールに最も敏感に反応するのが逸脱酵素γGTPです。健康診断で「γGTPが上昇していますよ。アルコールを控えてください」と言われた経験をお持ちの方も多いはず。きちんと禁酒をすれば同値は低下し、2~3カ月で正常値に戻ります。
ただし、肝臓はアルコール以外の薬剤などにも敏感に反応します。睡眠薬や精神安定剤などを常用している場合、同様にγGTPが上昇することがありますので注意が必要です。さて、アルコールの過飲は肝臓の細胞を壊す だけでなく、肝臓に中性脂肪を蓄積させ、脂肪肝になる 危険もはらみます。
脂肪肝とは何ですか
肝臓にトリグリセリド(中性脂肪)が過剰に(30%以上)貯まった状態で、ガチョウのフォアグラと同じです。今や男性3人に1人、女性も5人の1人にみられるあなどれない病気です。糖尿病、高脂血症、肥満など生活習慣病の方にしばしばみられますが、特に症状がないため、健康診断の血液検査でGOTやGPT値の上昇から、初めて見つかることも少なくありません。
脂肪肝は肝炎や肝硬変に移行することもあるため、見つかった時点での適切な生活管理が重要なポイントとなります。脂肪肝の原因は、多食やアルコールの飲み過ぎであることが多く、適度な運動を含めた生活習慣の是正が治療の主軸です。
肝硬変は恐ろしいイメージがあります
長期の肝臓障害の結果、肝臓の繊維化(組織が繊維成分に置き換わっていく状態)が進み形態的にも肝臓がゴツゴツとなった状態が肝硬変です。肝硬変の末期にはお腹に腹水が貯まるなど生命にとっても危険な状態となります。ドイツをはじめ欧州ではアルコールによる肝硬変が多いのですが、日本では、ウイルス性肝炎による肝硬変がほとんどです。こうしたウイルス性肝炎に起因する肝硬変の場合、肝臓がん(肝細胞がん)を併発することが少なくありません(図1)。
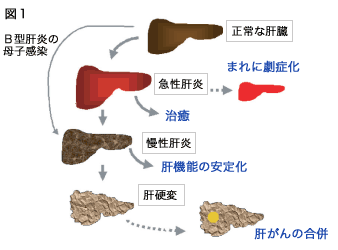
ウイルス性肝炎について教えてください。A型肝炎とは
A型肝炎ウイルスに汚染された食物や飲料水が口から入り、肝臓で増殖して起こる肝炎です。日本では以前に、ホタテや生牡蠣の摂取による集団発生がありました。A型肝炎は一時的な急性肝炎で、慢性化することはありません。一度感染・完治すれば、生涯にわたる免疫を獲得します。ただし現在の日本ではA型肝炎は少なく、中年以下では未感染の方が大半です。小児は軽くて済みますが、大人は重症になることが多いので、抗体を持っていない人は、ドイツ国外の汚染地区へ出張される場合など予防接種を行った方がよいでしょう。
B型肝炎とC型肝炎の違いは?
こちらはどちらも血液を介して感染する肝炎です。輸血や性行為のほか注射針の誤用などの医療ミスで感染することがあります。輸血後に急性肝炎が発症した場合は、95%以上がC型肝炎ウイルスによるものと考えられます。 C型肝炎は慢性化することが多いですが、日常的に接触する限りにおいては、家族間感染も認められていません。
一方B型肝炎ウイルスは、出産時に母親から子どもに感染(母子感染)することもあります。母子感染の場合、子どもは幼少期は全く症状がなく(キャリアーと呼びます)、大人になって気がついたら慢性肝炎や肝硬変になっていたという場合もあります。2~3歳以降にB型肝炎ウイルスに感染した場合は、急性B型肝炎を発症した後に完治するケースがほとんどです。
| 表2 ウイルス性肝炎の特徴 | |||
| A型肝炎 | B型肝炎 | C型肝炎 | |
| 主な感染ルート | 食物、水 | 輸血*、 母子感染 | 輸血*、医療器具 |
| 急性肝炎 | あり (発症後は治癒) | あり (母子感染ではなし) | あり |
| 劇症化 | まれ | あり | 少ない |
| 慢性肝炎への移行 | なし | 約10% 大人ではまれ 子供では効率 | 約60 - 70% |
| 慢性肝炎から肝硬変、肝細胞がんへの進展 | なし | あり | 多い |
*現在は輸血前に肝炎ウイルスの有無のチェックが行われています
肝がんを予防するために
さて問題は、B型肝炎とC型慢性肝炎は肝硬変へと移行し、さらに肝がんになりやすいということです。治療を行わなかった場合、C型肝炎の60~80%が慢性化し、うち30~40%が肝硬変へ、さらに一部は感染後30~40年で肝細胞がんに進行するといわれています(図1)。このため肝炎の予防と治療は大変重要です。現在、B型肝炎ウイルスに対するワクチンはありますが、C型肝炎に対するワクチンはなく、インターフェロンが治療に用いられます。肝がんは、定期的な肝機能検査、αフェトプロテインという腫瘍マーカーの測定、超音波検査(ソノグラフ ィー)などの画像診断により、早く見つけることができます。
日本の調査によると、アルコールによる肝機能障害だと考えていた人の約3分の1に、C型肝炎の感染が認められたということです。肝機能障害を指摘された方は、ぜひ1度、C型肝炎の抗体(HCV抗体)チェックを受けてください。
| 表3 主な肝機能検査の正常値(日本人の場合) | ||
| 基準範囲 | 肝障害における意味 | |
| ALT (GOT) | 8 - 40 IU/L | 肝細胞が壊れると上昇、 心筋梗塞でも上昇 |
| AST (AST) | 5 - 35 IU/L | 上に同じ |
| γGT (γGTP) | 男性 50 IU/L未満 女性 30 IU/L未満 |
アルコールの飲み過ぎや薬物性肝障害で上昇 |
| アルカリフォスファターゼ゙(ALP) | 測定法により違います | 胆汁排泄経路の障害で上昇、(胆石など) 骨の病気でも上昇 |
| 総ビリルビン | 1.0 mg/dl以下 | 胆汁排泄経路の障害で上昇、 値が高くなると黄疸が出現 |
| アルブミン | 4.0 - 5.0 g/dl | 肝硬変で低下 |
| Hbs抗原 | 陰性 | 血中にB型肝炎ウイルスが存在すると陽性 |
| HCV抗体 | 陰性 | 陽性の場合は過去にC型肝炎に感染したことを示す |
| HCV-RNA検査 | 陰性 | HCV抗体陽性の場合にC型肝炎ウイルスを直接的に検査する方法陽性は現在のウイルス保有を、陰性は過去の感染を意味します |
上記の基準値は測定法により違ってきます。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック