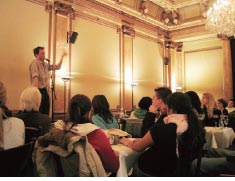エアバスが誕生する街
AIRBUS
ハンブルクに住んでいると、時折、イルカの形をした巨大な飛行機が低空飛行しているのに遭遇することがある。エアバスの胴体パーツなど大型の機体部品を輸送する貨物機「ベルーガ(シロイルカ)」だ。空飛ぶイルカは、なんとも言えぬ愛嬌があり、市民にも親しまれている。1995年のベルーガ就航以前は、ライバル、ボーイング社の「スーパー・グッピー」を利用していたため、「すべてのエアバス機はボーイングの翼で届けられる」と皮肉られていたそうだ。

ベルーガ(©AIRBUS S.A.S. 2007)
本社をフランスのトゥールーズに置くエアバス社は、1970年にフランスとドイツの企業連合としてスタート、その後スペイン、英国が加わり、現在は4カ国の航空機メーカー(仏独西共同のEADS社と英のBAEシステム社)の共同出資会社だ。エアバス社は目下、「パワー8」と呼ばれるコスト削減計画に取り組み始めているが、フランスとドイツが主導する経営陣の意見が食い違い、多国籍企業の経営の難しさを露呈している。今年は、1万人の人員削減と16工場の売却、あるいは閉鎖をめぐって、ドイツ、フランス間の議論は、ますます難航することだろう。
 |
エアバス社玄関 |
それにしても、技術者たちのチームワークは大したもので、フランスがコックピット部と主翼位置にある胴体上部を、ドイツがその他の胴体部と尾翼の一部を、スペインが主翼のつく胴体下部と尾翼の一部、そして英国が主翼をそれぞれ製造し、最終的にトゥールーズとハンブルクで組み立てる、という気の遠くなりそうな連携プレーを4カ国間 で行っている。
ドイツでは、北部のハンブルク、ブレーメン、ノルデンハイム、シュターデなどにパーツ工場があり、さらにハンブルクでは、「コンピュータ化されたコックピット」として話題をふりまいたA320型ファミリーであるA321、A319、A318の最終モンタージュとキャビン内装と塗装、さらに555人収容可能な世界最大の旅客機A380型のキャビン内装および塗装も行われている。日本の航空会社 ANAとスターフライアー発注のA320型ファミリー機はハ ンブルクで組み立てられているわけだ。
2005年の夏にその威容を市民の前に披露してくれたA380は昨年、複雑な電気系統のケーブルの取り付けにミスが生じ、最終モンタージュができないというトラブルが起こったが、今年10月には、1機目をシンガポール航空向けに出荷するめどがついたという。
ところでエアバスのハンブルク工場は、14歳以上であれば誰でも見学可能。エアバス社工場見学のサイトにアクセスし、Eメールあるいは電話で申し込む。通常はドイツ語だが、希望者は英語、フランス語のコースにも参加できる。当日は専門ガイドの案内で、1万人以上のスタッフが働く広大な工場群を2時間半ほどで回る。
 |
見学コースに組み込まれている組み立て工場 (©AIRBUS S.A.S. 2007) |
見学コースは、模型や機体のパーツなどが並ぶ小さな博物館にはじまり、ハンブルクで担当しているA320型ファミリーの胴体部の組み立て工場、さらにドイツで造られた胴体部と、フランスとスペインから運ばれた胴体部、および尾翼を繋ぐモンタージュ工場、主翼を取り付けるモンタージュ工場、キャビン内装工場と、製造工程に従って各工場を巡る。塗装工場は見学できないが、外にはカラフルに塗装された生まれたての飛行機がずらりと並んでいる。そのずっと先には、真新しいA380型の工場群が並んでいる。こちらは今年の秋以降から見学可能という。
http://airbus-werksfuehrung.de
(見学料:1人13 ユーロ)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック