今回は、今から150年ほど前のぶどう畑がどんな様子だったのか、想像をめぐらせてみましょう。
「ゲミッシュター・ザッツ(混植)」という言葉をご存知の方もおられると思いますが、当時のぶどう畑では、様々な品種が混ざった状態で栽培されていました。赤品種の隣に白品種、あるいは早熟品種の隣に晩熟品種といった具合だったのです。収穫量は1ヘクタール当たり20ヘクトリットル程度※1だったそうで、かなり低い数字です。今日も同程度の収穫量で醸造されるワインがありますが、できあがるワインは非常に高品質です。しかし「ゲミッシュター・ザッツ」では、品種ごとの最良の収穫タイミングを考慮することなどはできず、一挙に収穫してしまうため、未熟なぶどうも多く、高品質のワインは得にくかったようです。
そんな時代、欧州のぶどう畑は3つの困難に直面しました。1840年にウドンコ病、1863年にフィロキセラ、そして1878年にベト病が確認されたのです。この3つはいずれも北米から欧州に運ばれました。19世紀は欧州から北米・南米大陸へと人々が移住しはじめた時代。グローバル化により、それまで欧州に存在しなかった病害がもたらされたのでした。中でもフィロキセラの被害は凄まじく、欧州のぶどう畑の多くを壊滅させました。これら3つの病害は現在もなお、ぶどう畑を脅かし続けています。
1863年、ぶどうを根から食いつくし、枯らしてしまう体長1ミリにも満たない害虫フィロキセラを確認したのは、フランス、ヴォクリューズ県の栽培家でした。1871年の段階で、フランスでは10万ヘクタール以上のぶどう畑に被害が及びました。これはドイツの現在のぶどう畑全域に相当します。
ドイツ帝国成立翌年の1872年、ラインガウ地方のガイゼンハイムに「王立果樹・ぶどう研究所」が設立されます。この研究所の最初の使命がフィロキセラ問題に対処することでした。早くからフィロキセラに見舞われたフランスの研究者らと情報交換し、フィロキセラに耐性のある米国品種のぶどうを台木とし、それに欧州品種を接ぎ木する方法が採用されます。
しかし問題は簡単には解決しませんでした。フィロキセラに耐性のあるぶどうの産地は主に米国の北東部。同地は石灰分が少ない酸性土壌です。一方の欧州は石灰分が非常に多い土壌。初期の頃の台木はフィロキセラには効果があっても、欧州の土壌に適さず、ぶどうが鉄分不足になるという別の問題が起こりました。そこでフランスや当時のオーストリア=ハンガリー帝国の研究者は、複数の米国品種のぶどうを何通りも交配し、欧州の土壌になじむ台木を改良し始めます。
ドイツでも1870年代後半から、王立研究所が台木研究に力を入れはじめ、接ぎ木する欧州品種と相性が良く、ドイツの土壌に適合し、生育しやすい台木が次々誕生しました。その後、1935年のフィロキセラ法により、被害が予測される畑では接ぎ木ぶどうの栽培が義務付けられるようになり、植え替えが進むとともに混植の畑も減って行きました。1960年以降は接ぎ木ぶどうだけが植樹されるようになっています。ただ、樹齢100年前後の自根の古木が今日なお元気に育つ、モーゼル地方などの一部の畑に、リスク覚悟で新たに自根のぶどうを植えている醸造家もいます。
※1 ドイツでは収穫量を搾汁量で表すのが一般的。20hl/ haは約2800kg/ha。
ベルンハルト・コッホ醸造所(ファルツ地方)

コッホ・ファミリーと坂田千枝さん
コッホ家のルーツは1610年までさかのぼることができるという。現在のオーナーはベルンハルト&クリスチーネ・コッホ夫妻。ベルンハルトさんが父親から継いだ畑は7ヘクタール弱だったが、徐々に買い足し、現在では47ヘクタールを所有。ブルグンダー種のコレクションを充実させた。ぶどう畑での丁寧な手仕事を重視、個々の土壌のタイプ、ぶどう品種の特性を活かしたワイン造りが信条。厳格な選別収穫を行い,高品質のワインを生み出している。2013年からは日本人醸造家の坂田千枝さんを迎え、共同でワイン造りに取り組んでいる。次世代を担う長男のアレクサンダーはガイゼンハイム大学で栽培・醸造学を、次男のコンスタンティンはハイルブロン大学でワイン経営学をそれぞれ勉強中だ。
Weingut Bernhard Koch
Weinstraße 1
76835 Hainfeld
Tel. 06323 2728
www.weingut-koch.com
 2014 Grauburgunder „Letten“ Réserve
2014 Grauburgunder „Letten“ Réserve
2014 グラウブルグンダー・レッテン・レゼルヴァ 9€
ベルンハルトさんは当初、ブルグンダー系品種はシュペートブルグンダーだけを栽培していたが、現在ではヴァイスブルグンダー、グラウブルグンダー、そしてシャルドネが揃う。いずれもベーシックなワインから、レゼルヴァ、グランレゼルヴァまでを生産。ご紹介するのはハインフェルダーの「レッテン」という畑で栽培されているグラウブルグンダーのレゼルヴァ。「レッテン」は石灰質と粘土の混じるマール土壌。理想的な収穫期を見極めることに注力し、充実した味わいながら、軽やかでエレガントな仕上がりになっている。かりんや熟した洋梨の風味。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック
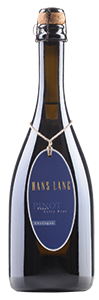 Sekt Pinot extra brut
Sekt Pinot extra brut
 2014 Reiterpfad Riesling GG
2014 Reiterpfad Riesling GG
 Zero Brut Nature
Zero Brut Nature
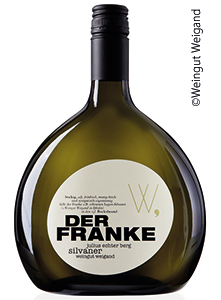 2014 Silvaner「Der Franke」
2014 Silvaner「Der Franke」





