1月下旬以降、欧州でも新型コロナウイルスが蔓延し、ドイツでは3月中旬に接触制限措置が発令されましたが、ようやく制約が緩和され始めています。この場をお借りして何よりもまず、医療や介護、食品、日用品などの生産と流通、生活の基盤を支えるさまざまな現場で働いておられる方々に感謝の気持ちを届けたいと思います。多くの人が思いがけずたくさんの時間を自宅で過ごすことになり、仕事や生活のスタイルを見直された方もおられたことでしょう。今回はドイツワインの世界での出来事をご報告します。
接触制限措置の発令後、生活必需品を除く全商店が一時的に閉店しましたが、ワイン専門店に関する規定はなく、州の判断に委ねられました。イベントや試飲販売は全て中止となりましたが、ほとんどの州で、衛生管理を徹底して営業が続けられていました。
消毒液不足に対しては、ワイン業界でも協同組合やガイゼンハイム大学などが臨時生産したり、 大手ワインメーカーが製造元にアルコールを寄付したというニュースを耳にしました。
欧州のワイナリーでは、今回のコロナ禍が人手を多く必要とする収穫期と重ならなかったのが何よりの幸いでした。3月以降は通常、新酒の試飲会をはじめとするイベントが目白押しですが、いずれも中止になりました。テイスティングコーナーでの試飲販売ができなくなったため、醸造所ではソーシャルメディアを活用するなどして、ワインのデリバリーに力を入れ、多くのワイナリーが宅配料金を一時的に無料にしていました。ワインをピックアップする顧客が車を降りなくても済むよう、ドライブスルー・スタイルで販売するようになった醸造所もあります。
ワイン関連のイベントが全て中止となったことを受けて、3月末にcheerswith.meというワイン業界支援のプロジェクトが立ち上がりました。主に造り手と消費者を繋ぐバーチャル・テイスティングで、参加者は試飲ワインを事前購入してテイスティングに臨みます。このライブ・テイスティングは好評を博し、cheerswith.meは5月末の段階で200回以上のテイスティングを達成しました。このほかにも数多くのオンライン試飲会やオンライン・セミナーが行われています。コロナ禍が一段落した後も、遠く離れた生産者と消費者を繋ぐバーチャル・テイスティングは存続するような気がします。
4月17日付の電子版シュピーゲルは、2月末から3月末にかけてのワインの売り上げが昨年の同時期と比較して34%増加したと報道しています。レストランやバーが閉鎖され、家庭での消費が増えているのでしょう。消費量が気になる方は、Wine in Moderation(www.wineinmoderation.eu)のサイトをご参考に、1日の適量(女性200ml、男性300ml程度)を守り、週に2日はアルコールを摂らない日を設けて、造り手の情熱がこもったワインを楽しんでいただけたらと思います。そのようなワインは開栓後も数日間、おいしくいただけるはずです。
さて、2007年から連載を続けてきた「ドイツワイン・ナビゲーター」は今回が最終回です。ドイツワインに関する書籍はまだ少ないため、今後もサイト内のバックナンバーを活用いただければうれしく思います。末筆ながら、読者の方々に心よりお礼申し上げます。
ユルゲン・ライナー醸造所(プファルツ地方)

ライナー一家。左からスヴェン、ハネス、マリー、ジモーネ
1974年にユルゲン・ライナーがプファルツ地方南部のイルベスハイムに創業した醸造所。現在は、ガイゼンハイム大学で醸造学を修めた2代目のスヴェン・ライナーが率いる。2005年にビオに移行、2011年にビオディナミ農法の生産者団体であるデメターの認証を得た。畑では健全な土壌を保つことに力を入れ、自然の声を聞き、自然と協調したワイン造りを実践している。ブドウの栽培と、ビオディナミ農法に欠かせない薬草などを素材とするプレパラート(調合剤)作りなどには親子で取り組んでいる。栽培ブドウはリースリングとブルグンダー系の品種が中心だ。セラーにおいてはブドウの持てる力を生かし、畑やヴィンテージの個性をそのまま映し出す、可能な限りナチュラルなワイン造りを実践している。
Weingut Jürgen Leiner
Arzheimer Straße 14,
76831 Ilbesheim/Pfalz
Tel 06341-30621
https://weingut-leiner.de
 2017 Ilbesheim Gewürztraminer trocken -unfiltriert-
2017 Ilbesheim Gewürztraminer trocken -unfiltriert-
2017年 イルベスハイム ゲヴュルツトラミーナ 辛口 -ノンフィルター-
15€
古代のアンフォラワインにヒントを得て、2015年からリリースしているゲヴュルツトラミーナ。樹齢は30年。トノー(500リットルの木樽)の上部の穴を片手が入る程度に広げて発酵容器とした。完璧なブドウだけを使用し、3割を手で除梗。1年間マイシェの状態で発酵、熟成させ、ろ過をせずにボトリング。ゲヴュルツトラミーナは香りが強く、食事に合わせにくいが、このワインは程よくオキシダティヴに仕上がっており、香りや酸味が一人歩きしていないので、食中酒にもぴったりだ。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック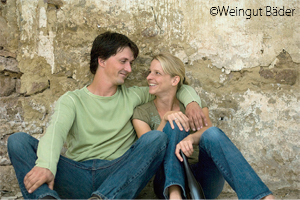
 2015 Spätburgunder Rotenfels
2015 Spätburgunder Rotenfels
 2017 Bechtheimer Riesling trocken
2017 Bechtheimer Riesling trocken
 2017 Petz Rotwein trocken
2017 Petz Rotwein trocken
 2018 Tacheles
2018 Tacheles





