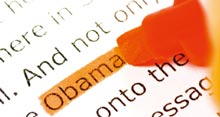©Senatsverwaltung für Finanzen
ザラツィン氏は、ベルリンのトルコ系やアラブ系の市民がドイツ語を学んで社会に溶け込むことを拒否し、社会保障に頼って生きていることを厳しく批判した。たとえば「ベルリン市民の20%は、経済的に不必要。ベルリンの新生児の40%は、下層階級で生まれている」と述べ、「彼らはドイツ政府の金で生きているくせに、政府を拒絶し、子どもにまともな教育を受けさせない。さらにスカーフを頭にまとった子どもをどんどん作る。トルコ系市民の70%、アラブ系市民の90%は、ドイツ社会に溶け込む能力がない」。
さらにザラツィン氏は、「私はむしろ、ドイツ人より知能指数が15%高い東欧のユダヤ人がこの国に増えて欲しいと思っている。社会に溶け込むための義務を果たさない外国人はもうごめんだ。能力を持ち、ドイツで一旗あげてやろうという外国人は大歓迎。そうでない人は、別の国へ行って欲しい」と述べた。
トルコ人やリベラルな考えを持つドイツ人たちは、この発言に激怒。彼が属する社会民主党からは除名を求める声すら出た。連邦銀行のヴェーバー総裁も「不穏当な発言だ」とザラツィン氏を批判したが、辞任に追い込むことはできなかった。同氏は担当分野を1つ減らされただけで、連邦銀行に留まっている。
私が興味深く感じたことは、保守系の新聞を中心として「ザラツィン氏の言うことは正しい」と、彼を支持する声が上がったことだ。特にフランクフルター・アルゲマイネ紙は「社会の中で袋叩きにされるのを承知の上で、真実を語ったザラツィン氏は、電車の中で子どもたちを助けようとして暴漢に殴り殺されたブルナー氏と同じ英雄だ」と持ち上げている。
つまり多くのドイツ市民は、「社会に溶け込まず、失業手当や生活保護で生きている外国人」に対して強い不満を抱いているが、世間体をはばかって口に出さない人が多い。彼らはザラツィン氏が、自分たちの考えを代弁してくれたと思っているのだ。
だが、1960 ~ 70年代に労働力が不足したためにトルコ人を労働移民として招き寄せたのは、西ドイツ政府である。ドイツ人は、トルコ人たちがいずれは母国へ帰ると思い込み、彼らにドイツ語の習得を義務付けるなど、社会に溶け込ませるための積極的な努力を30年近く怠ってきた。ドイツ人たちはこの国が「Einwanderungsland(移民が流入する国)」であることを2000年頃まで認めようとしなかった。外国人を社会に積極的に溶け込ませようとする制度が発足し、移民に語学の習得義務が課されたのは、2007年のことである。つまり、ドイツに10年以上も住んでいながらドイツ語を話せないトルコ人たちが自分たちの殻の中に閉じこもっている原因の一端は、ドイツ人にもあるのだ。
問題のインタビューの全文を読むと、ザラツィン氏が相当のインテリであることがわかる。しかし“ständig neue kleine Kopftuchmädchen produzieren“などという言葉は、極右のプロパガンダを思わせ、連邦銀行の役員にそぐわない。彼は社会に衝撃を与えて、政府が外国人の統合に本腰を入れることを希望しているのだろう。今後この国では、外国人についての論争が活発に行われるに違いない。
30 Oktober 2009 Nr. 789



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック