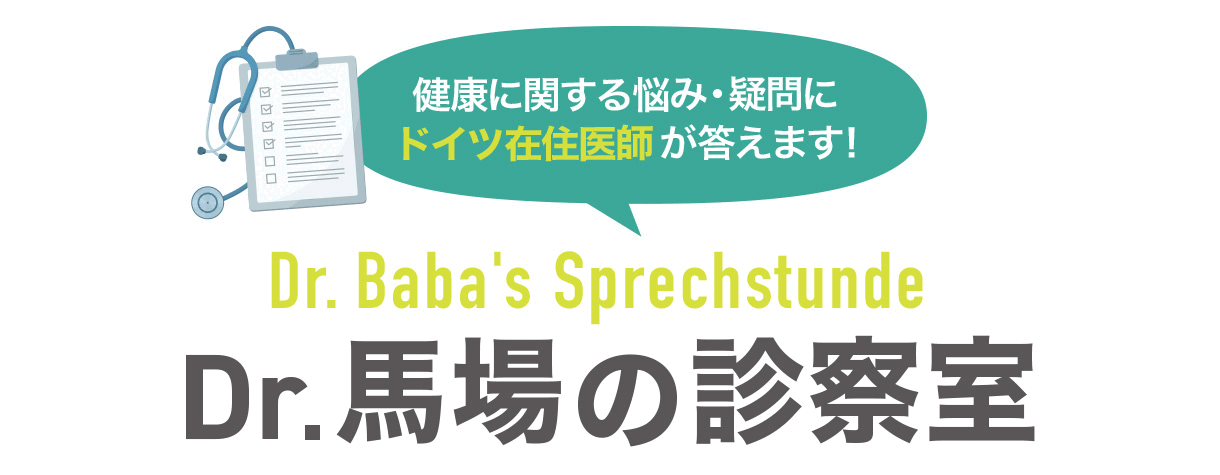ドイツ国外への出張中、マグロの刺身を食べたら、顔や首にじんましんが出ました。友人は白ワインは問題ないのに、赤ワインを飲むと頭痛を起こすことがあるようです。いずれも数時間後に症状はなくなりましたが、これはアレルギー反応でしょうか?
Point
- アレルギー反応ではありません
- 食中毒は食品のヒスタミン濃度が問題
- 不耐症はヒスタミン分解能低下が原因
- 赤身魚、発酵食品、加工食品に多く含まれる
- 赤ワイン、熟成チーズ、サラミにも注意
- 赤身魚の保存は冷凍庫、解凍は冷蔵庫内で
ヒスタミンとは何ですか?
花粉症や炎症に関与
ヒスタミン(Histamin)は、花粉症(Heuschnupfen)のようなアレルギー反応や、胃酸分泌、神経伝達物質にも関わる物質です。通常は特定の細胞内に蓄えられていますが、アレルギー反応などにより細胞の外に放出され多彩な作用を引き起こします。
皮ふが赤くなる、腫れる
ヒスタミンの血管拡張作用で、その部分の皮ふは少し熱感を伴って赤くなります(発赤、Rotung)。血しょう成分が血管の外に漏れやすくなるため、局所の腫れを生じます(腫脹、Schwollung)。さらに神経に働いて痒み(Juckreiz)、痛み(Schmerz)を生じます。じんましん(Nesselsucht)はその典型例です。
花粉症に効く抗ヒスタミン薬
ヒスタミンは、ヒスタミン受容体(Rezeptor)と呼ばれる受け皿を介して作用します。そのため花粉症やアレルギー疾患にはヒスタミン受容体拮抗薬(抗ヒスタミン、Cetirizin、Levocetirizn、Fexofenadinなど)が用いられます。一方、抗ヒスタミン薬には「鎮静作用」もあるため、眠くなるという副作用があります。
ヒスタミンによる食中毒(Histamin-Lebensmittelvergiftung)
ヒスタミン食中毒とは?
生魚や保存食品、発酵食品、熟成食品に含まれるヒスタミン産生菌(魚肉を汚染する海洋微生物)によって作られるヒスタミンが原因で起きる食中毒です。日本での集団発生による患者数は年間100~200人程度で(令和3年の内閣府食品安全委員会ファクトシート[ヒスタミン])、軽症の孤発例も含めると実際はもっと多いと推測されます。
ヒスタミンを分解するDAO酵素
食品から入ったヒスタミンは、小腸にある酵素(DAO酵素、Diaminoxidase)によって分解、不活化されます。この処理能力を超える量のヒスタミンが体内に入ったときに生じるのが、ヒスタミン食中毒です。
加熱で減らないヒスタミン
食品中で一度作られたヒスタミンは加熱しても壊れません。ヒスタミン産生菌は冷凍中は活動しませんが、解凍すると再び産生が始まり(常温に近いほど増えやすい)、ヒスタミンは食品中に蓄積されます(大日本水産会の「ヒスタミン食中毒防止マニュアル」)。
日本で原因となる食品
鮮度の落ちた魚(特にマグロ、カジキ、ブリ、サンマ、サバ、イワシなどの赤身の魚の身の部分)や、内蔵を抜かない魚の丸干しなどの加工食品が原因になります(農林水産省の有害化学物質含有実態調査結果データ集[平成27~28年度])。ヒスタミンが含まれているかもしれないドイツ食品生魚のほか、魚の薫製や塩漬け、缶詰、ソーセージ、サラミ、ザワークラウト、トマト、赤ワイン、ヴァイツェンビール、長期熟成のチーズ(パルメザン、熟成ゴーダ、エメンタール、ブルーチーズ)にもヒスタミンが含まれていることがあります(2006年のPharmazeutischeZeitung紙)。食物アレルギーと似たさまざまな症状食べてから数分後、多くは1時間以内に、ほてり、頭痛、じんましん、痒み、吐き気、おう吐、腹痛、動悸、めまい、疲労感などの症状が一つ以上みられます(2006年の日本食品微生物学会雑誌、2019年のEuro Survell誌、2020年のBiomolecule誌)。通常は数時間以内に回復し、人から人への感染はありません。
ヒスタミン量が発症を左右
一般にヒスタミンの濃度が100mg/100g以上の食品の摂取で発症するとされていますが、実際には摂取量が問題です(2009年の国立衛研報、前記の食品安全委員会ファクトシート)。ヒスタミン不耐症(後述)では、10~100mg/100g未満でも食中毒を起こす可能性があると推定されています。
ヒスタミン不耐症(Histaminintoleranz、HIT)
体内のDAO酵素の作用不足
ヒスタミンを分解するDAO酵素が少ないことやその作用不足が原因で、体内に入ったヒスタミンをうまく分解できずさまざまな症状を呈します。そのため、食品中のヒスタミンが少量でもヒスタミン食中毒と同じような症状を呈します(2015年のAllergol Immunopathol[Madr]誌、2020年のBiomolecule誌)。
ヒスタミン不耐症の頻度は?
約1%(2007年のAm J Clin Nutr誌)あるいは累積頻度が3~6%(2011年のJ Allergy Clin Immunol誌、2022年のNutrients誌)と報告されています。
一次性(遺伝性)と二次性DAO欠乏症
遺伝子の配列変異(遺伝子多型)によりヒスタミンを代謝するDAO酵素の活性が著しく低下している場合を一次性と呼び、アルコール、薬、病気の影響でDAO酵素の作用が低下しているものを二次性と呼んでいます。後者がほとんどを占めます。
不耐症を促す可能性のある食品、薬剤
①細胞からのヒスタミン放出を促す食品(卵白、魚、イチゴ、アルコールなど)、②ヒスタミンよりDAO酵素への親和性が強くDAO酵素を消費してしまう生体アミンを含む食品(バナナ、クルミ、チョコレートなど)、③ヒスタミン代謝に影響する薬剤(抗うつ薬、解熱鎮痛薬)も、ヒスタミン不耐症のリスク因子となり得ます。
診断方法は?
血中のDAO活性を直接測定(公的保険の適応外)して、値が低ければ強く疑われます。繰り返し同じような症状が出る人は、1カ月ほどリスク因子となる食品を避け、症状がなくなるかどうかを確かめる方法も。またヒスタミン代謝を促すDAO酵素製剤(DaosinⓇなど)を服用して、その効果をみることもできます。
ヒスタミン食中毒・不耐症を防ぐために
赤身魚での注意
①常温で放置しない、②冷蔵庫内でも長期保存は避ける、③解凍はできるだけ低温(例えば冷蔵庫内)で、④解凍・冷凍を繰り返さないことが大切です(大日本水産会の「ヒスタミン食中毒防止マニュアル」)。
加熱は意味ないことを念頭に
食品中のヒスタミンは加熱調理しても減ることはありません。前日の残りの刺身を加熱すれば大丈夫と考えるのは正しくありません。
長期熟成のチーズにも留意を
熟成期間が6カ月以上のチーズは避け、食する場合は、保存期間が短いチーズ(クリームチーズ、カッテージチーズ、若いゴーダチーズなど)が無難です。
アルコールは?
一般的にアルコールは腸管からのヒスタミンの吸収を高めるため、ヒスタミン不耐症の場合は、アルコールの摂取を制限することが推奨されています。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック