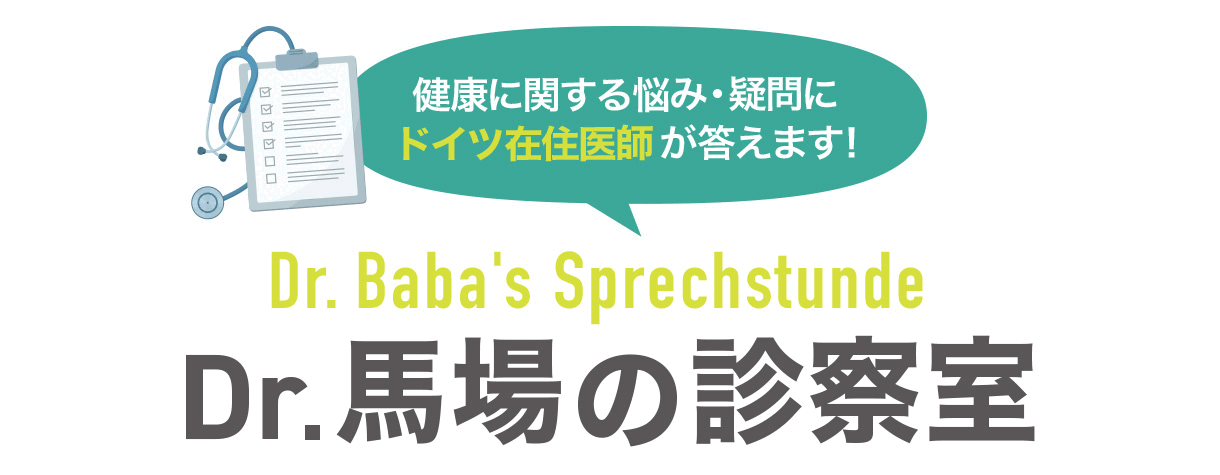アジアに海外駐在中の友人から、赴任地で適応障害と診断されたと聞きました。適応障害とはどのような状態を指すのでしょうか?日本の仕事を辞めてドイツに来た自分の配偶者(妻)も、当地の生活になじめずに最近元気がないようにみえます。予防法や治療法があったら教えてください。
Point
- 海外では家族のメンタルケアが大切
- 配偶者に多いこころの不調
- 言葉、異文化、周囲環境がストレスに
- 全てを失った感じの孤独感
- 早めの対応が基本
- 一人で悩まず相談を
- 家庭中心での思考が大切
適応障害とは
適応障害(Anpassungsstörung)の概念
周囲とのあつれきや環境要因によって陥るうつ的な状態です。日常生活の中で自分が置かれた環境や状況に適応するのが耐え難いほどつらく感じ、不安や抑うつ気分が強く、普段の生活を送れないほどの支障を生じる状態をいいます(2013年発表の米国精神医学会の「精神障害の診断と統計マニュアル第5版[DSM- 5]」、2014年の日本精神神経学会の同日本語訳)。
どんな症状?
自分はどうしてドイツにいるのだろうという存在意義への疑問、毎日がつらくふとしたことで涙が出る、生活が楽しくない、何となく押し寄せる不安感、抑うつ的な気分、あせり、怒りなどのメンタル面の症状に加え、めまい、動機、疲労感などの身体的な症状がみられることがあります。
うつ病(Depression)との違い
適応障害の場合、①発症のきっかけとなる引き金の出来事があること、②そのストレス状態に置かれてから比較的すぐに発症し、③原因となるストレスからの解放ですぐに症状がよくなります。また、④落ち込んだ状態でも楽しいことがあれば楽しむことができるのが特徴です(うつ病については本誌1187号)。一方、適応障害からうつ病へ移行することもあります。
孤独感の背景
現在の孤独感に影響を与えたと思う出来事について、最も多いのが「言語上のもの」、次いで「文化的違いに起因するもの」となっています(2024年公開の外務省「海外における邦人の孤独・孤立に関する実態把握のための調査」結果)。海外生活では、①言葉が通じない、②生活習慣やルールが違う、③周囲に解け込めない孤独感など、生活環境の大きな変化が関わっています。日本で築き上げた周囲とのネットワークや社会生活が海外に暮らしてみて失われたと感じます(2021年、在英国日本国大使館)。
海外駐在経験者のこころの不調
海外駐在経験者を対象とした2005年の旧JOHAC(海外勤務健康管理センター)の調査、2011年の産業能率大学の調査によると、海外赴任中にストレスを感じた人はいずれの調査でも約6割と高くなっています(2016年の広島修大論集)。外務省2022年海外邦人援護統計 (2024年発表)によると、欧州地域での邦人全死亡68人のうち1位が病気の38%、2位が自殺の12%で、病気やメンタルヘルス対策が重要であることが示されています。
帯同配偶者の適応障害
多くの人が経験するこころの不調
駐妻キャリア総合研究所の調査によると、配偶者のメンタル不調は海外生活が始まって1~6カ月の頃が多いとされています(駐妻キャリアnet )。永住者も対象に含めた外務省の「海外における邦人の孤独・孤立に関する実態把握のための調査」(2024年に結果公開)によると、海外に暮らす女性全体の10.6%が「常に孤独(Einsamkeit、Allein)」を感じ、なかでも収入を伴う仕事をしていない(探している)層が20.4%と最も高いことが示されました。
配偶者の居場所は?
海外駐在員の大半(81%)が男性(2023年のJAC リクルートメントの調査)で、帯同配偶者は女性という現状において、駐在員(多くは夫)にとっての会社、子どもにとっての学校に相当する居場所が配偶者(多くは妻)には用意されていません(2016年の広島修大論集)。そのため配偶者にとって、社会との関わりが非常に限られた海外生活スタートとなります。
日本でのキャリアの中断
海外勤務に伴い退職した配偶者は45.2%にも上ります(2023年に行われた「駐妻ファミリーカフェ」による調査)。キャリアが中断されるだけではなく、今まであった社会との接点が急に減り、生活のリズムも大きく変わることになります。ドイツで仕事をしたくとも、夫の勤務先の許可が得られないことも少なくありません。
配偶者への配慮
駐在者(夫)自身も仕事や新しい環境への適応に精一杯で、配偶者のこころにまで気が回らずに放置されたままになってしまうことも少なくありません(2021年、在英国日本国大使館)。子どものいる家庭では休むことなく一人で育児と家事を担ったり、夫婦二人だけの家庭では家族以外とは話をする機会がなかったりという状況も、適応障害の要因になりうるといえます。
駐在者(夫)の多忙、不在
夫の帰宅は遅く、週末も本社とのメール交信、なかには月の半分近くは出張で一人暮らしになってしまう配偶者も。自身が海外生活を望んだわけではない場合、「自分はなぜドイツにいるのだろう」という疑問を持つことになります。
駐在員の会社関係の付き合い
会社の同僚同士の駐在員コミュニティーにおいて楽しさはあるものの、時として付き合いがストレスと感じる人もいます。夫(妻)の会社を中心とした狭い範囲の人間関係、上下関係が配偶者にまで及んで、気疲れの原因になってしまうことも。
対応の工夫
不調が生じたらまずは相談を
適応障害が疑われるこころの不調を自覚したら、一人で抱え込まず、まずは抱えている問題を誰かに相談しましょう。外務省の「海外における邦人の孤独・孤立に関する実態把握のための調査」によると、不安や悩みを「相談することで解決しなくとも気持ちが楽になる」 と回答した人の割合が 73.9%と最も高く、次に「相談することで解決できる、または解決の手がかりが得られる」(55.5%)ことが示されています。
夫婦で話し合ってみる
「自分は何のためにドイツにいるのだろう」と悩むようになったら、正直に話し合ってみることが大切です。駐在者(夫)の自分は忙しいから愚痴を聞いている暇はない、自分だって苦労しているから我慢して頑張ってという態度は、必ずしも解決につながりません。
臨床心理士に相談してみる
数は限られていますが、ドイツでの資格を有する日本語を話す臨床心理士に相談することもできます。また私費扱いになりますが、最近は日本にいる臨床心理士とオンライン相談をするという選択肢も。掛かりつけの医師に紹介の助言をもらうこともできます。
「頑張らなければダメ」とは思わない
異国の地で育児と家事に追われ、孤独に陥っている場合、我慢して頑張ろうと無理を続けるのはよくありません。言葉が通じない異文化の中で、最初から現地人のように完璧にできることは無理です。むしろ開き直って、いわば赤ちゃんになったつもりで、ドイツのさまざまなことに興味を持ってトライしてみるのも一手です。
旅行、一時帰国、本帰国も選択肢
ドイツ国外への旅行や一時帰国も、症状を改善するための選択肢です。ドイツに暮らすのが本当につらい時は、本帰国も検討してみましょう。



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック