
西ヨーロッパ市民の間で、経済グローバル化に対する不信感は依然として根強い。彼らはグローバル化によって生産拠点が、労働コストの低い中東欧やアジアに移転され、雇用が脅かされると思っている。今年になって米英のヘッジファンドやプライベート・エクイティーなどの投資会社が欧州で活発に企業買収を行っている。「イナゴ」や「ハゲタカ」と呼ばれる投資ファンドによって伝統的な企業が買収されたり、解体されたりするのではないかと不安を抱いている人も少なくない。フランスとオランダの市民が数年前に欧州憲法に関する国民投票 で「ノー」と言ったことも、彼らがこの憲法をグローバル化の象徴と見なしたからである。
グローバル化によって、先進国とアフリカやアジアの貧しい国々との間の格差が一層拡大することに懸念を抱く人もいる。「市場の見えざる手」や自由競争を信奉するアングロサクソン型の資本主義社会は競争に負けた敗者には無慈悲であり、勝ち組には気が遠くなるような報酬を準備する。だがこの弱肉強食のシステムは、戦後西ドイツ社会の基本原理である「社会的市場経済(Soziale Marktwirtschaft)」の原理とは相容れない。ドイツ人たちは純粋に競争原理だけに従うのではなく、政府が競争の枠組みを規定し、敗者に対しては社会保障など最低限の安全ネットを準備するシステムを採用した。この考え方はキリスト教の影響が強く、秩序を好むドイツ人のメンタリティーに合っていた。
それだけにジャングルの掟が支配するような、グローバル資本主義に反感を持つドイツ人は少なくない。キリスト教民主同盟(CDU)の元幹事長ハイナー・ガイスラー氏が、サミット直前にグローバル化に反対する団体「アタック」に加わったことは、そのことを象徴している。メルケル首相が地球温暖化に歯止めをかけるための二酸化炭素排出削減策という、発展途上国にとっても重要な問題を議題の一つにしたことも、公共の利益を重視するよう米国に求めるメッセージだった。
G8直前にロストックで一部のデモ隊が警察官と衝突し、双方に1000人近いけが人が出たことは残念である。この事件で非暴力的な手段によってサミットに抗議しようとしていた市民団体のメッセージがかき消されてしまったからだ。庶民にはまず泊まれない、超高級ホテル「ハイリゲンダム・ケンピンスキー」でベルリンの壁を思わせるフェンスと鉄条網に囲まれ、美しい大海原を見ながら国際経済を語る各国首脳たち。メルケル首相の努力にも関わらず、グローバル化の勝ち組と反対勢力の間の溝が埋められたとは思えない。
15 Juni 2007 Nr. 667



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック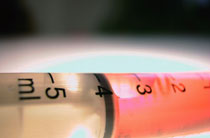 ドイツにお住まいの皆さんならご存知のように、この国の人々は自転車に乗るのが大好きである。自転車道や標識が整備されたドイツでは、サイクリングは誰もが手軽に楽しめる、素晴らしいスポーツである。春や夏には、大都市郊外のサイクリングコースは家族連れでにぎわう。テレビで中継される自転車競技に対する市民の関心も高い。
ドイツにお住まいの皆さんならご存知のように、この国の人々は自転車に乗るのが大好きである。自転車道や標識が整備されたドイツでは、サイクリングは誰もが手軽に楽しめる、素晴らしいスポーツである。春や夏には、大都市郊外のサイクリングコースは家族連れでにぎわう。テレビで中継される自転車競技に対する市民の関心も高い。 5月23日、ケルン・ヴァーン空港。3人のドイツ連邦軍兵士たちが、棺に納められて無言の帰国をした。アフガニスタンのクゥンドゥスの市場で自爆テロに遭い、殺害された男たちである。犯人は不明だが、イスラム原理主義勢力タリバンが犯 行声明を出している。
5月23日、ケルン・ヴァーン空港。3人のドイツ連邦軍兵士たちが、棺に納められて無言の帰国をした。アフガニスタンのクゥンドゥスの市場で自爆テロに遭い、殺害された男たちである。犯人は不明だが、イスラム原理主義勢力タリバンが犯 行声明を出している。 最近、メルケル政権の経済担当閣僚の表情が明るい。その最大の理由は、景気回復によって企業収益が大幅に改善し、国の金庫に入る税収が飛躍的に増えたことである。シュタインブリュック財務相は、今年度の歳入が、昨年11月の予想を202億ユーロも上回るという見通しを明らかにして、政財界を驚かせた。さらに同相は、「2011年には財政赤字ゼロ、つまり財政均衡を実現する」という大胆な予測すら打ち出している。
最近、メルケル政権の経済担当閣僚の表情が明るい。その最大の理由は、景気回復によって企業収益が大幅に改善し、国の金庫に入る税収が飛躍的に増えたことである。シュタインブリュック財務相は、今年度の歳入が、昨年11月の予想を202億ユーロも上回るという見通しを明らかにして、政財界を驚かせた。さらに同相は、「2011年には財政赤字ゼロ、つまり財政均衡を実現する」という大胆な予測すら打ち出している。






