Nr. 10 大家さんはこんなところを見ている!
 ドイツ語圏の4月は大掃除の季節。ドイツの主婦が一生懸命に家を磨きたてる季節です。ご近所の方々を見ているだけでプレッシャーを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ドイツ語圏の4月は大掃除の季節。ドイツの主婦が一生懸命に家を磨きたてる季節です。ご近所の方々を見ているだけでプレッシャーを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回のテーマは、ドイツ人の大家さんを安心させるコツ。日本と同じで、法律で間借り人が大変保護されているドイツです。常識のない人に家を貸してしまっても、大家側としてはなかなか出ていってもらう手立てがありません。大きな会社ではなく、例えば老後の生活費の足しに、といった感じで個人的に持ち家を貸している人の中には、ついつい心配になって覗きにいっては、うるさいことを言ってしまう人も多いようです。
うるさい大家さんに出会ったとしても、ほとんどの場合は資産の価値低下を恐れているだけ。西洋家屋のメンテナンスの常識さえ少し知っていれば、回避できるトラブルも多いと思います。
まず大切なことですが、大家さんには、いくら自分が所有しているといっても一度人に貸した家の中に勝手に入っていく権利はありません。人に貸している家の中をチェックしたいときは、必ず事前に住人の許可を得て日時を決めることになっています。留守中、勝手に侵入することが許されるのは、火事やガス漏れ、あるいは犯罪や事故などの緊急事態が発生している恐れのあるときだけ。時々、人の留守中に黙って合鍵を使って入ってしまう大家さんの話を聞くことがありますが、これは「不法侵入(Hausfriedensbruch)」として抗議すべきことです。
ともあれ常識的な大家さんならば、まずは外側からいろいろと眺め、気を揉むだけでしょう。国籍、男女を問わず借り手として次のような点に初めから気をつけていれば、多くのトラブルが避けられると思います。
まず家賃はできる限り、月初めの第3営業日までに自動送金(Dauerauftrag)されるように手配しておく。メンテナンス意欲があるところを早めにアピールする。場合によっては契約を結ぶ前から他の住人との共有空間である階段、玄関、廊下、物干し場などの掃除やごみ出し日のルールを聞いておく。仕事が忙しいから自分では掃除ができないと思ったら、人を雇うことにするか、あらかじめ掃除サービスがついている家に入る。
窓の状態は、家の中に入ってメンテナンス状態を確認できない大家さんにとって大きなポイントになっています。窓ガラスは少なくとも1カ月に1度くらいの間隔できれいに磨いておく。そのときは、外側の窓の桟なども一緒に洗っておくとよいでしょう。都会ならば、周りには窓ガラスをあまり気にしない人も多いかと思いますが、地方都市や閑静な住宅街では、ある程度近所のリズムを参考にすること。フランスやイタリアなどとも違って、窓ガラスの向こうに見えるカーテンも、すそに鉛のおもりを入れてひだがきっちり、まっすぐ下りるようになっていたり、ひだのひとつひとつを待ち針や専用のピンでとめている人もあるくらいですから、外側からカーテンがよれていたりするのが見えると、特に年配の大家さんはアラーム状態になる危険がありますので注意しましょう。
たまたま大家さんが何かの用で家の中に入ってきたり、あるいは自分が家を出る時点で文句を言われたとしても遅いのは、洗面所、トイレ、シャワーなど水周りのカルキ汚れ。ドイツの水は硬質ですので、きれいに水で洗っていてもすぐに外見が汚くなります。そこで対策ですが、洗面台は使った後で専用の古タオルなどでからぶきしておけばいいでしょう。そして1週間に1度くらいは洗剤液にお酢を加えてきれいにします。お手洗いも、定期的に酸性洗剤でそうじをすることをお勧めします。シャワー室内の壁のタイルも、金属の取っ手、蛇口、水道船なども1週間に1度程度は酸性の洗剤で洗った後、からぶきをしておかないと、数カ月もしないうちに、1回や2回の掃除では取れないような石灰の膜がこびりついてしまいます。水できれいに流した後、まめに水滴を布でふきとっておかないと、傷をつけずに石灰を取ることができなくなってしまうのでやっかいです。(ただし、大理石に酸性洗剤は厳禁です)
それからフローリングをしている床の傷。板敷きは頑丈、などと思って乱暴に扱わないでください。とてもデリケートな材質です。これに傷がつくと、次の人に貸しにくくなったり、家賃のレベルに大きな影響が出ます。戦前などの古いパーケット板であれば、表面を削ることもできますが、新しいものは薄いので、全部張り替えなくてはならなかったり、修復にはかなり費用がかかります。ですから、ドイツでは椅子や家具を動かすときなどには絶対にひきずらないように気を遣うものです。椅子を動かすことの多い食卓や書斎の机の下には、じゅうたんを敷くなどして工夫をしたり、細いヒールのハイヒールでは歩かない人が多いのです。昔はフェルトの上履きを靴の上に履いたものでした。また水にも弱いので、何かをこぼしたら、すぐにふき取るようにします。
留守中の郵便受け。これは留守中に郵便物や新聞などがあふれないようにしなくてはいけません。あふれている状態を放置すると、泥棒をおびき寄せますので、集合住宅では、みんなで注意しあっているところも多いはずです。手配をしないで家を空けると、泥棒を恐れた建物の他の住人がはみ出ている郵便物を勝手に抜き取っていた、などということにもなりかねません。数日出かけるような場合には、事前にご近所とコミュニケーションをはかり、信頼できる人に郵便受けの鍵を預けるようにすればいいでしょう。
庭つきの家を借りた人は、芝刈り、生垣の手入れなど、まめにやっておくこと。手入れが悪いと、景観を損ねたという理由から、隣近所の家賃にまで影響が出る危険があります。逆に庭でよく働いていれば、いかにも働き者に見えて、周りの信頼を集めることは確実です。
大家さんも安心できれば、そううるさく言ってこないはず。感じのよい相手なら、クリスマスなどにはグリーティングカードを出せば喜ばれます。信頼第一。大掃除の季節、みなさん、がんばりましょうね!
|
|||||



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック “Wie wird hier das Treppenhaus geputzt?”
“Wie wird hier das Treppenhaus geputzt?” どこの国にいっても敬語や丁寧語の類は使い方が難しいものですが、ドイツではDuとSieの使いわけに気を遣われる方もいるでしょう。いろいろな本には、日本語で「ですます調」以上の敬語を使う相手ならばSie、それよりも親しい間柄であればDu、とありますが、実際の生活ではいったいどうやって使えばよいのでしょうか。ドイツでも、最近は英米や北欧諸国の影響で、次第にDuとSieの使い分けのルールがあいまいになってきていますが、基本的にはまだまだいろいろな決まりがあります。
どこの国にいっても敬語や丁寧語の類は使い方が難しいものですが、ドイツではDuとSieの使いわけに気を遣われる方もいるでしょう。いろいろな本には、日本語で「ですます調」以上の敬語を使う相手ならばSie、それよりも親しい間柄であればDu、とありますが、実際の生活ではいったいどうやって使えばよいのでしょうか。ドイツでも、最近は英米や北欧諸国の影響で、次第にDuとSieの使い分けのルールがあいまいになってきていますが、基本的にはまだまだいろいろな決まりがあります。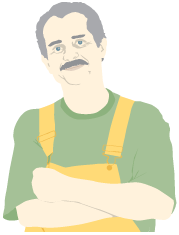 ドイツの貸家に住んだことのある方なら、賃貸契約書にも書いてあるのでご存知のことと思いますが、「家の手入れ」はドイツ語圏では非常に重視されている事項です。
ドイツの貸家に住んだことのある方なら、賃貸契約書にも書いてあるのでご存知のことと思いますが、「家の手入れ」はドイツ語圏では非常に重視されている事項です。 新しい年になって「今年こそはドイツ人との親睦を深めよう」と決意を新たにされた方も多いかと思います。
新しい年になって「今年こそはドイツ人との親睦を深めよう」と決意を新たにされた方も多いかと思います。 12月に入り、日本ではお歳暮の季節になりましたが、クリスマスの近づくドイツでの贈り物の作法に頭を痛めている方もあるのではないかと思います。そこで、前々回の「お礼」の章とも少し重なるテーマではありますが、今回は、クリスマスシーズンの贈り物をめぐるドイツでの慣習を、詳しく取り上げることにしましょう。
12月に入り、日本ではお歳暮の季節になりましたが、クリスマスの近づくドイツでの贈り物の作法に頭を痛めている方もあるのではないかと思います。そこで、前々回の「お礼」の章とも少し重なるテーマではありますが、今回は、クリスマスシーズンの贈り物をめぐるドイツでの慣習を、詳しく取り上げることにしましょう。





