終戦80周年記念特集
犠牲者としてのドイツの歴史
「追放」はどう語られてきたか?
 ポーランドのヴロツワフ西部を歩いて移動する被追放者たちの列(1945年撮影)
ポーランドのヴロツワフ西部を歩いて移動する被追放者たちの列(1945年撮影)
ドイツおよび欧州が第二次世界大戦の終わりを迎えた1945年5月8日から、今年で80周年を迎える。ドイツでは、ホロコーストをはじめ加害者としての歴史に触れる機会は多い一方で、犠牲者としての歴史を知る機会は少ない。本特集では、あまり知られてこなかった歴史の一つ「追放」に焦点を当てることにした。タブー視されていた時期もあったこの歴史が、どのように語り継がれてきたのかを探る。 (文:ドイツニュースダイジェスト編集部)
佐藤成基「ドイツ人の『追放』,日本人の『引揚げ』—その戦後における語られ方をめぐって—」、bpb.de「Kollektive Erinnerung im Wandel」、NDR「Flucht und Vertreibung überschatten 1945 das Kriegsende」、NHK映像の世紀バタフライエフェクト「ふたつの敗戦国 ドイツ さまよえる人々」
取材協力・監修
佐藤成基さん Shigeki Sato
法政大学社会学部教授。ナショナリズムと国家についての理論と歴史の研究に従事する。著書に『ナショナル・アイデンティティと領
土ー戦後ドイツの東方国境をめぐる論争』(新曜社)、『国家の社会学』(青弓社)、『国民とは誰のことかードイツ近現代における国籍法の形成と展開』(花伝社)などがある。
www.t.hosei.ac.jp/~ssbasis
1400万人が故郷を追われた「追放」
第二次世界大戦の敗戦で、ドイツは戦前の領土の4分の1に相当する東方領土(オーデル・ナイセ線以東の領土)を失った。これには、米国・英国・ソ連の首脳が1945年のポツダム会談で、ソ連とポーランド、ポーランドとドイツの国境をそれぞれ西へと移動させることを決めたという背景がある。それに伴い、ソ連とポーランドのみならず、チェコスロヴァキア(当時)、ハンガリー、ルーマニア、ユーゴスラヴィアなどに住んでいたドイツ人が故郷から追放されることになる。追放の対象となったのはドイツ国籍を持つ者はもちろん、民族的にドイツ人とされる人々も含まれていた。なかには、12世紀頃から東欧に定住していたドイツ系民族もいたという。

1944年秋、ソ連軍がすでに到達していた地域では、ドイツ人の避難が始まっていた。家を追われ、財産を没収された人々は、持てるだけの荷物を持って、徒歩や列車で西を目指した。その途上では、寒さや飢えで病気や栄養失調となって命を落とした者がいれば、バルト海上で移送船がソ連軍の魚雷によって撃沈されたり、爆撃などの戦闘に巻き込まれたりして犠牲となった者もいた。さらにドイツ人への報復として、解放された強制収容所に今度はドイツ人が収容されるなど、民間人による暴力や虐殺もあった。こうした非人道的なドイツ人の追放は1945年の終戦後も続いた。
「ドイツ人の秩序ある移送」と呼ばれる組織的な追放は1946年1月から行われた。ホロコーストの移送で使われた貨物列車にドイツ人が隙間なく詰め込まれ、劣悪な環境のなかドイツへ向かったという証言も残されている。最終的には1944~1950年の間に1200万~1400万人のドイツ人が東方からドイツへと追放され、そのうち60万~100万人、あるいはそれ以上が命を落としたといわれている(連邦政治教育センター参考)。
 1945年10月、ベルリンのアンハルター駅で電車を待つ被追放者たち
1945年10月、ベルリンのアンハルター駅で電車を待つ被追放者たち
ドイツの「追放」と日本の「引揚げ」
「追放」はドイツ語で「Vertreibung」といい、強制移住させられた人々を「被追放者」(Vertriebene)と呼ぶ。日本でも敗戦に伴い外地で生活していた人々が日本へと帰る「引揚げ」があったが、その意味は大きく違う。そもそも「引揚げ」は「もとにいた場所に戻る」ことを意味し、被強制性が含意されていない。一方で「追放」は「故郷から強制的に追放された」ことを意味し、明らかな被強制性が示唆されている。
東西ドイツで違った「追放」の扱い
追放がほぼ終了した1950年時点では、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)に約800万人、ドイツ民主共和国(東ドイツ)に約400万人の被追放者が流入していた。西ドイツでは総人口の約16%、東ドイツでは約25%に当たる数である。そもそも戦争で街が破壊され、さらに東西に分断されたドイツにとって、被追放者を受け入れることは大きな負担となった。西ドイツでは被追放者は人口比で偏りが生じないよう各州に振り分けられ、東西それぞれの形で社会に統合されていくことになるが、「追放」の扱われ方は東西で大きく異なっていた(詳しくは下記)。
東西で被追放者の扱われ方に違いはあるが、いずれの場合も表面上の統合にすぎず、実際には故郷を奪われた喪失感、差別や賃金格差などに苦しんだ人が少なくなかった。西ドイツにおける1949年の調査では、被追放者の82%が故郷に帰ることを望んでおり、1959年時点でも57%が帰還を望んでいたという。
西ドイツ
- 戦後直後から1960年代まで、追放は非人道的で国際法に反する「不正」と認識され、敗戦により東方領土を奪われたことは「不当」と訴えていた
- 基本法で、1937年の段階で「ドイツ帝国」の範囲でドイツ国籍を持つ人々、ドイツ国籍を持たない民族的にドイツ人とされた人を、配偶者・子孫を含めて「ドイツ人」と規定した。なお1950年以降の被追放者は「アウスジードラー」(Aussiedler)と呼ばれ、現在も民族的にドイツ人と認められれば、一定の条件のもとドイツ国籍を取得することができる
- 戦争被害の損失を国民全体で負担することを目指した「負担均衡法」(1952年制定)により、被追放者たちも援助の対象となった(ただし、償還された財産は2割程度)
- 1950年に「故郷被追放者・権利被はく奪者のブロック」(BHE)という政党も結成され、一時期は連邦議会に27議席を持っていた
- 1957年には「被追放者連盟」(BdV)が創設され、内政・外交両面で政党や行政に影響力を行使した
東ドイツ
- 東方からの避難民を「移住者」(Umsiedler)と呼んだ
- ソ連の同盟国として東欧の社会主義諸国と友好な関係を維持するため、西ドイツのように不正の告発を行おうとしなかった
- 地主から没収した農地を東方からの移住者にも配分することで、新生の社会主義国家に「新市民」(Neubürger)として同化させようとした
- 1950年の時点で400万人が東ドイツに流入したが、ベルリンの壁建設前にその多くが西ドイツに移住したといわれている
タブー化された「追放」の歴史が認められるまで
東ドイツでは「追放」について公式に言及してこなかったため、ここでは西ドイツの歴史を振り返る。戦後の西ドイツでは「難民・被追放者・戦争被害者省」を設置し、1969年まで被追放者の受け入れを担ったほか、追放の当事者の体験談や目撃談を700以上収めた公式記録(全5巻8冊)の制作も行っている。一方で追放に関する言論は反共主義と強く共鳴し、西ドイツの国是であった「再統一」には被追放者の故郷回復の意味も込められていた。
ところが、1968年にブラント政権が成立し、東欧社会主義諸国との融和を目指す「新東方政策」が開始されたことが、被追放者にとって逆風となった。当時、ナチスの罪を自覚することが「和解と平和」に貢献するとした公共的規範が西ドイツに根付いていった。その結果、追放を公然と語ることが難しくなり、タブー化されていったのである。追放の不正について語ることは、東方政策を妨害し、報復主義や歴史修正主義であるとみなされるようになった。被追放者団体やその支援者たちは追放の不正を訴え続けたが、そうした発言は批判され、ネオナチのレッテルさえも貼られたという。
転機が訪れたのは、1990年の東西ドイツの再統一だった。それまで未解決だったドイツとポーランドの国境が確定し、ドイツは東方領土への要求を正式に放棄。領土問題から解放され、追放の歴史を公然と語りやすくなる状況が生まれた。2000年代に入ると、追放の歴史に関連するドキュメンタリー放送、書籍の出版、展示などが相次ぎ、「追放のルネッサンス」のようなブームが訪れる。2005年にボンの歴史の家で開催された展示「避難・追放・統合」は、非難する声もあったものの、その後ベルリンとライプツィヒを巡回するほど注目された。こうして公共でのプレゼンスが高まるにつれ、追放はドイツ史の一部と認識されるようになったのである。
追放を描いた小説『蟹の横歩き』
ドイツを代表する作家であり、ノーベル文学賞受賞者のギュンター・グラスの『蟹の横歩き』は、1945年1月に大勢の被追放者を載せた豪華客船ヴィルヘルム・グストロフ号がソ連の攻撃で沈没した実際の事故を題材とする小説。グラス自身もダンツィヒ(現ポーランドのグダニスク)出身の被追放者として知られ、「追放」ブームが始まった2002年に出版された。翌年には日本語訳も出版されている(現在は絶版)。
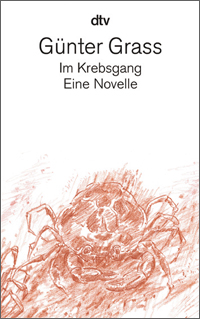 Im Krebsgang
Im Krebsgang(蟹の横歩き)
Günter Grass
発行元:dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
定価:13ユーロ
「追放」をめぐる今とこれから
1998年に被追放者連盟の会長に就任したエリカ・シュタインバッハ氏は、追放の問題を国民的なテーマへと復権させることを目指す取り組みを始めた。追放の歴史を語ることは、ナチスの犯罪やドイツ人の責任を相対化するものだという批判もあったが、同氏はこの歴史を加害の歴史と同時に語っていくスタンスを取り、前述の「追放」ブームを後押しした。一方で、シュタインバッハ氏は長らくキリスト教民主同盟(CDU)の議員だったが、右翼的な発言をすることでも知られていた。2017年にはメルケル元首相の難民政策に失望して、CDUを離党。さらに現在は、極右政党「ドイツのための選択肢」(AfD)の党員となって活動している。かつて被追放者は領土問題の流れから、右翼を支持する人が多かったという背景がある。被追放者やその子孫がAfDに共感を示す例もあり、記憶文化や政治的アイデンティティーをめぐる議論のなかで、慎重に扱われるべきテーマの一つである。
また、現在の被追放者連盟にとって、政治的主張とは距離を置く形で追放の歴史や文化をどう記録していくかは、大きなテーマだ。その取り組みの一つとして、追放の歴史や連盟の活動を紹介する機関誌の隔月発行を続けている。しかし、その機関誌では、例えば2015年の難民危機には一切触れられていない。被追放者と難民とでは置かれた状況や歴史的背景が大きく異なるとはいえ、こうした出来事を完全に切り離して扱う姿勢は一面的にも映る。連盟がこうした現代的な問題にどのようにアプローチしていくのか、今後も注目していくべきだろう。
さらに2021年、ベルリンに「避難・追放・和解資料センター」がオープンした。もともとはシュタインバッハ氏の構想からスタートし、2005年に首相に就任したメルケル氏も、就任演説で「ベルリンに追放の不正を記憶する目に見える目印を置く」ことに賛意を表明、2008年の連邦議会で承認を経て創設されることが決まった。実に10年以上の歳月がかかったが、最終的には「ナチズムと第二次世界大戦の結果としての『追放』」という視点を持った場所として開館が実現した。
今年2月、ロシアがウクライナに侵攻してから3年が経過したが、和平交渉が進もうとしている。交渉の末、もしロシア系住民が多く暮らすウクライナ東部がロシアの領土になった場合、そこに住むウクライナ人たちが追放される可能性もある。かつてのドイツ人の追放と類似した状況が、再び現実になるかもしれないのだ。こうした可能性を前に、ドイツが語り継いできた「追放」の歴史は、今後どのように生かされるのだろうか。21世紀になっても世界各地で戦争が起きている今、あらためて「追放」を学び、考えるべきときが来ているのかもしれない。
避難・追放・和解資料センター
Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung
20~21世紀における避難・追放・強制移住をテーマにする資料センター。かつて被追放者たちがたどり着いたアンハルター駅近くに位置する。展示室のほか、当事者の声をアーカイブした図書室があり、ツアーやワークショップなども。入場無料。
Stresemannstr. 90, 10963 Berlin
www.flucht-vertreibung-versoehnung.de




 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック







