Guten Tag? Servus? Moin? 多様性が見えるドイツの方言
ドイツでは、いわゆる高地ドイツ語が標準語として使用されている。しかし、特に話し言葉は地域によって大きな違いがあり、生粋のドイツ人同士だとしても、生まれ育った場所が違えば、お互いに何を言っているのか分からないということさえ起きる。本特集では、そんなドイツの「方言」にフォーカス。多様な地域性が育んだドイツ方言の歴史から、失われつつある方言の未来まで、味わい深いドイツの方言の世界へとご案内しよう。 (文:ドイツニュースダイジェスト編集部)
方言をめぐるドイツ語の歴史
そもそもドイツ語は、紀元前1000年頃のゲルマン祖語から生まれた。その後ゲルマン語は、紀元600~800年の間に子音の大きな変化(いわゆる「第二次子音推移」)が起こり、その影響を受けた中南部の高地ドイツ語(Hochdeutsch)と、影響を受けなかった北部の低地ドイツ語(Niederdeutsch)に分割される。子音推移の影響を受けた古高ドイツ語は、ゲルマン語でリンゴを意味するApplaがApfulになったり、ウムラウトが見られたりするようになったりと、この時代の変化は現代の方言の違いにも残っている。中世以降、ドイツでは深い谷や高い山が点在する自然環境と、多数の小国に分かれていた政治制度の影響で、地域ごとに独特の方言を形成していき、ドイツ語は長い時間をかけてさらに細分化されていった。
現在の標準語の基礎が成立したのは16世紀、1522年に宗教改革者のマルティン・ルターが聖書をドイツ語翻訳したときのことである。ルターの目的は、それまでラテン語かギリシャ語しかなかった聖書を、誰もが読むことのできるドイツ語に翻訳すること。しかしドイツには英国でいうロンドン、フランスでいうパリのような政治的・文化的な中心地がなかったため、各地方の方言が分立した状況で標準ドイツ語が存在していなかった。ルターが形作ったドイツ語は、低地ドイツ語の語彙を取り入れつつも、高地ドイツ語をベースにしたものだった。
近世になると、標準ドイツ語は書き言葉としてさらに発達。その発展にはザクセン宮廷に仕えた書記官や作家が貢献したため、標準語はザクセン方言とプファルツ方言の影響を大きく受けている。この段階で方言は書き言葉から排除され、標準ドイツ語は統一された文法と発音を備えるようになる。さらに1920年代にラジオが導入されると、話し言葉でも標準語が普及していった。一部の方言は時代の流れの中で淘汰されていった一方で、今日でもドイツには約20の方言が存在し、それぞれ方言協会がある。特に地方では方言は日常的に使われており、村単位で発音の違いが見られることも。次ページでは、そんな彩豊かなドイツの方言をピックアップしてご紹介する。
参考:Planet Wissen「Deutsche Geschichte: Dialekte」、All About「ドイツ語の歴史!これだけは知っておきたい重要ポイント」
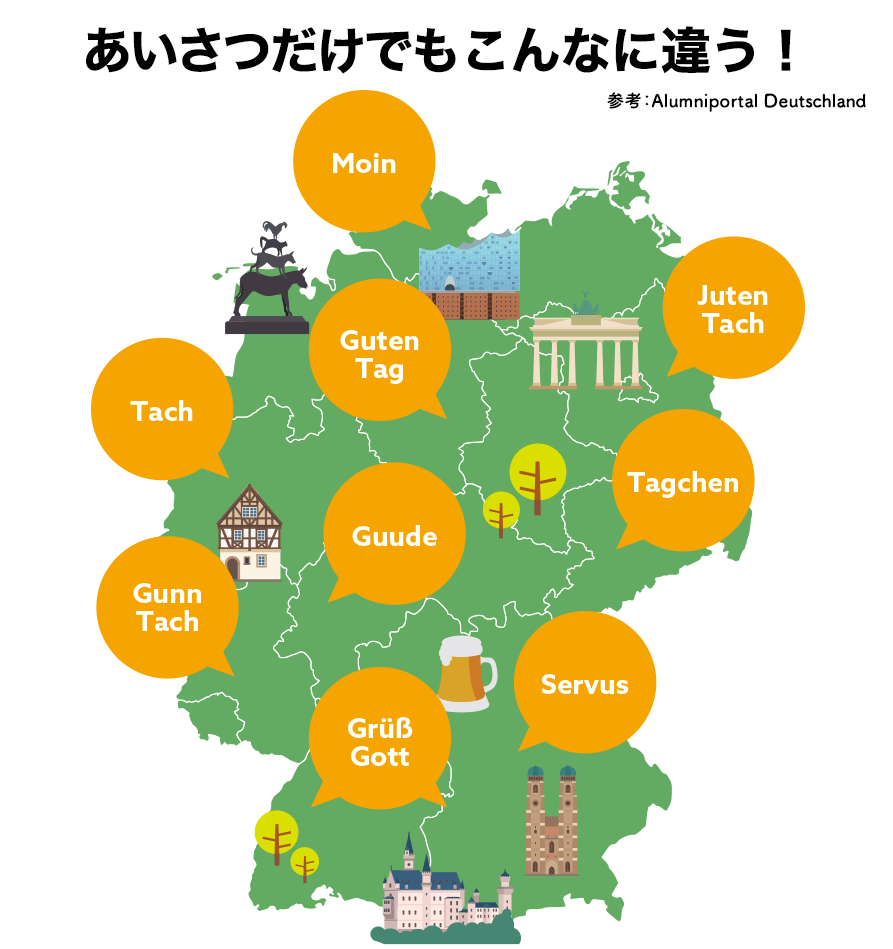
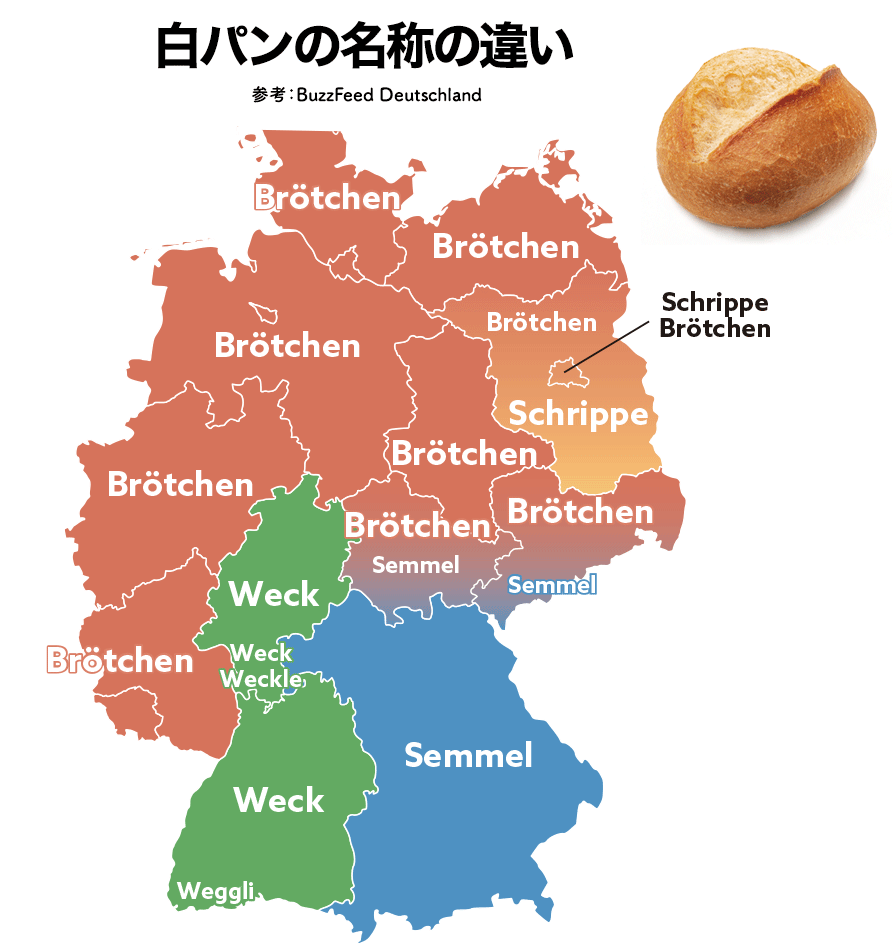
外国語を学ぶくらい 難しい!?ドイツの主な方言リスト
およそ20あるといわれるドイツの方言の中から、現在も話者が多いものを中心にご紹介。標準語とのあまりの違いにもはや外国語では……と思ってしまうが、かつて小国に分かれていたドイツの歴史が色濃く反映されていると感じられる。それぞれの方言の特徴を知っておけば、旅先でも役に立つことがあるかも⁉
参考:PONS「Deutsche Dialekte」、Baden-Württemberg「Vielfältige Sprachlandschaft Dialekte」、Babbel、mdr「Ist Sächsisch das eigentliche Deutsch?」、Deutschlandfunk Kultur「Mundart: Die Berliner Schnauze ist auf dem Rückzug」、Hessen Tourismus「Der Hessische Dialekt」
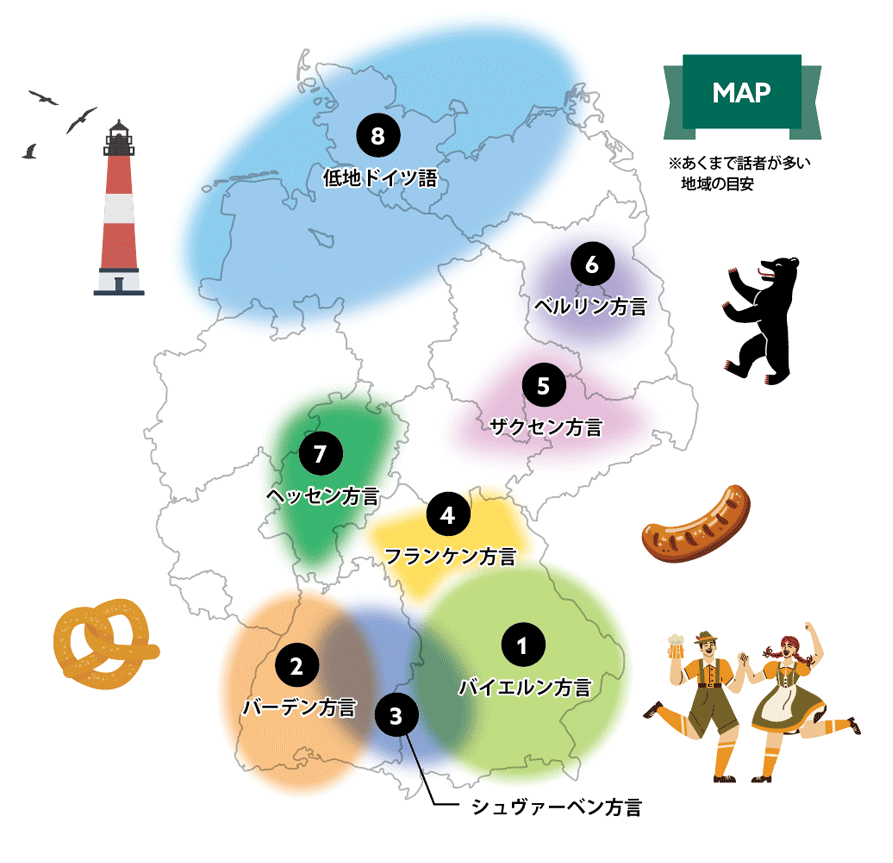
❶バイエルン方言
Bayerisch
バイエルン方言はもともと高地ドイツ語とは別の言語だが、標準ドイツ語やさまざまな方言が合わさって形成されている。バイエルン州以外でもオーストリアやスイスで話されており、話者はおよそ1300万人いると推定されている。
主な特徴
- 一般的に「ei」が「oa」になる hoaß(heiß /熱い)
- 「母音+r」が「a」になる oba(ober /上)
- 「k/p/t」が「g/b/d」になる Dopf(Topf /鍋)
- 時制の使い方が異なる
例えばこんな方言
Dangschee/Bittschee(Danke schön/Bitte schön)
例) Ein Weiße bittschee.
白ビールください。
Ja mei!
「仕方ない」「どうでもいい」などを意味し、日常的によく使われる表現。
❷ババーデン方言
Badisch
バーデン=ヴュルテンベルク州ではシュヴァーベン方言が最も話されているが、それ以外の方言を総称してバーデン方言という。カールスルーエなどで話されている南フランケン方言や、フライブルクなどで話されているアレマン語などが含まれる。
主な特徴
- 「st」が「sch」になる machsch(machst /する)
- 「a」が「o」になる mogsch(magst /好き)
- 単語の多くがフランス語由来
例えばこんな方言
Weggle(Brötchen/白パン)
例) A Weggle oder a Bretzele?
白パンとブレーツェル、どっちがいい?
外部から来ると分からない定番方言
Schnoog(Stechmücke/蚊)
例)Dea Schnoogeschdich beißd mi ganz aag.
蚊に刺されたところがすごくかゆいんだ。
❸シュヴァーベン方言
Schwäbisch
ドイツ南西部の方言で、大きな都市ではシュトゥットガルト、オーストリアのチロル州の一部でも話されている。柔らかい響きを持つが、冠詞や母音が聞こえづらいため、理解しづらいともいわれる。
主な特徴
- 「st」が「sch」になる hasch(hast/持つ)
- 「a」が鼻音化する naahogga(hinsetzen/座る)
- 「ö/ü」が「e/i」になる effendlich(öffentlich /開かれた)
- 「k/p/t」が「g/b/d」になる Babba(Papa/パパ)
- 冠詞が一部異なる dr Budder(die Butter /バター)
- 指小辞に「-le」を使う Häusle(Häuschen /小さい家)
- 「wir」が「mir」になる
例えばこんな方言
Herrgottsbscheißerle(Maultaschen/マウルタッシェン)
直訳では「神を欺く」ことを意味するが、かつて肉食が禁じられた金曜に肉を隠すために作られた料理だったいう説から、シュヴァーベン地方ではこの名で呼ばれている。
Mir könnet älles. Außer Hochdeutsch.
1999年にバーデン=ヴュルテンベルク州が掲げた伝説的なスローガン。意味は「私たちは何でもできます。標準ドイツ語以外なら」。
❹フランケン方言
Fränkisch
いわゆるフランケン地方(バイエルン州北西部)の方言で、ニュルンベルクやアウクスブルクでも話されている。古くはフランク王国で話されていた言語であり、アルザス語やルクセンブルク語もフランケン諸語に分類される。
主な特徴
- 「r」が強めの巻き舌になる
- 「k/p/t」が「g/b/d」になる Fränggisch(Fränkisch/フランケン)
- 語尾が「-ng」になる Abodeng(Apotheke/薬局)
- 指小辞に「-la」を使う Laabla(Brötchen/白パン)
例えばこんな方言
Allmächd!(Oh Gott!/ああ、神様!)
驚いたときなどに使う感嘆詞。この叫び声を上げている人は間違いなくフランケン地方の人。
Broudwoschd(Bratwurts/焼きソーセージ)
ニュルンベルガーソーセージで有名なニュルンベルクでは特に日常的に使われる言葉。現地ではDrei im Weggla(3本入りパン)を注文しよう。
❺ザクセン方言
Sächsisch
ルターはザクセン方言をもとに標準ドイツ語を形成したとされている。一方で東ドイツ時代のエリート層がザクセン方言を話していた影響などもあり、最も人気のない方言の一つ。母音は丸く、子音は柔らかく発音し、旋律的なアクセントで話すのが特徴。
主な特徴
- 「a」が「o」になる Orbeit(Arbeit/仕事)
- 「st」が「scht」になる bischt(bist)
- 「k/p/t」が「g/b/d」になる Abbl(Apfel/リンゴ)
- 「sch」が「ch」になる Breedschn(Brötchen/白パン)
- 単語同士がつながる hammer(haben wir)
例えばこんな方言
Bämme(Stulle/オープンサンド)
ザクセン地方の人々にとってBämmeは、皆で一緒に食べる文化遺産ともいうべき存在で、ただのオープンサンド以上に意味を持っている。
Modschegiebschen(Marienkäfer/てんとう虫)
例)Gugge ma, de Modschegiebschen!
見て、てんとう虫だよ!
❻ベルリン方言
Berlinerisch (Berliner Schnauze)
大都市ゆえにさまざまな方言や言語が混ざってできた方言で、もともと労働者階級が使っていた。東西分断時代、西ベルリンでは学校でベルリン方言を話すことは不適切とされていたが、東ベルリンでは「労働者と農民の国家」を掲げていたため、許容されていた。
主な特徴
- 「g」が「j」になる janz(ganz/まったく、完全に、全体の)
- 二重母音になる een(ein/一つの), ooch(auch/~も)
- 「pf」が「p」になる Appel(Apfel/リンゴ)
- 独自の代名詞(ich=ick, es=et, das=dit, was=watなど)
- 4格がしばしば3格になる(Du liebst mich nicht=Du liebst mir nich)
例えばこんな方言
Bulette(Frikadelle/ドイツ風ミートボール)
例)Nu aba ran an de Buletten! さあ、食事にしよう!
Pfannkuchen(Berliner, Krapfen, Krebbl/菓子パンの「ベルリーナー」)
例)Jedes Jahr an Silvesta werden Pfannkuchen jejessen. 毎年大みそかにベルリーナーを食べます。
❼ヘッセン方言
Hessisch
主にヘッセン州で話されているが、さらに五つのグループに細分化される。フランクフルト地域で話されている言葉は、20世紀後半に映画やテレビ用に作られたヘッセン風の方言で「Medienhessische」(メディアヘッセン方言)とも呼ばれている。
主な特徴
- 「pf」が「p」になり、「b」が続く Äbbelwoi(Apfelwein/アップルワイン)
- 「sch」が「ch」になる Fich(Fisch/魚)
- 所有格の使い方が独特(Ulis Bruder=em Uli sei Brouder)
例えばこんな方言
babbele(sprechen/話す)
名詞の「Babbelsche」はおしゃべり好きの人のことを指す。
Dudd(Tüte/袋)
例)Brache se ne Dudd? 袋にお入れしましょうか?
❽低地ドイツ語
Plattdeutsch
標準語とは別の言語で、北ドイツを中心にドイツで最も多くの話者がいる方言。オランダ語とも近い。現在は話せる人が少なくなっているが(詳しくは下記)、日常的な会話では単語レベルで使われていたり、お店の看板に残っていたりする。
主な特徴
- 「地域が幅広いため、さらに細かく分類される
- 「f」が「p」になる slapen(schlafen/眠る)
- 「ch」が「k」になる ik(ich/私)
- 「schp/schm」が「sp/sm」になる smeren(schmieren/塗る)
- 独自の代名詞(er=he, sie=se, das=dat, wir=wiなど)
- 過去分詞にge-がつかない(getan=daan
例えばこんな方言
Moin(Hallo/こんにちは)
昼夜問わず使えるあいさつで、元々の意味は「心地よい、良い、美しい」など。
Schlackermaschü(Schlagsahne/ホイップクリーム)
「今年の低地ドイツ語2025」に選ばれた。広義の意味ではクリーミーなデザートのことを差し、家庭でも使われる言葉。
方言はいつかなくなってしまうのか?
時代の流れとともに方言を話す人は少なくなり、地域によるアクセントやイントネーションの違いは残るものの、いつかドイツは標準語を話す人しかいなくなってしまうのだろうか……。そもそも方言とは人々にとってどんな存在であるかを紐解きながら、方言の未来について展望する。
参考:WELT「Sind deutsche Dialekte vom Aussterben bedroht?」、t-online「Sprachforscher über Dialekte "Für einen Süddeutschen ist das diskriminierend"」、Babbel「Warum du stolz auf deinen Dialekt sein solltest」、NDR「"Platt mit Beo": Leicht Plattdeutsch lernen mit einer Lern-App」、NDR「Wie Grundschulen versuchen, Plattdeutsch am Leben zu halten」
方言を話す人が減少 背景に差別や偏見も
言語学習プラットフォーム「Babbel for Business」の2024年の調査によると、ドイツ人の約60%は方言を習得していることが分かった。そのうち半数が55歳以上であり、24歳未満のZ世代では方言を話す人はわずか5%にとどまる。方言を話す人が減少している背景には、いくつかの理由がある。一つは、学業や職業上の成功のため、多くの親が子どもに方言を教えなくなっていること。さらに、移動の自由が高まったことで標準語を話す人が増えていることも挙げられる。メディアによる標準語の普及もまた、方言の消滅に拍車をかけてきたといえる。
職場や学校では、標準語を話すことが望ましいとされてきたが、その背景には方言を理由とする差別がある。方言で育った子どもはかつて、文法習得の遅れやスペルミスが増えるなど、学校の成績に悪影響を及ぼし、不利になると考えられていた。方言を話す人は知能的に劣っているという印象を持たれる傾向があり、実際に差別されたことがある人も決して少なくないのである。また方言を話すことによって、どこの出身の人であるか見当がつくため、人物像への偏見を持たれることも。しかし今日、方言の習得は外国語を学ぶのと同じように認知能力の向上につながるとの研究もあり、そうした偏見は以前に比べて少なくなってきている。
方言を話す人々の本音
- 64%のドイツ人が方言は家庭や故郷と密接に結び付いていると考えている
- 73%のドイツ人がドイツ語の多様性を高く評価している
- 70.5%のドイツ人が方言よりも標準語が仕事に向いていると考えている
- 8.7%の人が、方言を理由に見下されてたり差別を受けたりしたことがある
参考:WELT「Sind deutsche Dialekte vom Aussterben bedroht?」
下記は中部ドイツに限る
- 86%の人が方言を保存したいと考えている
- 11%の人が旅行先で方言を話して不快な思いをしたことがある
- 47%の人が標準語を話すことにメリットを感じている
- 46%の人が標準語を話すことにメリットを感じていない
参考:mdr「Mehr Jüngere sprechen Dialekt als Ältere」
方言話者に持たれやすい印象の例
- ベルリン方言:生意気、気さく
- シュヴァーベン方言:節約好き、居心地がいい、地道で誠実
- ケルン方言:誠実、率直
- 低地ドイツ語:無口、ユーモアがないわけではない
- バイエルン方言:基本的に温厚、軽視されるのが嫌
方言を守ることは自分と文化を守ること
比較的新しい考え方として、「Regiolekt」(地域方言)という言葉がある。地域方言は、地域的な影響を受けた口語表現のことを指し、例えばヘッセンで「ich」は「isch」と発音されることや、ベルリン方言やルール地帯方言もこれに該当する。話者が減少している歴史的な方言とは対照的に、地域方言は今もなお広い範囲で話されている。標準語だと思って使っていたのが実は方言だったということも少なくなく、地域方言を含めれば、若い世代も実は方言を話しているのだ。
歴史的な方言でも地域方言でも、人々にアイデンティティを与え、特定の民族集団への帰属意識を抱かせる役割がある。例えば、旅先で馴染みのある方言を話す人に出会ったとき、どこか温かい気持ちになるのは、故郷とのつながりを感じるからだろう。また、方言にしかない表現やフレーズがあり、方言で悪態をつくからこそ気持ちがこもる場合もある。さらに、方言はその地域の文化や慣習とも深く結び付いているため、方言が消滅することで失われる文化も出てくるだろう。方言を守ることは、すなわち自分自身のアイデンティティを守ることであり、地域の文化や慣習を守ることでもあるのだ。
方言を未来へつなぐ授業やアプリの導入
上記でも取り上げた低地ドイツ語は、北フリジア語やソルブ語などの少数言語と共に「地方言語または少数言語のための欧州憲章」の保護下にある。特に低地ドイツ語の話者の多い北ドイツでは、低地ドイツ語の保存のためにさまざまな施策が行われている。
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州では、2014年に低地ドイツ語のモデル学校に、ゲルティングのゲオルク・アスムセン小学校を指定。同校では、英語の教育メソッドを低地ドイツ語の授業に活かしているという。例えば、エリック・カール著の絵本『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?』(くまさん くまさん なにみてるの?)を低地ドイツ語で読み、子どもたちは絵本に登場する動物や色を学んでいく。同校では、州からの助成を受け、年に8回の低地ドイツ語授業を実施し、4年生の終わりには送別会で低地ドイツ語の劇を披露。卒業までに子どもたちが少しでも低地ドイツ語を理解し、2~3文でも話せるようになることを目標としているのだという。
お隣のメクレンブルク=フォアポンメルン州では毎年、「低地ドイツ語週間」(Plattdeutsche Wochen)が開かれ、各地で低地ドイツ語によるコンサート、演劇、朗読会などが行われている。また、低地ドイツ語の教師養成にも力を入れており、同州ではおよそ1700人の生徒が低地ドイツ語を学んでいるという。2024年には、語学学習アプリ「Platt mit Beo」をリリース。メクレンブルク=フォアポンメルン州で話されている低地ドイツ語をはじめ、ほかの地域の低地ドイツ語のコースを提供。テキストの読み上げもあり、食事やショッピングなど、日常的なトピックから実践的な低地ドイツ語を学ぶことができる。
100年後には歴史的な方言は消滅するだろうともいわれる。そんななか、全国各地の方言協会は必死になって未来へ方言を残そうと奮闘している。バイエルン方言協会では、将来的にバイエルン方言、フランケン方言、シュヴァーベン方言のアクセントで話すAIの制作を検討中だという。これによって、子どもたちが方言を学べるようにすることが狙いだ。こうした最新技術は、方言を継承していくためにこれからさらに活用されていくだろう。とはいえ、技術だけでは限界がある。最終的には、その地域の人々の方言への愛こそが、方言を守っていく原動力になるのかもしれない。
低地ドイツ語を楽しむ演劇体験
ハンブルク中央駅前にあるオーンゾルク劇場では、低地ドイツ語による劇作品を中心に上演している。オーンゾルク劇場版『ふたりのロッテ』(Das doppelte Lottchen)は、ロッテが双子の妹に低地ドイツ語を教える演出があり、観客も一緒に低地ドイツ語を学ぶことができる。2025年9月28日~11月16日まで上演予定。
www.ohnsorg.de
 オーンゾルク劇場
オーンゾルク劇場
 『ふたりのロッテ』(Das doppelte Lottchen)
『ふたりのロッテ』(Das doppelte Lottchen)



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック







