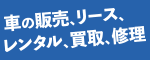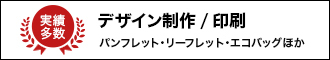今年のベルリン国際映画祭(ベルリナーレ)のメインテーマは「グローバリゼーション」に尽きた。国際的な共同制作や数カ国でロケをした映画、地球規模の問題を扱った作品が目白押し。しかし、多くの作品が提示したのは、グローバル化への賛同よりも懐疑だったように思われる。特に、資本主義経済の弊害がたくさんの作品に反映されていた。また、巨視的に社会を見る立場が必ずしも賢明なわけではないと思わせる作品も少なくなかった。
一方で、国際映画祭というイベントを1つのグローバル化現象として捉えると、上映される映画の1本1本が鎖のように連鎖して、まるで1つの壮大な地球叙事詩を語っているかのようだった。観客は作品に導かれ、オデュッセウスさながら、地球の住み心地を試す旅に出かけた。世界の状況、映画産業の現状のみならず、映画の芸術としての国際的な発展をも一望に収めるこの映画祭こそ、グローバリゼーションを最も理想的に実現している場所の1つかもしれない。
(映画研究者:足立ラーベ加代)
Fotos:©Internationale Filmfestspiele Berlin
国際映画部門受賞作
| 金熊賞 | La teta asustada (The Milk Of Sorrow) 監督:Claudia Llosa |
|
| 銀熊賞 | Alle Anderen (Everyone else) 監督:Maren Ade |
|
| Gigante 監督:Adrián Biniez |
||
| 銀熊 最優秀監督賞 | Asghar Farhadi 作品:Darbareye Elly (About Elly) |
|
| 銀熊 最優秀男優賞 | Sotigui Kouyate 作品:London River 監督:Rachid Bouchareb |
|
| 銀熊 最優秀女優賞 | Birgit Minichmayr 作品:Alle Anderen (Everyone else) 監督:Maren Ade |
|
| 銀熊 芸術貢献賞 | Gábor Erdély & Tamás Székely 作品:Katalin Varga 監督:Peter Strickland |
|
| 銀熊 脚本賞 | Oren Moverman & Alessandro Camon 作品:The Messenger 監督:Oren Moverman |
|
| アルフレッド・バウアー・ プライス |
Gigante 監督:Adrián Biniez |
|
| Tatarak (Sweet Rush) 監督:Andrzej Wajda |
||
戦犯裁判と人権問題を考える

The Reader
英国人監督スティーブン・ダルドリーによる、ドイツ人作家ベルンハルト・シュリンクのベストセラー小説「朗読者」を映画化した「The Reader」(愛を読むひと)は、国際色豊かなキャスティングとロケーションで話題を呼んだ。少年時代、年上の女性ハンナとひとときの恋に落ちた主人公ミヒャエルが、後に彼女とナチス戦犯裁判の法廷で再会するというドラマチックな物語である。映画版は過度なメロドラマに陥ることもなく、原作の仕掛ける人間性への問いを丁寧に拾い上げている。同じ戦犯裁判ものでも、日本で昨年にリメイクされた「私は貝になりたい」よりはよほど良識がある。ケイト・ウィンスレットの演じる、人並みの教育を受ける機会を逸した人間の悲哀には胸が塞がれる。知性に妨げられてハンナの心を受け止められないミヒャエルの愚かさも重く伝わってくる。
この作品がただの恋愛ものであったなら上出来だったかもしれないが、アウシュビッツを通俗的に語るがゆえの難点は到底カバーできず、「史上最悪のホロコースト映画」と厳しい批判に晒された。確かに、原作中のハンナを始めとする人物設定の不謹慎さは、以前から物議を醸していた。

Storm
ドイツのハンス・クリスチャン・シュミット監督の「Storm」(嵐) は、オランダ・ハーグの国際戦犯法廷での1件を題材にしている。ある女性検察官が、旧ユーゴ軍によるボスニア女性に対する性的虐待を公訴するが、裁判が進むにつれて証人の証言に矛盾が生じる。この判例を巡る非常に複雑な国際法上の手続きが、重厚なドラマとして繰り広げられる。観客は不条理な社会システムの中で主人公たちとともに考え、可能性を模索する立場に立たされる。ヨーロッパ統合の機運の中で正義が必ずしも通用せず、真実がタブー化されていることを論理的かつ具体的に解明していく知的な作品だ。
★「Storm」(嵐) ドイツ映画館ギルド賞、アムネスティ・インターナショナル賞、ベルリーナー・モルゲンポスト紙読者賞受賞
記録映画
また、シュミット監督は記録映画「Die wundersame Welt der Waschkraft」(クリーニングの不思議な世界)も出品した。ベルリンのほとんどの大型ホテルが、シーツ類の洗濯をすべてポーランドに発注しているという話だ。グローバルな市場経済の不正を扱いながらも、こちらはやや批判力に欠けた作品になっている。

Zum Vergleich
それに比べ、ハルン・ファロッキ監督(ドイツ)の記録映画「Zum Vergleich」(比較)は評価が高かった。各国における建材ブロックの製法を、コメントを一切入れずに比較するという作品だ。インドでは、人の流れ作業によって泥を固めて焼く古来の方法が守られている。スイスでは、不気味なほど細かい工程を機械がすべてこなし、無人の作業場に金属音ばかりが響く。現代におけるシュールなまでの人間疎外の状況を冷徹に観察する映画である。
2人の巨匠 ─ アンゲロプロスとワイダ

I skoni tou chronou
今回の映画祭で最も遠大な時空旅行を実現したのは、73歳のギリシア人監督テオ・アンゲロプロスによる20世紀3部作の第2部「I skoni tou chronou」(第三の翼)であろう。(第1部は2004年の「エレニの旅」)スターリンの死に揺れるモスクワに始まり、カナダ、アメリカ、イタリアを経て世紀末のベルリンで終わる。ウィリアム・デフォー扮する映画監督が、彼の両親の物語を映画化することを企画する。両親を演じるのはイレーネ・ヤコブとミシェル・ピコリ。戦前にギリシアから旧ソ連に亡命した彼らが送った、波瀾万丈の人生を描く。
残念なことにこの作品は、世界的巨匠の大プロジェクトでありながら、いささか空疎でメランコリーに惑溺したものとなった。特にベルリンの描写が平凡だったのが惜しまれる。もちろん群衆シーンの劇的なコリオグラフィー、流麗なカメラワークは健在なのだが。第3部で物語がどのように再生されるかに期待したい。

Tatarak
これと対照的だったのは、82歳のポーランド人監督アンジェイ・ワイダの新作「Tatarak」(Sweet Rush)の瑞々しさだった。医師の妻で、2人の息子をワルシャワ蜂起で失った中年女性マルタは、自らも病と死の影に脅かされている。彼女がある日出会った若者は、彼女にもう1度生の輝きを与え てくれるのであった。
この女主人公を演じるのが、ワイダの「大理石の男」(1977)に出演した当時と変わらない美貌のクリスティナ・ヤンダである。彼女は「Tatarak」の撮影中に、夫でカメラマンのエドワルド・クォシンスキと死別している。この映画には、ヤンダが自分自身を演じ、夫の最期の日々の様子を延々と独白するシーンが幕間劇のように挿入されている。ワイダ監督は、名作「全て売り物」(1968)でも映画と現実をクロスさせる独特の手法を用いているが、「Tatarak」でフィクションの中から現実が突然変異のように飛び出してくるシーンは鮮烈であった。
「白樺の林」(1970)で表現されたように、死は残酷に人の運命をせせら笑うが、「全て売り物」のように、力強い生によって克服されるという楽観主義が、この作品の深い水脈から沸き起こるようだった。
★「Tatarak」アルフレート・バウアー賞受賞
ドイツ的テーマ─「ドイツ09」と「マテリアル」

Deutschland 09
1977年に起こったドイツ赤軍による一連のテロ事件と幹部の謎の獄中死を受け、当時のドイツの映画監督たちが「秋のドイツ」(1978)というオムニバス映画を撮ってから30年が過ぎた。それに呼応する作品として誕生したのが、現代ドイツを代表する13人の監督による共同製作「Deutschland 09」(ドイツ09)である。特別なきっかけもないのに何のために作ったのか、などと辛口評が目立ったが、意外と面白いものだった。
拍手がひときわ大きかったのは、ダニエル・レヴィ製作のパートだった。監督自身が主演し、薬物を使ったのは、「秋のドイツ」で最も過激だったファスビンダー監督作品を意識したのかもしれない。鬱に悩まされる監督が医者に薬を処方してもらうと、途端に街がバラ色に見えて隣人が皆親切になるという、ベルリンに住む人なら思わず共鳴してしまうような話だ。
国家全体を病院に見立て、患者の症状を政治経済の問題に例えたヴォルフガング・ベッカー製作の短編は、批判精神が旺盛すぎて記者会見では敬遠されているような印象を受けた。兄の埋葬を禁じられるアンティゴネーの悲劇(ギリシア神話)とテロリストの運命を重ねた「秋のドイツ」でのシューレンドルフ作品を彷彿とさせる。
現代におけるフェミニズムの実体を改善するために1969年にタイムスリップし、当時先端を行った社会運動家であり、子を持つ母でもあった2人の女性思想家、ウルリケ・マインホフとスーザン・ソンタグの対話を実現させたニコレッテ・クレービッツの作品は、アイディアで断然光っていた。
この企画の発起人であるトム・ティクヴァ監督が描く、世界中どこに行っても判を捺したように同じ行動しかできないドイツ人ヤッピーのせせこましさについ笑ってしまうのは、外国人の意地悪な見方かもしれない。フランクフルター・アルゲマイネ紙のレイアウトの刷新に憤る人物についての断片など、ドイツ人独特の複雑な心理を感じさせるパートもあった。ローカル色が面白い作品でありながら、国という単位でものを考えることの限界をも実感させる。今後の一般公開でどのような反響があるか楽しみである。

Material
「Deutschland 09」に対して上がった批判の1つに、旧東ドイツの問題についてまったく言及がないというものがあった。この欠如を補って余りあったのが、トーマス・ハイゼ監督(ドイツ)の記録映画「Material」(マテリアル)だった。映画祭期間中、何度もアンコールがかかった作品である。80年代終わりから現在に至る東ベルリンの状況を、インサイダーの視点から赤裸々に記録した初公開の映像集だ。決起集会とデモの日常、秘密警察の狼狽、ネオナチ青年たちの反乱、共和国宮殿の取り壊し……。この作品を観ると、私たちが見たドイツ統一のプロセスは西側のマスコミによって操作されたイメージに過ぎなかったことに気付かされ、愕然とする。
特別企画「冬よさらば」と70mm映画

Kutya éji data
東西ドイツの統合は、グローバリゼーションを大きく前進させた大事件だった。壁崩壊20年目の節目を記念して今回の映画祭では、「Winter Adé」(冬よさらば─改革の前触れ)と題し、冷戦終結直前に東欧からベルリンにやって来た革新的な映画の特集が組まれた。「Winter Adé」(冬よさらば)は、ヘルケ・ミッセルヴィッツ監督(ドイツ)による、旧東ドイツの暮らしを追った素朴なドキュメンタリー(1988)のタイトルで、初めて市民の素顔と本音が伝えられたと評判を呼んだ。さらに、自国での映画製作の将来を儚んで1985年に自殺したハンガリーの鬼才ガボア・ボディ監督の 「Kutya éji data」(The Dog's Night Song, 1983)などを含め、ベルリンの映画ファンにとっては懐かしい名作が揃った。このプログラムは今年ドイツ各地に巡回されるという。
70mmフィルムを特集したレトロスペクティブ部門も大盛況だった。映画フィルムのスタンダードサイズは35mmであり、70mmというと幅が倍のワイドスクリーンになる。標準フィルムに画像を細長く凝縮して焼き付け、上映時に引き延ばすシネマスコープとは違った贅沢な規格だ。代表作として、今回上映された「ベンハー」「クレオパトラ」「アラビアのロレンス」「2001年宇宙の旅」がある。

Goya
旧東ドイツの巨匠コンラート・ヴォルフ監督の伝記映画「Goya」(ゴヤ、1970)は、中でも珍しい作品だった。大判キャンバスと華やかな色彩のリアリズムで描かれたゴヤの絵を70mm映画の手本にしているのだ。彼の代表作「カルロス4世の家族」が大画面いっぱいに登場するシーンは圧巻である。ただ大きければ良いというものではないが、画面の大きさを存分に利用した、コンセプトのある作品はエキサイティングで、映画館はパーティー会場のように盛り上がっていた。主催者はこれを機に、70mm規格をベルリンの映画館で復活させると請け合った。
実験映画部門の発展 「映画としての映画」 というステイタス
商業主義が前面に押し出された映画祭のメジャーなプログラムに背を向けるようにして、実験映画部門では真剣に映画の芸術性を論じるレクチャーが重ねられた。
ゲストに、現代ドイツ・アヴァンギャルド映画の先駆者であり、「生の映画」(1968)で有名なビルギット・ハインが招かれた討論会「映画としての映画」は、実に聞き応えがあった。劇映画とは違い、ストーリーのない、純粋に視聴覚的表現の発展を目指した実験映画というものを芸術として一般に認知させるまでに、いかに長い受難の時代があったかという話は、芸術家たちが常に時代を先取りしていることを確信させた。また、当時から受け継がれる作家たちの国際的な連帯が、今の実験映画の隆盛を支えていることも明らかにされた。

Sense of Architecture
この部門の参加作品の充実ぶりは素晴らしかった。オーストリアのグラーツ市の現代建築の数々を傾いた不動のカメラで撮影したハインツ・エミッヒホルツ監督の「Sense of Architecture」を観た後は、傾いていない映像がかえって不自然に感じらるほど、完璧な構図を堪能できた。観客席にいた1人の老婦人は、「私も1軒の家に住んでいるが、建築が言語を持つとは知らなかった。今後はコミュニケーションを試みる」と粋なコメントをしていた。
ビル・ヴィオラのビデオ インスタレーション
Bill Viola
映画祭のメイン会場からやや離れたギャラリーには、ビデオアートの第1人者ビル・ヴィオラのビデオインスタレーションが展示されていた。宗教画を思わせる数種の縦長のビデオパネルが並び、画面の奥からモノクロームの人影が近づいてくる。画面の前景には薄い滝のような水のヴェールがあり、それをくぐると人物の姿が突然鮮明なカラーを帯びる。そしてびしょ濡れの人物は、画面前方にある何かに驚いたような表情をする。人物によっては怖れを露にしていたり、がっかりした様子だったり、ハッとしたようだったり、表現が微妙に違っている。
この画面の手前の空間、つまり私たち観客がいる場所に彼らは何を見たのだろうか。それはまるで、これからの映画祭の方向性や映画というメディアの将来、そして地球の未来をも暗示しているかのようだった。
小宇宙の豊潤さ ─ 各国の作家映画 ─
ワイダ監督作品のように、個性的な語り口で深遠な小宇宙を創出する、いわば反グローバル的でありながら普遍的なテーマを扱った作品が、今回の映画祭では異彩を放っていた。
エハ・エルデム監督

Hayat var
エハ・エルデム監督の「Hayat var」(My Only Sunshine)は、イスタンブールに住む14歳の少女ハヤトの日常を描く。彼女は寝たきりの祖父と売春斡旋や麻薬密売を生業とする父とともに、最底辺の暮らしをしている。学校でのいじめ、近所の大人からのセクハラに悩まされるハヤトだが、それでも自分なりに反撃するし、守護天使のような仲間を従える。厳しい現実から少女の自由への野心が殻を破るように解放されてゆく過程が、ファンタジックに描かれている作品。また、水の都を海や川の側から眺めるカメラの視点は、思春期の心の揺れを繊細に捉えていた。
★「Hayat var」(My Only Sunshine) ターゲスシュピーゲル紙読者賞受賞
フレデリック・ヴェンツェル監督
ヘンリック・ヘルストローム監督

Man tänker sitt
クチコミで評判が広まり、急きょ再上映が決まったフレデリック・ヴェンツェルとヘンリック・ヘルストローム監督の「Man tänker sitt」(Burrowing)はリアルでありつつシュールな、新感覚の映画だった。田舎町に住む、ドロップアウトした不可解な大人たちと、彼らに付き合わされる子どもと赤ん坊の、他愛無い日常が叙情的に描写されている。子どもの意識で見て語られる世界には、何の論理も脈絡もないように思われる。ところが、それが子どもの時間の豊かさと、大人の世界の深い孤独を対比させ、観客はいつの間にか、北欧の森に囲まれた集落の小市民の暮らしにどっぷりと浸り込む。
洪榮傑 監督

無聲風鈴
洪榮傑(Kit Hung)監督の「無聲風鈴」 (Soundless Wind Chime)は、香港を舞台にした、1人の中国人青年と双子のようにそっくりな2人のスイス人男性が繰り広げるラブストーリーである。些細な諍いと和解の繰り返しにも見えるが、非常に観念的な恋物語であることが次第に解き明かされてくる。三島由紀夫の「豊饒の海」にも似た恋人の転生や不滅の愛というテーマが、現代的かつ国際的に展開する。ガラス細工のように繊細に入り組んだ時間構成は、アラン・レネの「去年マリエンバードで」を想起させた。映画史的に興味深いドッペルゲンガーが登場する、謎めいた男のメロドラマである。
園子温 監督

愛のむきだし
園子温監督の4時間に及ぶ高校生の純愛物語「愛のむきだし」も非常に評判が高かった。性的倒錯、自傷、虐待、カルト、盗撮など、日本社会のスキャンダラスなキーワードをピックアップして表面的になぞっただけで長丁場をもたせるストーリーができているのは驚異的だ。マンガのように軽くて速い知覚のプロセスに、アングラ文化のグロテスクが盛り込まれた、個性的な娯楽作品になっている。しかし、ミニマル・シネマの傑作「部屋」(1994)の大ファンとしてあえて言わせていただければ、若者文化と戯れる今の子温さんのスタイルは、世を欺いた仮初の姿であってほしい。
★「愛のむきだし」 カリガリ賞 国際批評家連盟賞受賞



 インベスト・イン・ババリア
インベスト・イン・ババリア スケッチブック
スケッチブック